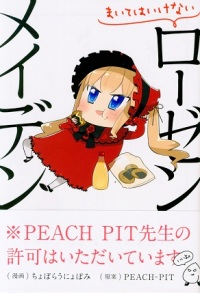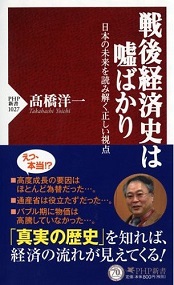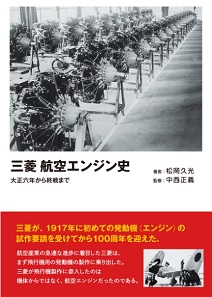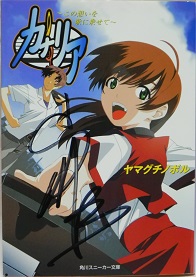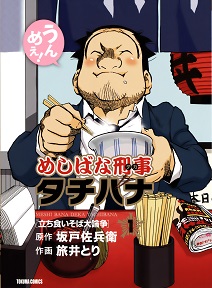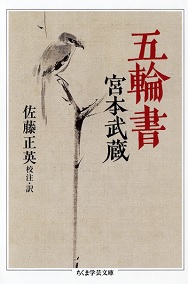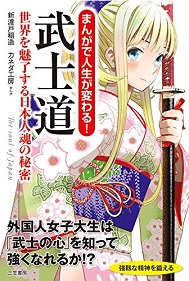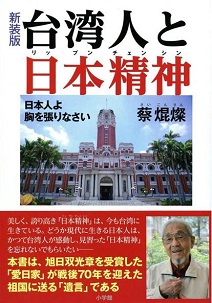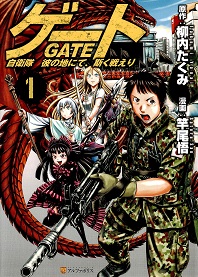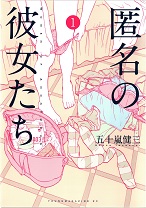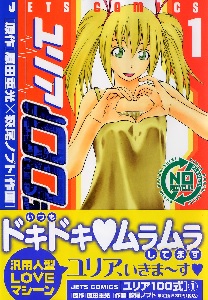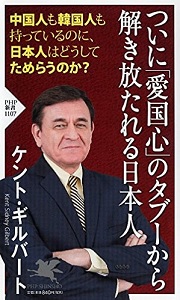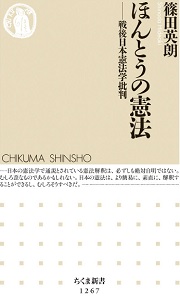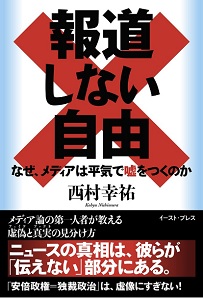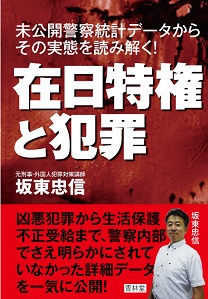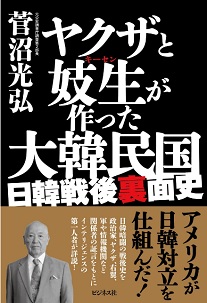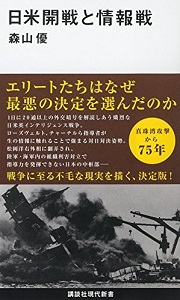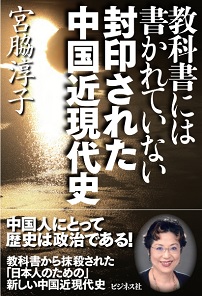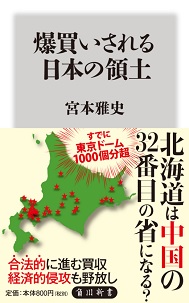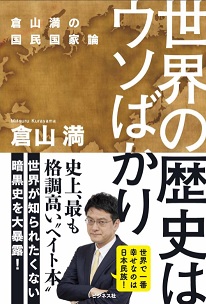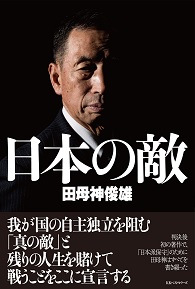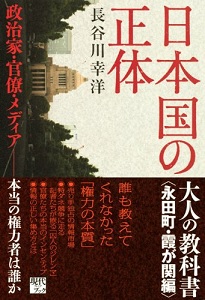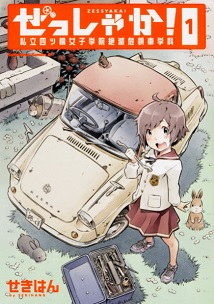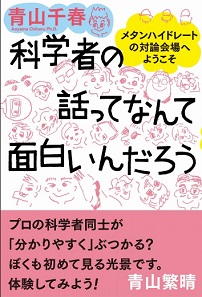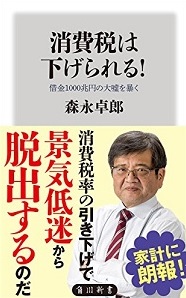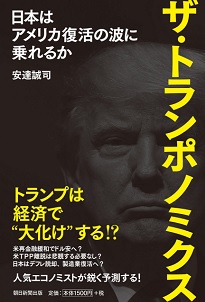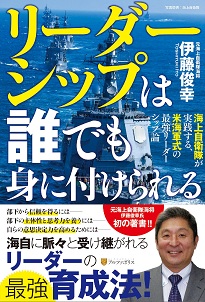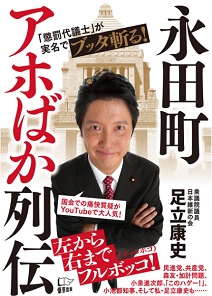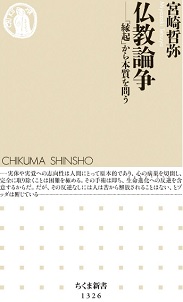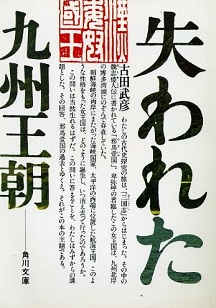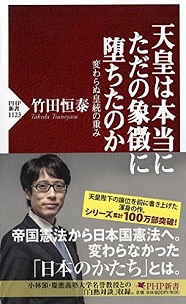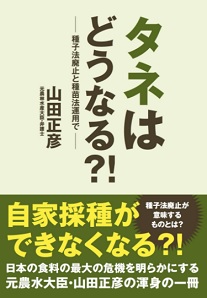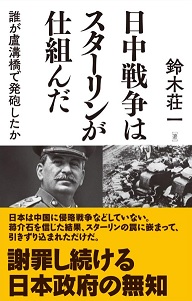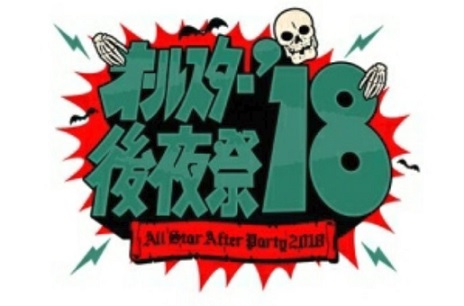今年の1月下旬頃より、地元でチラホラと見かける様になってきたかと思いきや。数ヶ月と経たず、その増殖の勢いとどまること知らず。気がつけば、すれ違うタクシーの大半が約22年ぶりにタクシー向け新型車両として市場に投入された『JPN TAXI』なる車両に入り替わっているではないか。なんでも、昨年(17年)10月に発売して以降、今年の3月末時点までに全国で約4,000台を販売しているんだとか。その内の2,000台弱が都内タクシー会社が購入しているんだそうな。これにより、都内の法人タクシー3万台の内、約7%相当が新型タクシーこと、『JPN TAXI』なる車両になっているそうです。そんな『JPN TAXI』なる車両。エクステリアが二重舌、三重舌外交と、全世界で喧嘩をふっかけていない所を探すのが困難ではあるが。何故か表だって、矢面に立たされ批難される事の少ないジェントルなお国で走っていそうな車両を彷彿とさせるデザインなんですけどね。どうにも
今年の1月下旬頃より、地元でチラホラと見かける様になってきたかと思いきや。数ヶ月と経たず、その増殖の勢いとどまること知らず。気がつけば、すれ違うタクシーの大半が約22年ぶりにタクシー向け新型車両として市場に投入された『JPN TAXI』なる車両に入り替わっているではないか。なんでも、昨年(17年)10月に発売して以降、今年の3月末時点までに全国で約4,000台を販売しているんだとか。その内の2,000台弱が都内タクシー会社が購入しているんだそうな。これにより、都内の法人タクシー3万台の内、約7%相当が新型タクシーこと、『JPN TAXI』なる車両になっているそうです。そんな『JPN TAXI』なる車両。エクステリアが二重舌、三重舌外交と、全世界で喧嘩をふっかけていない所を探すのが困難ではあるが。何故か表だって、矢面に立たされ批難される事の少ないジェントルなお国で走っていそうな車両を彷彿とさせるデザインなんですけどね。どうにも 『CROWN COMFORT』 『CROWN SEDAN』なりの従来車両を強く意識してのデザインをしたのか? は不明だが、全体としてのバランスが悪く。国内のデザイン感性ではこれが限界なんかなぁ~なんて見かける都度、にゃんともコレジャナイ感を抱いていたのですが。本家の車体デザインって、どんな感じだったっけかなぁ~っと、画像検索なんかで漁っている。
『CROWN COMFORT』 『CROWN SEDAN』なりの従来車両を強く意識してのデザインをしたのか? は不明だが、全体としてのバランスが悪く。国内のデザイン感性ではこれが限界なんかなぁ~なんて見かける都度、にゃんともコレジャナイ感を抱いていたのですが。本家の車体デザインって、どんな感じだったっけかなぁ~っと、画像検索なんかで漁っている。 基本的なデザインとして、初代『Austin・FX3』のイメージを伝承という形で、幾度とモデルチェンジを経ても何処かしらかに面影を残しつつ、
基本的なデザインとして、初代『Austin・FX3』のイメージを伝承という形で、幾度とモデルチェンジを経ても何処かしらかに面影を残しつつ、 うまく進化をさせることで誰が見ても本家の車両であると認識できる事を思うに。『JPN TAXI』も 以前の車両こと、『CROWN COMFORT』や『CROWN SEDAN』でも。その『CROWN 』系の元祖である
うまく進化をさせることで誰が見ても本家の車両であると認識できる事を思うに。『JPN TAXI』も 以前の車両こと、『CROWN COMFORT』や『CROWN SEDAN』でも。その『CROWN 』系の元祖である 『TOYOPET CROWN(RS型)』を元にデザインを再構築すれば、かなり味のあるエクステリアになるんじゃ……なんて個人的な意見はさておき。この『JPN TAXI』なる車両は『SIENTA(DAA-NHP170G)』をベースに開発された車両なんだそうで、従来の “セダン” とは異なり “コンパクトミニバン” であることから、全高は 1,695 mm と天井が高く、最低地上高も 145 mm(車高⤴パッケージの場合、全高・最低地上高 + 15 mm⤴ 更に185/60R15 & 15×5 ½ Jスチールホイール装着で全高・最低地上高 + 10 mm⤴)と床も低くい事から、乗降車が容易にでき。左側の後部座席ドアも、従来は自動ドア(バキューム式(真空式) or 手動式)とからくり仕立てで便利であった一方、ガードレール等の障害物に接触する危険性があったのてすが。パワースライドドアになったことで、障害物に車を寄せすぎない限り、接触の危険性もなくなり。
『TOYOPET CROWN(RS型)』を元にデザインを再構築すれば、かなり味のあるエクステリアになるんじゃ……なんて個人的な意見はさておき。この『JPN TAXI』なる車両は『SIENTA(DAA-NHP170G)』をベースに開発された車両なんだそうで、従来の “セダン” とは異なり “コンパクトミニバン” であることから、全高は 1,695 mm と天井が高く、最低地上高も 145 mm(車高⤴パッケージの場合、全高・最低地上高 + 15 mm⤴ 更に185/60R15 & 15×5 ½ Jスチールホイール装着で全高・最低地上高 + 10 mm⤴)と床も低くい事から、乗降車が容易にでき。左側の後部座席ドアも、従来は自動ドア(バキューム式(真空式) or 手動式)とからくり仕立てで便利であった一方、ガードレール等の障害物に接触する危険性があったのてすが。パワースライドドアになったことで、障害物に車を寄せすぎない限り、接触の危険性もなくなり。 エンジンも直列4気筒 1,998 L から 直列4気筒 1.496 L と総排気量を落とすもLPG-ハイブリッドシステムを採用することにより従来から動力性能を損なわず、耐久性と燃費性能に加え、フロントバンパー・リアバンパーを3分割バンパーとサイド部分のみの交換も可能な分割構造にしたことで、運行中に誤ってバンパーを擦ってしまった等、パンパーの修理 or 交換修理が必要となってしまっても。傷・損傷のあるバンパーパーツのみの交換で済むので、バンパー丸ごと交換修理……なんて事もなくなるので、交換部品費も低く抑えられるといったコストパフォーマンス面・メンテナンス面にも優れているそうな。更に、ベース車両では10万㎞も走行すればへたってしまう足回りなんかも、年間数万㎞と軽く走行。数年も経つ頃には30~50万㎞とオドメーター表示されているなんて事も珍しくもないタクシーであっても十分に耐えうる足回り等々、乗客や乗務員は勿論のこと。運送業を営む経営側にも納得のいく仕上がりになっているそうな。そんな数ある商品PRポイントの中でも、個人的に最大の注目したいポイントは、何と言っても
エンジンも直列4気筒 1,998 L から 直列4気筒 1.496 L と総排気量を落とすもLPG-ハイブリッドシステムを採用することにより従来から動力性能を損なわず、耐久性と燃費性能に加え、フロントバンパー・リアバンパーを3分割バンパーとサイド部分のみの交換も可能な分割構造にしたことで、運行中に誤ってバンパーを擦ってしまった等、パンパーの修理 or 交換修理が必要となってしまっても。傷・損傷のあるバンパーパーツのみの交換で済むので、バンパー丸ごと交換修理……なんて事もなくなるので、交換部品費も低く抑えられるといったコストパフォーマンス面・メンテナンス面にも優れているそうな。更に、ベース車両では10万㎞も走行すればへたってしまう足回りなんかも、年間数万㎞と軽く走行。数年も経つ頃には30~50万㎞とオドメーター表示されているなんて事も珍しくもないタクシーであっても十分に耐えうる足回り等々、乗客や乗務員は勿論のこと。運送業を営む経営側にも納得のいく仕上がりになっているそうな。そんな数ある商品PRポイントの中でも、個人的に最大の注目したいポイントは、何と言っても “車椅子のまま乗下車が出来る” という点だ。昔程ではないしろ、市内を運転していると『CROWN』系や
“車椅子のまま乗下車が出来る” という点だ。昔程ではないしろ、市内を運転していると『CROWN』系や 『CEDRIC』系等で送迎している “セダン” のトランクルームから車椅子がひょっこりはんっと、収納しきれず走行している光景を見かけたもので。道路の段差を通過する都度、トランクルームの蓋が上下にバウンドする様は……。幾ら車椅子をバンドで固定されている(してない場合もある)とはいえ、さすがにその後続車として走行するのは……にゃんとも。また、1度でも足の不自由であったり車椅子の人を介助なりで乗降車させたことがある方ならば、その大変さは身に沁みることと思いますが……そんな苦労をする or させることなく、車椅子のまま乗降車が出来るとか最高やん♪ しかも、この『JPN TAXI』なる車両は一般ユーザーであっても購入することも可能ときたもんだ!! 例えば将来、自分自身なり家族に~っと、車椅子が必須となった時。各自動車メーカーが通常ラインナップしている車両から福祉車両の回転シート・昇降シート・スロープ・リフター仕様車のいずれかが選択できる車両から買い換えを検討するか。或いは、今現在所有している車両を福祉仕様へカスタマイズする必要があるも。標準で “車椅子のまま乗下車が出来る” 設計になっているこの『JPN TAXI』なる車両であれば、竹中直人の曲なみに心配御無用ですYO(LPG燃料仕様なので、一般ユーザー的にはレギュラーガソリン仕様が欲しいところ。車両価格的に跳ね上がるだろうけど、FCVなんてのもあり?)。今後、現在の愛車にエンジントラブル等、如何ともし難い買い換えに迫られた場合、次の車両選び候補の選択肢に加えてもいいんじゃないないの? ってな具合に、関心を抱き。興味本位で調べてみる。
『CEDRIC』系等で送迎している “セダン” のトランクルームから車椅子がひょっこりはんっと、収納しきれず走行している光景を見かけたもので。道路の段差を通過する都度、トランクルームの蓋が上下にバウンドする様は……。幾ら車椅子をバンドで固定されている(してない場合もある)とはいえ、さすがにその後続車として走行するのは……にゃんとも。また、1度でも足の不自由であったり車椅子の人を介助なりで乗降車させたことがある方ならば、その大変さは身に沁みることと思いますが……そんな苦労をする or させることなく、車椅子のまま乗降車が出来るとか最高やん♪ しかも、この『JPN TAXI』なる車両は一般ユーザーであっても購入することも可能ときたもんだ!! 例えば将来、自分自身なり家族に~っと、車椅子が必須となった時。各自動車メーカーが通常ラインナップしている車両から福祉車両の回転シート・昇降シート・スロープ・リフター仕様車のいずれかが選択できる車両から買い換えを検討するか。或いは、今現在所有している車両を福祉仕様へカスタマイズする必要があるも。標準で “車椅子のまま乗下車が出来る” 設計になっているこの『JPN TAXI』なる車両であれば、竹中直人の曲なみに心配御無用ですYO(LPG燃料仕様なので、一般ユーザー的にはレギュラーガソリン仕様が欲しいところ。車両価格的に跳ね上がるだろうけど、FCVなんてのもあり?)。今後、現在の愛車にエンジントラブル等、如何ともし難い買い換えに迫られた場合、次の車両選び候補の選択肢に加えてもいいんじゃないないの? ってな具合に、関心を抱き。興味本位で調べてみる。 公式サイトへアクセスするや、真っ先に目に付く大きさで “ご利用の留意事項” なる表記!? なんや、車椅子で利用するのに、なんか制約でもあるんかいっと読んでみる。なんでも、乗車可能な車椅子寸法やらなんやらと、大抵の車椅子なら問題はないんだけど……ちょっち例外もありまっせ~等の規定が連なり。更に『その他』の項目にて、乗降車時の所要時間は “10分程度(状況により異なる)” 時間がかかりますとの一文があるではないか!? おいおい、10分って……“poddi” ならご飯が炊けるやん。虚けな当方には、なして車椅子をそのまま乗降車させるだけで、そんなに時間が必要なのか、さっぱりわからん。こりゃ~取扱説明書なりを確認した方がよさげと、車椅子の乗降車の仕方が記載されている項目を探ろうかと思ったところで。乗務員向けと思われる項目があるではないか。何にそんなに手間暇かかるんだと項目をクリックしてみたところ、車椅子の乗降車説明動画があるんですけどね。その動画の再生時間、なななんと30分!? “ウル得マン” なら計6品の料理が出来る時間ですよ。恐らく、丁寧な解説やらで説明動画の尺が長いだけだろうと、気軽な気持ちで再生してみたところ……あ、ありのまま今起こったことを話すぜ。①まず乗務員は、運転席を降り運転席を最前にスライドさせ、背もたれも最前に倒す。②助手席ドア & リアスライドドアを開け。助手席を一度前にスライドさせた後、最後部までスライドさせリクライニングレバーを上げ、助手席をタンブルさせる。③運転席に付いている料金トレー(設置してある場合)を外す。④後部座席の座面下にあるレバーを使い、座面を跳ね上げる(左右後部座席)。⑤後部座席を跳ね上げた床に、固定用ベルト一式(色分けされている)とスロープNo.1が納められている収納袋があるので、そこから必要な固定用ベルトとスロープNo.1を取り出す。⑥リアハッチを開け、トランクルームの床下収納ボックスより、スロープNo.2を取り出す(乗降車場所が歩道など、高さがある場合、この項目はスキップ可)。⑦スロープを組み立て車体に固定(しっかりと固定されているか。正しく設置できたかをアタッチメント・固定用ベルト等を要確認し、乗務員自らスロープに乗り安全を確認)する。⑧車椅子を車内へ。乗車させた後、反時計回り(車両進行方向へ)で90°回転させ、車椅子の車両中心と跳ね上げた助手席側の後部座席の中央にある “↓” マークと合わせるように車椅子をバックさせ、車椅子の車輪が確実に後部座席と接触しているか確認した後、車椅子のブレーキをかける。⑨スロープを車体から外し、バラしてから固定用ベルトで車椅子を固定。運転席側の後部座席を元に戻す。⑩戻した後部座席の中央座席用のシートベルトを外し、延長シートベルトをセット。その延長シートベルトを車椅子の乗客の協力を得て、シートベルトをする。⑪バラしたスロープをトランクルームへ収納。これで、ようやく発進準備が完了となる。下車時には、①からの⑪へ飛び、内容を逆にした順序でやるんだそうだ。……ぇ、これを車椅子の乗降車時に毎度やるの!? 仮に自家用車だったとしても、家族・親戚を乗せるのですら……面倒だと感じるだろうに。これが乗務員の立場だったら……車椅子の客は勘弁してくれって思わずにはいられないだろう。何でこんな七面倒臭い設計になってんだ? 素直にリアパンパーと連動するテールゲート一体型スロープを採用し、後部座席にスライド機能をもたせ、座面を跳ね上げたらそのまま前席まで前にスライドさせ、車両後方から直にスロープで乗降車をするって設計にしなかったんだ? とか疑問に思うも。どうにも、
公式サイトへアクセスするや、真っ先に目に付く大きさで “ご利用の留意事項” なる表記!? なんや、車椅子で利用するのに、なんか制約でもあるんかいっと読んでみる。なんでも、乗車可能な車椅子寸法やらなんやらと、大抵の車椅子なら問題はないんだけど……ちょっち例外もありまっせ~等の規定が連なり。更に『その他』の項目にて、乗降車時の所要時間は “10分程度(状況により異なる)” 時間がかかりますとの一文があるではないか!? おいおい、10分って……“poddi” ならご飯が炊けるやん。虚けな当方には、なして車椅子をそのまま乗降車させるだけで、そんなに時間が必要なのか、さっぱりわからん。こりゃ~取扱説明書なりを確認した方がよさげと、車椅子の乗降車の仕方が記載されている項目を探ろうかと思ったところで。乗務員向けと思われる項目があるではないか。何にそんなに手間暇かかるんだと項目をクリックしてみたところ、車椅子の乗降車説明動画があるんですけどね。その動画の再生時間、なななんと30分!? “ウル得マン” なら計6品の料理が出来る時間ですよ。恐らく、丁寧な解説やらで説明動画の尺が長いだけだろうと、気軽な気持ちで再生してみたところ……あ、ありのまま今起こったことを話すぜ。①まず乗務員は、運転席を降り運転席を最前にスライドさせ、背もたれも最前に倒す。②助手席ドア & リアスライドドアを開け。助手席を一度前にスライドさせた後、最後部までスライドさせリクライニングレバーを上げ、助手席をタンブルさせる。③運転席に付いている料金トレー(設置してある場合)を外す。④後部座席の座面下にあるレバーを使い、座面を跳ね上げる(左右後部座席)。⑤後部座席を跳ね上げた床に、固定用ベルト一式(色分けされている)とスロープNo.1が納められている収納袋があるので、そこから必要な固定用ベルトとスロープNo.1を取り出す。⑥リアハッチを開け、トランクルームの床下収納ボックスより、スロープNo.2を取り出す(乗降車場所が歩道など、高さがある場合、この項目はスキップ可)。⑦スロープを組み立て車体に固定(しっかりと固定されているか。正しく設置できたかをアタッチメント・固定用ベルト等を要確認し、乗務員自らスロープに乗り安全を確認)する。⑧車椅子を車内へ。乗車させた後、反時計回り(車両進行方向へ)で90°回転させ、車椅子の車両中心と跳ね上げた助手席側の後部座席の中央にある “↓” マークと合わせるように車椅子をバックさせ、車椅子の車輪が確実に後部座席と接触しているか確認した後、車椅子のブレーキをかける。⑨スロープを車体から外し、バラしてから固定用ベルトで車椅子を固定。運転席側の後部座席を元に戻す。⑩戻した後部座席の中央座席用のシートベルトを外し、延長シートベルトをセット。その延長シートベルトを車椅子の乗客の協力を得て、シートベルトをする。⑪バラしたスロープをトランクルームへ収納。これで、ようやく発進準備が完了となる。下車時には、①からの⑪へ飛び、内容を逆にした順序でやるんだそうだ。……ぇ、これを車椅子の乗降車時に毎度やるの!? 仮に自家用車だったとしても、家族・親戚を乗せるのですら……面倒だと感じるだろうに。これが乗務員の立場だったら……車椅子の客は勘弁してくれって思わずにはいられないだろう。何でこんな七面倒臭い設計になってんだ? 素直にリアパンパーと連動するテールゲート一体型スロープを採用し、後部座席にスライド機能をもたせ、座面を跳ね上げたらそのまま前席まで前にスライドさせ、車両後方から直にスロープで乗降車をするって設計にしなかったんだ? とか疑問に思うも。どうにも、 後部座席の後ろには従来のLPGタンクより小型軽量化された新開発のLPGタンクが配置されている関係で、後部座席を動かす事が不可能である故にリアスライドドアからの車体側面からの乗降車という設計になり。更に “コンパクトミニバン” と限られた車内空間で車椅子を90°回転させる & 固定用ベルトや延長シートベルトを装着させる作業空間を確保するには、どうしても前席のシートアレンジなる前準備も必要となり。作業工程 & 所要時間が増えてしまうようだ。まぁ、なんというか……“車椅子のまま乗下車が出来る” と公式サイト的には謳ってはいるも。現実的、かつ誤解を生まないニュアンス的には、“車椅子のまま乗下車することも、出来なくもない” と表現した適切な気もしないでもない。そんな公式サイト的には、乗降車時の所要時間は “10分程度(状況により異なる)” と記載しているも、実際に運行をしているタクシー会社のHPを数社巡ってみると、車椅子での乗降車には “10分~20分程” とか。事前に車椅子であることは伝えてね♥ と、車椅子での乗降車には其相応のお覚悟をして下さい的な一文が記載され。それとなく「悪いことは言わない、福祉用にカスタマイズされた専門の介護タクシー・福祉タクシーを呼んだ方が良いですよ!」と、遠回しに促している気もしないでもない。然しながら、安易に「車椅子の客はNG!!」なんて表明しようものなら、頼もしい団体の方々なりが速攻で突撃してくるだろうし……色々と難しい所ですね。とはいえ、実際に車椅子での移動に使う車両としては到底現実的とは思えなぬ車両設計をするんなら、わざわざ車椅子に対応する必要があったのだろうか? そんな素朴な疑問すら頭によぎってしまう。車椅子に対応するならするで、もっとスロープを室内床下 or 車内に収納され、1アクションで設置固定が可能で、固定用ベルトや延長シートベルトも室内、あるいは後部座席の跳ねたげた座面下に配置されていて、それぞれのベルトを車椅子と接続固定すればいいだけとかね。コスト的には上乗せを余儀なくされるとは思うが、もっとやりようが……あったのではないかと思わずにはいられないのだが。この『JPN TAXI』なる車両の関連記事を読み漁っているや、殊更 “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” なる文言が入っていることに気がつく。UD? トラックかな??? なにやら、聞き慣れないWordが出てきたので、ついでに調べてみるや、なんでも
後部座席の後ろには従来のLPGタンクより小型軽量化された新開発のLPGタンクが配置されている関係で、後部座席を動かす事が不可能である故にリアスライドドアからの車体側面からの乗降車という設計になり。更に “コンパクトミニバン” と限られた車内空間で車椅子を90°回転させる & 固定用ベルトや延長シートベルトを装着させる作業空間を確保するには、どうしても前席のシートアレンジなる前準備も必要となり。作業工程 & 所要時間が増えてしまうようだ。まぁ、なんというか……“車椅子のまま乗下車が出来る” と公式サイト的には謳ってはいるも。現実的、かつ誤解を生まないニュアンス的には、“車椅子のまま乗下車することも、出来なくもない” と表現した適切な気もしないでもない。そんな公式サイト的には、乗降車時の所要時間は “10分程度(状況により異なる)” と記載しているも、実際に運行をしているタクシー会社のHPを数社巡ってみると、車椅子での乗降車には “10分~20分程” とか。事前に車椅子であることは伝えてね♥ と、車椅子での乗降車には其相応のお覚悟をして下さい的な一文が記載され。それとなく「悪いことは言わない、福祉用にカスタマイズされた専門の介護タクシー・福祉タクシーを呼んだ方が良いですよ!」と、遠回しに促している気もしないでもない。然しながら、安易に「車椅子の客はNG!!」なんて表明しようものなら、頼もしい団体の方々なりが速攻で突撃してくるだろうし……色々と難しい所ですね。とはいえ、実際に車椅子での移動に使う車両としては到底現実的とは思えなぬ車両設計をするんなら、わざわざ車椅子に対応する必要があったのだろうか? そんな素朴な疑問すら頭によぎってしまう。車椅子に対応するならするで、もっとスロープを室内床下 or 車内に収納され、1アクションで設置固定が可能で、固定用ベルトや延長シートベルトも室内、あるいは後部座席の跳ねたげた座面下に配置されていて、それぞれのベルトを車椅子と接続固定すればいいだけとかね。コスト的には上乗せを余儀なくされるとは思うが、もっとやりようが……あったのではないかと思わずにはいられないのだが。この『JPN TAXI』なる車両の関連記事を読み漁っているや、殊更 “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” なる文言が入っていることに気がつく。UD? トラックかな??? なにやら、聞き慣れないWordが出てきたので、ついでに調べてみるや、なんでも  04年にバリアフリー化推進要綱んるものが策定され。06年にハードビル法と交通バリアフリー法を統合した “高齢者、障害者などの移動等の円滑化の推進に関する法律” こと、『バリアフリー新法』なるものが施行され。更に国際的な運動競技なる夏の
04年にバリアフリー化推進要綱んるものが策定され。06年にハードビル法と交通バリアフリー法を統合した “高齢者、障害者などの移動等の円滑化の推進に関する法律” こと、『バリアフリー新法』なるものが施行され。更に国際的な運動競技なる夏の7.24 本土決戦 ~対価はいりません、おもてなしですから~……もとい、既得権益者の祭典があるんだから。それまでにバリアフリー・ユニバーサルデザインを普及させまくれ! てな大号令があるんだとかで、“ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” を購入すると 自動車重量税の免除(初回に限る) & 自動車所得税の減税に加え、各都道府県で別途補助金を出しちゃいますYOっと、購入特典を天こ盛りにする優遇措置があるそうな。例えば、都内であれば
自動車重量税の免除(初回に限る) & 自動車所得税の減税に加え、各都道府県で別途補助金を出しちゃいますYOっと、購入特典を天こ盛りにする優遇措置があるそうな。例えば、都内であれば こんな感じなんだそうです。そりゃ~都内の法人タクシーが発売から半年も経たずに3万台の内、約7%相当が新型タクシーこと、『JPN TAXI』なる車両に入り替わる訳ですよ。なんだか、乗客や乗務員の為と言うより、運送業を営む経営側が購入特典目当てに購入しやすいよう
こんな感じなんだそうです。そりゃ~都内の法人タクシーが発売から半年も経たずに3万台の内、約7%相当が新型タクシーこと、『JPN TAXI』なる車両に入り替わる訳ですよ。なんだか、乗客や乗務員の為と言うより、運送業を営む経営側が購入特典目当てに購入しやすいよう 車両設計した企業は、無理くり “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” 認定(UD Lv.1)に適合するギリギリのラインを狙って車両を設計したんじゃないかと……そんなことはこれっぽっちも思いもしない当方ですが。先行して “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” 認定を受け販売をしている『NV200』や『SERENA』も同じくUD Lv.1。ありゃ? ベース車両が “ワゴン” や “ミニバン” と “コンパクトミニバン” がベース車両である『JPN TAXI』なる車両より車両寸法が大きいのに同じ認定Lvなの!? どういうこっちゃと、認定基準についても調べてみる。①乗降口の1カ所はスロープ(別体含む)を設け(スロープは幅 700 mm 以上の耐荷重 200 ㎏)、乗降口の幅 700 mm 以上 高さ 1,300 mm 以上で “円滑” に車椅子使用者が乗降出来ること。②地上高は 350 mm 以下(超える場合は補助ステップ等設置)。③4人以上の乗客が乗車でき、車椅子使用者乗車時、車椅子使用者以外に乗客1名以上が乗客出来るのがUD Lv.1(端折っている項目があるので、詳細は確認してくらはい)らしく。これがUD Lv.2になると、①乗降口の1カ所はスロープ(別体含む)を設け(スロープは幅 700 mm 以上の耐荷重 “250 ㎏” )、乗降口の幅 “800 mm” 以上 高さ “1,350 mm” 以上(※小型自動車は幅 700 mm 以上で可)で “円滑” に車椅子使用者が乗降出来ること。②地上高は “300 mm” 以下(超える場合は補助ステップ等設置)。③4人以上の乗客が乗車でき、車椅子使用者乗車時、車椅子使用者以外に乗客 “2名以上” (※小型自動車は乗客1名以上で可)と認定基準が上がり、項目も増える為。仮にUD Lv.2認定を得られるタクシーを発売するとなるば、ベース車両から大幅にUD Lv.2基準に適合する専用設計にするか。或いは、現行販売している車両をハイルーフ化 & リフターを標準装備にするくらいな水準が求められるので、いくら “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” を標準化しましょう的な流れがあるにしろ、介護タクシー・福祉タクシー等は別にしても、通常のタクシーをUD Lv.2基準にするのはコスト的に現実的ではないだろう(完全自動運転や電気自動車など、車内レイアウトの制限・コストなんかの条件が変わってくれば、UD Lv.2基準の車両設計が容易になる時代も来るかも?)。
車両設計した企業は、無理くり “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” 認定(UD Lv.1)に適合するギリギリのラインを狙って車両を設計したんじゃないかと……そんなことはこれっぽっちも思いもしない当方ですが。先行して “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” 認定を受け販売をしている『NV200』や『SERENA』も同じくUD Lv.1。ありゃ? ベース車両が “ワゴン” や “ミニバン” と “コンパクトミニバン” がベース車両である『JPN TAXI』なる車両より車両寸法が大きいのに同じ認定Lvなの!? どういうこっちゃと、認定基準についても調べてみる。①乗降口の1カ所はスロープ(別体含む)を設け(スロープは幅 700 mm 以上の耐荷重 200 ㎏)、乗降口の幅 700 mm 以上 高さ 1,300 mm 以上で “円滑” に車椅子使用者が乗降出来ること。②地上高は 350 mm 以下(超える場合は補助ステップ等設置)。③4人以上の乗客が乗車でき、車椅子使用者乗車時、車椅子使用者以外に乗客1名以上が乗客出来るのがUD Lv.1(端折っている項目があるので、詳細は確認してくらはい)らしく。これがUD Lv.2になると、①乗降口の1カ所はスロープ(別体含む)を設け(スロープは幅 700 mm 以上の耐荷重 “250 ㎏” )、乗降口の幅 “800 mm” 以上 高さ “1,350 mm” 以上(※小型自動車は幅 700 mm 以上で可)で “円滑” に車椅子使用者が乗降出来ること。②地上高は “300 mm” 以下(超える場合は補助ステップ等設置)。③4人以上の乗客が乗車でき、車椅子使用者乗車時、車椅子使用者以外に乗客 “2名以上” (※小型自動車は乗客1名以上で可)と認定基準が上がり、項目も増える為。仮にUD Lv.2認定を得られるタクシーを発売するとなるば、ベース車両から大幅にUD Lv.2基準に適合する専用設計にするか。或いは、現行販売している車両をハイルーフ化 & リフターを標準装備にするくらいな水準が求められるので、いくら “ユニバーサル・デザイン(UD)タクシー” を標準化しましょう的な流れがあるにしろ、介護タクシー・福祉タクシー等は別にしても、通常のタクシーをUD Lv.2基準にするのはコスト的に現実的ではないだろう(完全自動運転や電気自動車など、車内レイアウトの制限・コストなんかの条件が変わってくれば、UD Lv.2基準の車両設計が容易になる時代も来るかも?)。 まぁ、何にしても。通常ラインナップされている車両が標準で “ユニバーサル・デザイン” 仕様っていうのも、意外と需要が……ある? かも知れない。そんな福祉車両ラインナップ選択肢がかなり限られている三自。
まぁ、何にしても。通常ラインナップされている車両が標準で “ユニバーサル・デザイン” 仕様っていうのも、意外と需要が……ある? かも知れない。そんな福祉車両ラインナップ選択肢がかなり限られている三自。 超大型リコール(隠し)が出た! 出た! 出た(池の水を全部抜くナレーション風)ぁぁぁぁ!! っと、色々としでかし、偉大なる既存メディアからの連日連夜による正義の鉄槌という名の袋叩きなるサブリミナル効果も功を奏し、見事に国内市場におけるブランドイメージの失墜。因みに、企業が国からの業務を代行し、車両組み立て工場にて、資格を持つ検査員による完成車検査をしなければならないのを……つい、うっかりね。無資格者に完成車検査をさせていたり。無いことは確定しているけど、一応ね……盆暗企業や、虚偽の下方補正を加えた燃費データを申告してくる企業みたく、やらかした企業はおらんかね? ってな通達をするも、何ら問題はないとスルーをしていた企業が……実は、燃費データに加え、排出ガスのデータも改ざんしてた!? なんて本当に些細な出来事もあった気もしなくもありませんが。我こそは世論の代弁者と
超大型リコール(隠し)が出た! 出た! 出た(池の水を全部抜くナレーション風)ぁぁぁぁ!! っと、色々としでかし、偉大なる既存メディアからの連日連夜による正義の鉄槌という名の袋叩きなるサブリミナル効果も功を奏し、見事に国内市場におけるブランドイメージの失墜。因みに、企業が国からの業務を代行し、車両組み立て工場にて、資格を持つ検査員による完成車検査をしなければならないのを……つい、うっかりね。無資格者に完成車検査をさせていたり。無いことは確定しているけど、一応ね……盆暗企業や、虚偽の下方補正を加えた燃費データを申告してくる企業みたく、やらかした企業はおらんかね? ってな通達をするも、何ら問題はないとスルーをしていた企業が……実は、燃費データに加え、排出ガスのデータも改ざんしてた!? なんて本当に些細な出来事もあった気もしなくもありませんが。我こそは世論の代弁者と驕り高ぶる……もとい、多くの人……国民を誘導……ゴホンゴホン。知る権利があると、社会的重大な情報を恵んで下さる役割を担う敬愛すべき既存メディアがまるで取り上げようともしない。又は、取り扱ったとしても、さらっと流す程度であることは、多くの人……国民に報じるに値もしない情報であることは、国の借金が1085兆円(17年末時点)!! 人……国民一人当たりに換算すると、858万円の借金を抱えている計算になり。国の財政を健全化させる為には増税(※新聞は人……国民の皆様にニュースや知識を与える貴重や情報源なので、軽減税率が適応予定)しかない! とか、放送法改正で “政治的公正” や “正確な報道” 等を定めた『放送法4条』の撤廃を検討している不届きな政権の暴挙を許してはいけない!! 但し『放送法4条』はあくまで “倫理規範” と解するのが適切なので、法的義務も無ければ、法律違反も無く。放送で表現の自由や報道の自由を、例え時の権力者ですら侵すべからず。仮に放送内容に『放送法4条』的に抵触しているのではないか? なんて指摘され放送内容があったとしても? 放送倫理・番組向上機構があるから、なんの問題ナッシング♪ そんな既得権益を死守する……もとい、情報弱者を親切丁寧に誘導……ゴホンゴホン、人……国民にとって、有益と判断される情報を独断と偏見で取捨選択して下さる親愛なる既存メディアが全く以て問題視すらしていないので、無資格検査や燃費データ・排出ガスのデータが如何にしょうもない事柄であると確信できますよね♥ ※但し戦犯企業は除く。そんな崇拝すべき既存メディアでCMを見ることが多い素晴らしいブランドイメージの良い企業とは違い。国内市場の立て直しをする為に経費やら労力を費やすより、成長著しい海外市場に力を注いだ方が理に適っていると、海外市場に現を抜かしている間に……国内販売網壊滅寸前!? 緊急SOS! 経営危機に陥る国内販販売店を保護せよ!! っと、かなり放置気味だった国内市場なのですが。某フランス企業グループに買収からの傘下に入った事により、彼方から役員なり社員が加わったからか? いくら国内市場が縮小傾向とはいえ、指くわえて車が売れませんでは話にならんと。手探りながらもマーケティング戦略なる新たな試みを始めたようで。従来のCM・販売店での宣伝中心販売戦略とは打って変わり、様々なイベントや広告媒体は元より、自動車メーカーとしては初? となる、インターネットでのライブ配信(1月末までのアクセス数、累計6万5,000件)で宣伝活動をした結果。1月末時点で先行予約受注が3,000台を超え、好調な滑り出しを魅せる……も。宣伝活動を1月下旬~2月上旬に集中し過ぎ、実際に発売を迎える3月頃には、なんか一息ついちゃった感がなくもないという……継続性が今一ないという伝統は未だ健在と言うのはさておき。折角のインターネットでのライブ配信なる試みをしたのなら、どこぞの0ch Café Staとはいかずとも、各週なり各月なりのペースでプロドライバーや開発陣の方なりをゲストに迎え、新車やMC・一部改良の宣伝なり。技術やら拘りの機能のPRとか。昔の車両の開発秘話に海外市場の話に、折角だから海外から来ている技能実習生にインタビューとか……ぇ!? それは実習計画から逸脱しているからNGだって? ごめんねごめんね~。兎に角、心酔すべき既存メディアの情報媒体に頼ることなく、三自が情報を発信する番組でも拵えれば良いのになぁ~なんて思いつつ。 此方の新型車両、 OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)
OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W) ek CUSTOM(DBA-B11W)
ek CUSTOM(DBA-B11W) RVR(DBA-GA3W/GA4W)と発売当初のフロントフェンスより、テコ入れの為に新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” へとプリティーリメイクさせるも。再設計・再生産にコストのかかるボンネットやらフロントヘッドライトはそのまま流用し、フロントバンパー部分を
RVR(DBA-GA3W/GA4W)と発売当初のフロントフェンスより、テコ入れの為に新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” へとプリティーリメイクさせるも。再設計・再生産にコストのかかるボンネットやらフロントヘッドライトはそのまま流用し、フロントバンパー部分を 新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” へフロントフェンスチェンジさせることで、低コストで確かに印象はがらりと変わるものの……
新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” へフロントフェンスチェンジさせることで、低コストで確かに印象はがらりと変わるものの…… どうにもConcept carデザインとの乖離がね……ボリューム感であったり、スマートさにいささか不自然な感じが否めなず。まぁ、量産車にConcept carクラスの加工を求めるのは酷ではあるが、フロントバンパーだけで、よくそれっぽく仕立てているなぁ~と個人的な好みは別として関心したものですが。
どうにもConcept carデザインとの乖離がね……ボリューム感であったり、スマートさにいささか不自然な感じが否めなず。まぁ、量産車にConcept carクラスの加工を求めるのは酷ではあるが、フロントバンパーだけで、よくそれっぽく仕立てているなぁ~と個人的な好みは別として関心したものですが。 国内では初となる、元からのエクステリアデザインが新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” である此方の新型車両。フロントヘッドライトのややつり上がり具合やら、左右のメッキの配置具合と、
国内では初となる、元からのエクステリアデザインが新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” である此方の新型車両。フロントヘッドライトのややつり上がり具合やら、左右のメッキの配置具合と、 量産車でありながらもConcept carを彷彿とさせるフロントフェンスの仕上がり具合はなかなかにグットである。然しながら、対向車線に走行している車両が遠目に此方の新型車両? と思いすれ違ってみるや。15年式以降のOUTLANDERだったり、ポジションランプの光る位置が同じようなところにあるので、DBA-AGL20W / DAA-GYL20W / GYL26W のどれか……下級市民風情には縁の無い車両なんで、見分けのつかない高価格車……なんて事が多々ありますが。
量産車でありながらもConcept carを彷彿とさせるフロントフェンスの仕上がり具合はなかなかにグットである。然しながら、対向車線に走行している車両が遠目に此方の新型車両? と思いすれ違ってみるや。15年式以降のOUTLANDERだったり、ポジションランプの光る位置が同じようなところにあるので、DBA-AGL20W / DAA-GYL20W / GYL26W のどれか……下級市民風情には縁の無い車両なんで、見分けのつかない高価格車……なんて事が多々ありますが。 フロントフェンス全体で認識するのではなく、フロントバンパーの左右部分のフォグランプ箇所がやけに大きいか否かで識別が可能。それにしても、真っ正面から見ていると、やけにゴツい印象があるが、真横から見るとCd値の為なのかな? やけに丸みがある。
フロントフェンス全体で認識するのではなく、フロントバンパーの左右部分のフォグランプ箇所がやけに大きいか否かで識別が可能。それにしても、真っ正面から見ていると、やけにゴツい印象があるが、真横から見るとCd値の為なのかな? やけに丸みがある。 テールランプより伸びるキャラクターラインにより、車両側面の力強さを表しているのは良いとして。なしてフロントドアのドアハンドルはキャラクターライン上に設けているのに、リアドアのドアハンドルはちょっとキャラクターラインより上にずらしてあるのだ? バランスが悪いような……プレス加工なりの何かしらの意味があるんだろう。
テールランプより伸びるキャラクターラインにより、車両側面の力強さを表しているのは良いとして。なしてフロントドアのドアハンドルはキャラクターライン上に設けているのに、リアドアのドアハンドルはちょっとキャラクターラインより上にずらしてあるのだ? バランスが悪いような……プレス加工なりの何かしらの意味があるんだろう。 サイドミラーの根元がやけに極太な気が……多少なんかの障害物に当たっても壊れないようにしてるのかな?
サイドミラーの根元がやけに極太な気が……多少なんかの障害物に当たっても壊れないようにしてるのかな? 試乗車には、ディーラーオプションであるエクステンションパッケージ(フロントコーナーエクステンション・サイドエクステンション・リアコーナーエクステンションの単品合計で税込163,922円がパッケージ価格で税込142,862円)が装着されているのだが、ボディーカラーが有料色の “レッドダイヤモンド” と赤系である所為か、朱色に近い赤い細いラインがあまり目立たない……。試しに、
試乗車には、ディーラーオプションであるエクステンションパッケージ(フロントコーナーエクステンション・サイドエクステンション・リアコーナーエクステンションの単品合計で税込163,922円がパッケージ価格で税込142,862円)が装着されているのだが、ボディーカラーが有料色の “レッドダイヤモンド” と赤系である所為か、朱色に近い赤い細いラインがあまり目立たない……。試しに、 他のボディカラーならどうなるのかと、公式HPにてオプションを組み合わせみたところ。白・黒がワンポイントラインとなって良い感じですね。赤系は同化しすぎて似合う・似合わない以前に、違和感がないといった具合。個人的に驚いたのが、青が意外としっくりくる。また、フロントバンパーガーニッシュはボディーカラーをわざわざ隠してしまうので、付けなくてもいい気が~なんて個人的に思うも。黒のボディーカラーに限り、フロントバンパーガーニッシュの有無でかなり印象が異なるので、同一条件(オプション選択)で合わせようとしたのですが……黒だけはフロントバンパーガーニッシュを選択してます。
他のボディカラーならどうなるのかと、公式HPにてオプションを組み合わせみたところ。白・黒がワンポイントラインとなって良い感じですね。赤系は同化しすぎて似合う・似合わない以前に、違和感がないといった具合。個人的に驚いたのが、青が意外としっくりくる。また、フロントバンパーガーニッシュはボディーカラーをわざわざ隠してしまうので、付けなくてもいい気が~なんて個人的に思うも。黒のボディーカラーに限り、フロントバンパーガーニッシュの有無でかなり印象が異なるので、同一条件(オプション選択)で合わせようとしたのですが……黒だけはフロントバンパーガーニッシュを選択してます。 インターネットでのライブ配信動画にて、多くの開発担当の方々がオススメしたアングル。
インターネットでのライブ配信動画にて、多くの開発担当の方々がオススメしたアングル。 この角度で見ると、どうにもブレーキランプからのキャラクターラインの溝の入れ方がDAA-GP5 / GP6こと、「さあ、クルマで世界を驚かそう。」と独自開発した変速機構こと、“デュアル・クラッチ・トランスミッション” を搭載。満を持して新発売したところ、あまりの完成度に購入したオーナーが度肝抜かす程だったそうで、次々に賛美の嵐が巻き起こったそうな。その功績を称えるべく、運転席側のドアトリガーの下には、燦々と輝く数々のステッカーが貼られているとか……いないとか。そんな恐れ多い素晴らしい車両っぽく見えなくもないが……DBA-B11Wの “トリプルアローズライン” もブレーキランプからキャラクターラインを入れているので、その系譜って解釈も出来なくもないが……それを考慮し始めたら、DBA-E12の “スカッシュライン” を彷彿とするようなキャラクターラインに見えなくも……もしや、OEM供給する前提で車両デザインしたんじゃないかと疑ってしまう当方はさておき。フロントのボリューム感に、サイドのごつい感じとは一変し、リアバンパーを中心として
この角度で見ると、どうにもブレーキランプからのキャラクターラインの溝の入れ方がDAA-GP5 / GP6こと、「さあ、クルマで世界を驚かそう。」と独自開発した変速機構こと、“デュアル・クラッチ・トランスミッション” を搭載。満を持して新発売したところ、あまりの完成度に購入したオーナーが度肝抜かす程だったそうで、次々に賛美の嵐が巻き起こったそうな。その功績を称えるべく、運転席側のドアトリガーの下には、燦々と輝く数々のステッカーが貼られているとか……いないとか。そんな恐れ多い素晴らしい車両っぽく見えなくもないが……DBA-B11Wの “トリプルアローズライン” もブレーキランプからキャラクターラインを入れているので、その系譜って解釈も出来なくもないが……それを考慮し始めたら、DBA-E12の “スカッシュライン” を彷彿とするようなキャラクターラインに見えなくも……もしや、OEM供給する前提で車両デザインしたんじゃないかと疑ってしまう当方はさておき。フロントのボリューム感に、サイドのごつい感じとは一変し、リアバンパーを中心として 丸みを持たせた印象のあるエクステリアデザインになっている。なんたが、見る角度により大分と印象が異なるのはどうなんですかね~。自車が後続車として、この車両を見るに、きっとフロントフェンスも丸みを持ったデザインか、かわいい系のフロントフェンスを想像してしまわくもないが……。それにしても、リアバンパー中央下のリアフォグランプがあってもおかしくないデザインなのに、海外仕様のみに設定されているリアフォグランプはバックランプの片方が変更するという設定なので、何の為のリアバンパーデザインなのか……不自然だ。
丸みを持たせた印象のあるエクステリアデザインになっている。なんたが、見る角度により大分と印象が異なるのはどうなんですかね~。自車が後続車として、この車両を見るに、きっとフロントフェンスも丸みを持ったデザインか、かわいい系のフロントフェンスを想像してしまわくもないが……。それにしても、リアバンパー中央下のリアフォグランプがあってもおかしくないデザインなのに、海外仕様のみに設定されているリアフォグランプはバックランプの片方が変更するという設定なので、何の為のリアバンパーデザインなのか……不自然だ。 リアガラスには、4WD車両である “スーパーオールホイールコンチョロォォル(発音の仕方が重要!)” ステッカーが貼られている。
リアガラスには、4WD車両である “スーパーオールホイールコンチョロォォル(発音の仕方が重要!)” ステッカーが貼られている。 フロントに関しては、フロントバンパーガーニッシュはが不必要(但し、黒のボディーカラーは除く)と個人的には思うも、リアについてはなにかしらのオプション選択をしていないと
フロントに関しては、フロントバンパーガーニッシュはが不必要(但し、黒のボディーカラーは除く)と個人的には思うも、リアについてはなにかしらのオプション選択をしていないと リアパンパーが寂しい感じなので、リアバンパーガーニッシュなりテールゲートメッキガーニッシュを装着させる事で、大分印象が華やかになる。因みに、メッキドアハンドルカバーを装着するだけでも随分と車両の印象も良くなるので、メッキパーツをワンポイントアクセント的な具合に配置していくのもいいかと。それにしても、オプションパーツの種類があまりにも乏しくはないだろうか? 個人的には “マッドフラップ” “アンダーガード” “フードデフレクター” があっても……とか思うも、さすがにサンシェードやボディカバーすらないというのは、オプションを揃えるだけの経費が……将又、売れないからそもそも用意もしなかったのか? それはさておき、ぱっとエクステリアを一回りした感じ、
リアパンパーが寂しい感じなので、リアバンパーガーニッシュなりテールゲートメッキガーニッシュを装着させる事で、大分印象が華やかになる。因みに、メッキドアハンドルカバーを装着するだけでも随分と車両の印象も良くなるので、メッキパーツをワンポイントアクセント的な具合に配置していくのもいいかと。それにしても、オプションパーツの種類があまりにも乏しくはないだろうか? 個人的には “マッドフラップ” “アンダーガード” “フードデフレクター” があっても……とか思うも、さすがにサンシェードやボディカバーすらないというのは、オプションを揃えるだけの経費が……将又、売れないからそもそも用意もしなかったのか? それはさておき、ぱっとエクステリアを一回りした感じ、 Concept carでは、かなりの独創的で立体感のあるデザインだったのに。量産化をするにあたり、多少の簡略化は致し方ないにしても。フロントバンパーのサイドウィンカーとフォグランプが一体化したデザインやら、リアウィンドからリアバンパーのデザインが、どうにも
Concept carでは、かなりの独創的で立体感のあるデザインだったのに。量産化をするにあたり、多少の簡略化は致し方ないにしても。フロントバンパーのサイドウィンカーとフォグランプが一体化したデザインやら、リアウィンドからリアバンパーのデザインが、どうにも DAA-ZVW30 前期モデルを彷彿とさせるデザインになっている様に……感じるのは気のせいですかね? まぁ、リアランプから下の丸みのある感じは
DAA-ZVW30 前期モデルを彷彿とさせるデザインになっている様に……感じるのは気のせいですかね? まぁ、リアランプから下の丸みのある感じは E-BHAに見えなくも無いが……うまい具合に三自の車両っぽくはまとめたのだろう。開発陣としては、Concept car路線のエクステリアデザインで量産車を目指すも、当然コストのかかるプレス加工や造形は断念せざる得ず。簡略化したデザインでまとめるにはどうしようかと四苦八苦していたところに、経営側から「売れる車を開発しろ」とのお達しがあったのか? は定かではないが、開発当時に “売れている車” のエクステリアデザインを盛り込んだところ、うまい具合にGOサインが降りた……なんてことがあったんかな? なんにしても。
E-BHAに見えなくも無いが……うまい具合に三自の車両っぽくはまとめたのだろう。開発陣としては、Concept car路線のエクステリアデザインで量産車を目指すも、当然コストのかかるプレス加工や造形は断念せざる得ず。簡略化したデザインでまとめるにはどうしようかと四苦八苦していたところに、経営側から「売れる車を開発しろ」とのお達しがあったのか? は定かではないが、開発当時に “売れている車” のエクステリアデザインを盛り込んだところ、うまい具合にGOサインが降りた……なんてことがあったんかな? なんにしても。 リアにもフロントやサイドのボリューム感、ゴツい感じを出すには、テールランプをもうちょい高い位置に設定し、リアガラスの寝かせ方を緩やかにした上で、リア(荷室空間)を伸ばす車体寸法にできれば、大分Concept carに近い量産車になったんだろうが。そんなことをしてしまったら車両寸法的にOUTLANDERとかぶってしまう……と、車両寸法的な制限でリアのボリューム感、ゴツさが表現しきれなかったのだろう。そんな個人的な解釈はさておき、新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” にDAA-ZVW30 前期モデルを彷彿とさせるデザインを盛り込んだ(?)事により、
リアにもフロントやサイドのボリューム感、ゴツい感じを出すには、テールランプをもうちょい高い位置に設定し、リアガラスの寝かせ方を緩やかにした上で、リア(荷室空間)を伸ばす車体寸法にできれば、大分Concept carに近い量産車になったんだろうが。そんなことをしてしまったら車両寸法的にOUTLANDERとかぶってしまう……と、車両寸法的な制限でリアのボリューム感、ゴツさが表現しきれなかったのだろう。そんな個人的な解釈はさておき、新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” にDAA-ZVW30 前期モデルを彷彿とさせるデザインを盛り込んだ(?)事により、 他社で採用しているフロントグリルこと “スピンドルグリル” と似たり寄ったりで、差別化が今一出来てないなぁ~なんて思っていた新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” が、
他社で採用しているフロントグリルこと “スピンドルグリル” と似たり寄ったりで、差別化が今一出来てないなぁ~なんて思っていた新デザインコンセプトである “ダイナミックシールド” が、 独特のフォルムへと転化・発展出来たので、デザインの進化過程としては良かったんだろう。ただ、
独特のフォルムへと転化・発展出来たので、デザインの進化過程としては良かったんだろう。ただ、 某所にて、海外のみで販売されている最新のデザインで量産化された実車を拝見している当方としては、今更デザインの進化過程の車両デザインが “新型車” として見せられてもね。発売もしていない段階で、フロントフェンスの大幅MCが必要なのでは……なんて思っていたり。まぁ、開発のスケジュールやらなんやらと、色々と事情があるんでしょうし。デザインに関する好き好きは兎も角として、この新型車両。クーペスタイルのコンパクトSUVとか、OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)やRVRの中間ですよぉ~と車両のデザインやら、車両サイズに注目が行きがちかと思うが。注目すべきは、
某所にて、海外のみで販売されている最新のデザインで量産化された実車を拝見している当方としては、今更デザインの進化過程の車両デザインが “新型車” として見せられてもね。発売もしていない段階で、フロントフェンスの大幅MCが必要なのでは……なんて思っていたり。まぁ、開発のスケジュールやらなんやらと、色々と事情があるんでしょうし。デザインに関する好き好きは兎も角として、この新型車両。クーペスタイルのコンパクトSUVとか、OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)やRVRの中間ですよぉ~と車両のデザインやら、車両サイズに注目が行きがちかと思うが。注目すべきは、 13年よりアジアクロスカントリーラリーへほぼ市販車状態(ロールバー等の安全装備や、足回りの強化はしている)のOUTLANDER PHEV で参戦するも。当然他の参加車両の様にレーシング用にチューンナップ改造された車両ではないため、嘗て “たま電気自動車” こと、“プリンス自動車工業” が国内大規模レースを開催するに当たり。各社市販車状態で競いましょうねぇ~なんてゆるい規定があったので、馬鹿正直にほぼ市販車状態で出場してみた所……他社は当然の如くバッチリチューンナップ改造し、爆走する中。周囲の参加車両から取り残されて走る散々たる結果に終わり。翌月からの自動車販売台数に大いに響いた……なんてことみたく。まぁ、コンマ1秒と争うレースの舞台ではお話にならない走りっぷりにアジアクロスカントリーの参戦中にも拘わらず、未だ未知数であったPHEVシステム(量産車ではかなりの安全マージンを設けて出力設定などされている)をいじり倒し。翌年のアジアクロスカントリーでは、更に限界への挑戦とPHEVシステムを調整ししまくった所。完走した頃にはPHEVシステムが逝ってしまった……なんて話もあったりもしますが。そんなPHEVシステムやら、4WD制御を突き詰めれば突き詰める程に、その駆動力を受け止めるだけのボディ剛性が足りない。本来であればPAJEROで採用している “ラダーフレーム ビルトイン モノコックボディ” であれば……なんて思ってしまうも、ベース車両がモノコック構造である以上如何ともしがたく。どうにか、ベース車両に大がかりな手を加えることなく、コスト・重量増を拵えつつボディ剛性を飛躍的に上げる手立てはないものかと……模索した所。
13年よりアジアクロスカントリーラリーへほぼ市販車状態(ロールバー等の安全装備や、足回りの強化はしている)のOUTLANDER PHEV で参戦するも。当然他の参加車両の様にレーシング用にチューンナップ改造された車両ではないため、嘗て “たま電気自動車” こと、“プリンス自動車工業” が国内大規模レースを開催するに当たり。各社市販車状態で競いましょうねぇ~なんてゆるい規定があったので、馬鹿正直にほぼ市販車状態で出場してみた所……他社は当然の如くバッチリチューンナップ改造し、爆走する中。周囲の参加車両から取り残されて走る散々たる結果に終わり。翌月からの自動車販売台数に大いに響いた……なんてことみたく。まぁ、コンマ1秒と争うレースの舞台ではお話にならない走りっぷりにアジアクロスカントリーの参戦中にも拘わらず、未だ未知数であったPHEVシステム(量産車ではかなりの安全マージンを設けて出力設定などされている)をいじり倒し。翌年のアジアクロスカントリーでは、更に限界への挑戦とPHEVシステムを調整ししまくった所。完走した頃にはPHEVシステムが逝ってしまった……なんて話もあったりもしますが。そんなPHEVシステムやら、4WD制御を突き詰めれば突き詰める程に、その駆動力を受け止めるだけのボディ剛性が足りない。本来であればPAJEROで採用している “ラダーフレーム ビルトイン モノコックボディ” であれば……なんて思ってしまうも、ベース車両がモノコック構造である以上如何ともしがたく。どうにか、ベース車両に大がかりな手を加えることなく、コスト・重量増を拵えつつボディ剛性を飛躍的に上げる手立てはないものかと……模索した所。 JFEスチール(株)の『JFEトポロジー最適化技術』を採用することで、最小の粘着剤使用量で最大限にボディ剛性を向上させる事に成功! まぁ、三自は国内企業の中ではかなり早い段階である90年代に一部車種で構造用接着剤を採用した車両があったそうですが……どうにも構造用接着剤の塗りむらやら、安定した生産管理が難しいことからライン工程に組み入れるのが困難だったそうで。他の量産車種へ拡大採用されること無く終息(06年 PAJERO V80型から採用されている)してしまったんだとか。因みに、他の国内企業では、数年前より構造用接着剤を採用した上で、スポット溶接を増やしたりレーザー加工的なボディ剛性⤴に力を入れているので、今更構造用接着剤? 的な出遅れ感じもあるっちゃ~あるのですが。このアジアクロスカントリーラリーへ出場した成果として、量産車である
JFEスチール(株)の『JFEトポロジー最適化技術』を採用することで、最小の粘着剤使用量で最大限にボディ剛性を向上させる事に成功! まぁ、三自は国内企業の中ではかなり早い段階である90年代に一部車種で構造用接着剤を採用した車両があったそうですが……どうにも構造用接着剤の塗りむらやら、安定した生産管理が難しいことからライン工程に組み入れるのが困難だったそうで。他の量産車種へ拡大採用されること無く終息(06年 PAJERO V80型から採用されている)してしまったんだとか。因みに、他の国内企業では、数年前より構造用接着剤を採用した上で、スポット溶接を増やしたりレーザー加工的なボディ剛性⤴に力を入れているので、今更構造用接着剤? 的な出遅れ感じもあるっちゃ~あるのですが。このアジアクロスカントリーラリーへ出場した成果として、量産車である OUTLANDER PHEV(S-Edition限定)に構造用接着剤を試験的(?) に採用されたのを皮切りに。それ以降に発売された新型車両である “Xpander” から構造用接着剤を本格導入。勿論、この新型車両にも採用され、来年辺りに発売? されると言われる新型の “DELICA D:5” でも、恐らく国内専用モデルから世界展開モデルへと手直し & 構造用接着剤による更なるボディ剛性⤴がされていると推測され、この新型車両を開発していた時期から推察するに。言わばアジアクロスカントリーラリーのフィードバック車両と捉えるのが適切なのではないかと……勝手に思っていたり。ラリーへなり、レースという過酷な環境において得られたデータを元に車両開発へ反映~とか、ストーリーがあるんですYO的なRPの仕方も良いと思うんだけどなぁ~モゴモゴ。リアハッチを開けると、
OUTLANDER PHEV(S-Edition限定)に構造用接着剤を試験的(?) に採用されたのを皮切りに。それ以降に発売された新型車両である “Xpander” から構造用接着剤を本格導入。勿論、この新型車両にも採用され、来年辺りに発売? されると言われる新型の “DELICA D:5” でも、恐らく国内専用モデルから世界展開モデルへと手直し & 構造用接着剤による更なるボディ剛性⤴がされていると推測され、この新型車両を開発していた時期から推察するに。言わばアジアクロスカントリーラリーのフィードバック車両と捉えるのが適切なのではないかと……勝手に思っていたり。ラリーへなり、レースという過酷な環境において得られたデータを元に車両開発へ反映~とか、ストーリーがあるんですYO的なRPの仕方も良いと思うんだけどなぁ~モゴモゴ。リアハッチを開けると、 クーペスタイルな割には、それなりな荷室空間がある。
クーペスタイルな割には、それなりな荷室空間がある。 インターネットでのライブ配信動画では、この状態でもゴルフバッグは3つ積むことが出来るそうな。
インターネットでのライブ配信動画では、この状態でもゴルフバッグは3つ積むことが出来るそうな。 荷室の床下にはパンクタイヤ対応修理キットが備え付けられており。スペアタイヤ(応急用)はメーカーオプション(税込10,800円)にて、搭載することも可能。その場合、ラゲッジアンダーボックス容量減に車両重量も微増するので、メーカーとしては省スペース・軽量で済むはパンクタイヤ対応修理キットにしたのだろう。
荷室の床下にはパンクタイヤ対応修理キットが備え付けられており。スペアタイヤ(応急用)はメーカーオプション(税込10,800円)にて、搭載することも可能。その場合、ラゲッジアンダーボックス容量減に車両重量も微増するので、メーカーとしては省スペース・軽量で済むはパンクタイヤ対応修理キットにしたのだろう。 後部座席を倒し、
後部座席を倒し、 最大積載量シートアレンジをするも、
最大積載量シートアレンジをするも、 座面の関係で水平にはならない。
座面の関係で水平にはならない。 前後ドアの開口角度が、RVRと比べ、前がやや角度が狭まり。後ろは広がっているので、コンパクトSUVであっても、後部座席の使用頻度も高いと想定して設計してあるのかな?
前後ドアの開口角度が、RVRと比べ、前がやや角度が狭まり。後ろは広がっているので、コンパクトSUVであっても、後部座席の使用頻度も高いと想定して設計してあるのかな?
 ドア内側部分の手に触れるエリアに関しては、なかなかに触り心地よく配慮されている。また、ドアと車体接合部分が従来の車両とは比べものにならない程にゴツく、ガッチリとしてある。ただ、
ドア内側部分の手に触れるエリアに関しては、なかなかに触り心地よく配慮されている。また、ドアと車体接合部分が従来の車両とは比べものにならない程にゴツく、ガッチリとしてある。ただ、
 リアドアの肘掛け部分に関してはクッション素材が入っておらず。めっさ固いです。因みに、この試乗車にはディーラーオプションのドアスイッチパネル(税込15,811円)とピアノブラックパネルが装着されていますが。通常はカーボン調のドアスイッチパネルになります。
リアドアの肘掛け部分に関してはクッション素材が入っておらず。めっさ固いです。因みに、この試乗車にはディーラーオプションのドアスイッチパネル(税込15,811円)とピアノブラックパネルが装着されていますが。通常はカーボン調のドアスイッチパネルになります。 更に、ディーラーオプションのLEDイルミネーション付スカッフプレート(税込31,622円)が装着されており、前席のドアを開けると白色のMITSUBISHI MOTORS ロゴが光るんですYO! ただ、配線がある関係で、車両を傷つけない為のスカッフプレートなのに、このMITSUBISHI MOTORS ロゴのスカッフプレートには足を乗っけるのはNGなんだそうな。
更に、ディーラーオプションのLEDイルミネーション付スカッフプレート(税込31,622円)が装着されており、前席のドアを開けると白色のMITSUBISHI MOTORS ロゴが光るんですYO! ただ、配線がある関係で、車両を傷つけない為のスカッフプレートなのに、このMITSUBISHI MOTORS ロゴのスカッフプレートには足を乗っけるのはNGなんだそうな。 座席に関しては、非メーカーオプションなので、通常のファブリックタイプになります。さわり心地はざらざら感があり。座った印象としては少しばかし滑る印象は否めないが、シートに体を預けてしまえば、シート自体の適度な柔らかさとサイドのサポート部分の反発力のある硬さが良い感じに体をホールドし、体の収まり具合は悪くない。そんな前席とは対称的に、
座席に関しては、非メーカーオプションなので、通常のファブリックタイプになります。さわり心地はざらざら感があり。座った印象としては少しばかし滑る印象は否めないが、シートに体を預けてしまえば、シート自体の適度な柔らかさとサイドのサポート部分の反発力のある硬さが良い感じに体をホールドし、体の収まり具合は悪くない。そんな前席とは対称的に、 後部座席のシートクッションこと、座面部分に関してはそれなりの柔らかさがあり。それ程気にはならないのだが……シートバックこと、背もたれ部分が固く。特に腰から上の背中の固さが圧迫感に感じ、サイドの出っ張り部分が小さいのに、やけに反発力の強い素材であるので、座った印象としては “ek SPACE CUSTOM” とどっこいどっこい? と、長距離移動に後部座席は厳しいんじゃないかと。せめて、シートバックこと、背もたれ箇所がもう少し柔らかく、背中に感じる圧迫感が緩和されれば座った印象も大分変わってくると思われ。また、リクライニングでシートを一番後ろまで倒した位置に調整すれば、体の姿勢的にはそこそこ楽にはなるので、コンパクトカーとしては快適な方かな? 欲を言えば、もう1~2段階後ろに倒せれば……モゴモゴ。個人的に驚いたのが、
後部座席のシートクッションこと、座面部分に関してはそれなりの柔らかさがあり。それ程気にはならないのだが……シートバックこと、背もたれ部分が固く。特に腰から上の背中の固さが圧迫感に感じ、サイドの出っ張り部分が小さいのに、やけに反発力の強い素材であるので、座った印象としては “ek SPACE CUSTOM” とどっこいどっこい? と、長距離移動に後部座席は厳しいんじゃないかと。せめて、シートバックこと、背もたれ箇所がもう少し柔らかく、背中に感じる圧迫感が緩和されれば座った印象も大分変わってくると思われ。また、リクライニングでシートを一番後ろまで倒した位置に調整すれば、体の姿勢的にはそこそこ楽にはなるので、コンパクトカーとしては快適な方かな? 欲を言えば、もう1~2段階後ろに倒せれば……モゴモゴ。個人的に驚いたのが、 シートベルトバックルが座面に沈め込めるようになっている……だと!? 三自車で、こんな気を遣った配慮があるとか……ガクブル。
シートベルトバックルが座面に沈め込めるようになっている……だと!? 三自車で、こんな気を遣った配慮があるとか……ガクブル。 センターコンソールボックス後方……後部座席側からシガーソケットが使えるように配置されているのだが……これは車内空気清浄機用にでも使ってくれって事なんですかね? コンセントとか、USBポートの方が汎用性があっていい気も……急速充電対応 2USBシガーソケットあたりを差し込んでおくのが無難そうだ。そして、コンパクトSUVでは異例の
センターコンソールボックス後方……後部座席側からシガーソケットが使えるように配置されているのだが……これは車内空気清浄機用にでも使ってくれって事なんですかね? コンセントとか、USBポートの方が汎用性があっていい気も……急速充電対応 2USBシガーソケットあたりを差し込んでおくのが無難そうだ。そして、コンパクトSUVでは異例の 左右独立 200 mm のシートスライド機構と、前後に後部座席を動かせることで、後部座席を倒すことなく、荷室空間を広げる事が出来。ゴルフバッグが3つから4つへ乗せられる量が増えるんだとか。ただ、
左右独立 200 mm のシートスライド機構と、前後に後部座席を動かせることで、後部座席を倒すことなく、荷室空間を広げる事が出来。ゴルフバッグが3つから4つへ乗せられる量が増えるんだとか。ただ、 後部座席を前へスライドさせてしまうと、ラゲッジアンダーボックスとの間に隙間が発生してしまう。ゴルフバッグなり段ボール等、大きな物体としての荷物であれば問題ないが。例えば 500 ml ペットボトルやら、折り畳み傘なんかがこの隙間に落ちてしまったとしたら? 回収するのにえらい面倒くさい上に、潰れたら厄介なモノが落ちているのに気付かず後部座席を後ろへスライドさせてしまったら……とか思うと、スライド機構は極力使わない方がいい……気もしなくもない。
後部座席を前へスライドさせてしまうと、ラゲッジアンダーボックスとの間に隙間が発生してしまう。ゴルフバッグなり段ボール等、大きな物体としての荷物であれば問題ないが。例えば 500 ml ペットボトルやら、折り畳み傘なんかがこの隙間に落ちてしまったとしたら? 回収するのにえらい面倒くさい上に、潰れたら厄介なモノが落ちているのに気付かず後部座席を後ろへスライドさせてしまったら……とか思うと、スライド機構は極力使わない方がいい……気もしなくもない。 インストルメントパネルは、手触りが良いとか。
インストルメントパネルは、手触りが良いとか。 コストがかかっていそうな素材をそれ程使用している訳ではないのだが、ボリューム感のあるデザイン性が功を奏し、なかなかの豪華な印象を受ける演出となっている。
コストがかかっていそうな素材をそれ程使用している訳ではないのだが、ボリューム感のあるデザイン性が功を奏し、なかなかの豪華な印象を受ける演出となっている。 大用量のフロアコンソールボックスには、サングラスホルダーが設けられており。3D眼鏡を車内に常備し、思い立った時にそのまま映画館へ~♪ って使い方を想定しているのかな?
大用量のフロアコンソールボックスには、サングラスホルダーが設けられており。3D眼鏡を車内に常備し、思い立った時にそのまま映画館へ~♪ って使い方を想定しているのかな? カーナビゲーションシステムは、7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS](Gなら税込351,000円。G Plus Packageでは税込216,000円で、G Plus Package限定で+税込102,600円上乗せするとRockford Fosgate プレミアムサウンドシステムとなる)が装着されているので、
カーナビゲーションシステムは、7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS](Gなら税込351,000円。G Plus Packageでは税込216,000円で、G Plus Package限定で+税込102,600円上乗せするとRockford Fosgate プレミアムサウンドシステムとなる)が装着されているので、 左右独立温度コントロール式フルオートエアコン(クリーンエアフィルター付)の下にあるUSBポートが1となっている。因みに、G Plus Packageの標準装備であるスマートフォン連携ディスプレイオーディオ[SDA](+税込102,600円上乗せでRockford Fosgate プレミアムサウンドシステム)では、
左右独立温度コントロール式フルオートエアコン(クリーンエアフィルター付)の下にあるUSBポートが1となっている。因みに、G Plus Packageの標準装備であるスマートフォン連携ディスプレイオーディオ[SDA](+税込102,600円上乗せでRockford Fosgate プレミアムサウンドシステム)では、 S-AWCドライブモードセレクター(プッシュボタン)の下にタッチパッドコントローラーが配置される為、電動パーキングブレーキ/ブレーキオートホールドスイッチがドリンクホルダーの真横へ移動される。
S-AWCドライブモードセレクター(プッシュボタン)の下にタッチパッドコントローラーが配置される為、電動パーキングブレーキ/ブレーキオートホールドスイッチがドリンクホルダーの真横へ移動される。 ステアリングはボタンの数は増えてはいるが、基本的にekシリーズにも採用されている物と同じ。
ステアリングはボタンの数は増えてはいるが、基本的にekシリーズにも採用されている物と同じ。 ステアリング横のスイッチ類は……まぁ、一杯。
ステアリング横のスイッチ類は……まぁ、一杯。 ディーラーオプションなりで、アルミペダルがあっても……いい気もするが。そこら辺は今後企画されるであろう特別仕様車にでも装着されるのかな?
ディーラーオプションなりで、アルミペダルがあっても……いい気もするが。そこら辺は今後企画されるであろう特別仕様車にでも装着されるのかな? 運転席からの視界は、サイドミラーをAピラーの付け根から独立させたことにより、
運転席からの視界は、サイドミラーをAピラーの付け根から独立させたことにより、 死角エリアが減り。Aピラーのプラスチックパーツ自体も心なしかスリルな形状をしており、サイドミラー自体も大きいので、RVRやOUTLANDER系と比べて視認性は良さそうだ。
死角エリアが減り。Aピラーのプラスチックパーツ自体も心なしかスリルな形状をしており、サイドミラー自体も大きいので、RVRやOUTLANDER系と比べて視認性は良さそうだ。  エンジンルームを開くと、
エンジンルームを開くと、 これ見よがしに存在感のある3点留めのストラットタワーバー。LANCER Evolution Ⅹなんかのハイパフォーマンスモデルなり、SPORTSモデルでは標準装備で備え付けられる事が多いが。基本的にコスト増となるボディ剛性補強用パーツは大衆車では無駄と省かれてしまうところを、此方の新型車では全グレード標準装備とガッチリ装着された上に、バルクヘッド側にもカウルトップリンフォースを入れているとかで。大衆向け量産車としては、あるまじきボディ剛性補強用パーツへの熱の入れよう。
これ見よがしに存在感のある3点留めのストラットタワーバー。LANCER Evolution Ⅹなんかのハイパフォーマンスモデルなり、SPORTSモデルでは標準装備で備え付けられる事が多いが。基本的にコスト増となるボディ剛性補強用パーツは大衆車では無駄と省かれてしまうところを、此方の新型車では全グレード標準装備とガッチリ装着された上に、バルクヘッド側にもカウルトップリンフォースを入れているとかで。大衆向け量産車としては、あるまじきボディ剛性補強用パーツへの熱の入れよう。 タイヤはTOYO PROXES R44 225/55R18 98H。
タイヤはTOYO PROXES R44 225/55R18 98H。
試乗環境 → 3人乗車。AUTOエアコン → 25.5 ℃ 設定。S-AWCドライブモード → AUTO。ECOモード → OFF。平日の日中、国道10 ㎞ + α。晴れ。外気温は11℃。
時を遡ること、今年の3月の日こと(突然の回想シーン!?)。18年式のekシリーズで遊ばせて……試乗させて頂いた後、営業の方と雑談をしていたところ「新型車の試乗第1号になって貰おうかと思っていたんですけど~」と歯切れ悪く話し始める営業の方。なんでも、久方ぶりの新型車と注目度(三自車としては)がある上に、乗り換えを検討している馴染みのオーナーさんより試乗予約が殺到しているんだとかで。仮に試乗しにお越し頂いても、数時間待ちになってしまう可能性があるんだそうな。そんな訳で、試乗を希望するのであれば、事前に日程調整を~っと、新型車で遊ぶ……もとい、試乗するのは難しいとの旨を伝えられたので。購入検討者から冷やかしの試乗希望客まで、一通り試乗需要が終わる時期までは試乗する気は無いんで、全然問題ナッシング♪ なんて返答したところ。どうにも営業の方的には当方に試乗をさせ、感想を他の客へのセールスに生かそうとしていた? 将又、只でさえ忙しくなる決算期。接客という大義名分のサボり……休憩を画策していたかは不明だが、やけに「平日なら大丈夫ですから、平日なら」っと、試乗を勧められたんですけどね。まぁ、世間では “試乗最速レポート” なんて具合に、動画投稿なりアフリエイトで報酬を得る為、頑張っている方々も居るだろうし。新型車関係のネタはその方々にでもお任せしとけばいいやっと、大型連休が過ぎた後にでもと思っていたんですけどね。とある知人より「新型車が気にはなるんだけど……新型車の名前がわからん」なんて話を振られたので、新年度を迎えるちょいと前の平日、とある知人を引き連れ販売店を訪れる事になる。
画面切り替わりましての、そんな経緯で出迎えた営業の方より「運転するんですか? 運転するんですよね?」なんて詰め寄られる当方であったが「営業はこっちの方にしてくらはい」と簡潔に事情を話し、知人へバトンタッチ。知人を新型車の運転席へ招き営業トークが始まったところで、営業の邪魔をしたら悪いと新型車の前方(正確には、右側面フロントフェンダー付近)をうろつきつつ、販売店へ商談? か冷やかしと思しき駐車スペースに駐まるDBA-GSRの前期モデルや、16年にFMCされたばかりのLDA-KF2Pを遠目に眺めていたところ。突然、何処からエンジン始動音!? 音の発信源を探るべく、周囲グルッと見渡した所……どうやら、営業の方がプッシュスタート式のエンジンスイッチの説明をしているようで、この新型車だったようだ。それにしても、あまりのエンジン始動音の小ささ。更には、コールドスタートって程にエンジンが冷え切った状態ではなかったにしろ。エンジン始動直後のアイドリング音ですらエンジン音が小さく、自身が突発性難聴になったんじゃないか? 疑ってしまう程だ。体感的に言い表すのであれば、エンジン始動音がスーパーマーケットなどの平面駐車場に車両がずらりと並ぶ駐車スペースの向かい駐車スペース側に駐車する数台も離れた車両がエンジン始動したくらいで。エンジン始動直後のアイドリング音ですら、駐車スペース2台程跨いだ車両が既にエンジンが温まり、低回転でアイドリングをしているLvだ。偶然とは言え、エンジンの真横に立っているのにこの静粛性は凄すぎ! こりゃ~、ボンネット開けて、エンジンカバーの上に500円玉を縦に立てても倒せません的な……事も出来ちゃうんじゃないの? なんて思わずにはいられない程である。それから数分と経たぬうちにエンジンも温まったようで、エンジンの真横にいるにもかかわらず、微かにエンジン音が耳に届く程度である。こりゃ~早朝や深夜であっても、ご近所に気を遣うことなくエンジン始動が気兼ねなく出来そうだ。試乗しに販売店を訪れた際には、自身でエンジンスイッチボタンを押したい……と思われるでしょうが、敢えて車両の外……エンジンの間近でエンジン始動音を聞くことを推奨ですよ! そんな1人で驚いている当方に気が付くこともなく、営業の方よりヘッドアップディスプレイ[HUD]の説明やら、電動パーキングブレーキスイッチなりの一通りレクチャーを終え。それじゃ~試乗へ行きますかとの流れになり、営業の方が運転席側の後部ドアを開けたところで、当方が後部座席へ座りたいと申し出る。最初こそ「助手席でなくていいので?」なる反応をする営業の方であったが「後部座席の乗り心地が知りたいんで~」っと運転席側の後部座席を陣取る当方。なんだかよくわからないけど、助手席へ回り込み座り “通常” の試乗コースを説明する営業の方と、ドライビングポジションを調整するとある知人。後部座席に座り、真っ先にリクライニングレバーでシートを後ろへ倒し。シートベルトをしたところで背中上部に感じる突起物……あぁ、この後部座席はヘッドレストを上げないといけないタイプだった。両手を首の後ろへと回し、ヘッドレストを上げるも……あれ? 何処まで上がるんだ??? 完全に上げきるまで固定できないようで、ヘットレストの高さを調整できず。シートベルトをしてからのヘッドレスト調整は肩がつらひ……ぼそぼそ。座る前に、事前にヘットレストを上げておくことが推奨ですね。そんな自分の体の硬さに嘆きつつ、シートに体を預けてみるや、スライド機構で一番後ろまで下げてある状態なのでコンパクトSUVとは思えぬ足下空間の広さはあるのだが。肩くらいまでしかないシートバックから長く伸びるヘッドレストと、なんだか首が落ち着かず。上記にも記載しての通り、シートバックによる背中への圧迫感 & 小さなサイドサポートの反発力が強いので、こりゃ~後部座席に乗員の為に車両ネックパットや背中に背もたれクッションが必須だなぁ~なんて思いつつ。今回紹介するのは、4thシーズン挿入歌ミニアルバム「Wonderful Tour」ですっと、脳内でジャケット紹介し始めた所で、とある知人が車両を動かし始める。車両が数㍍と動いただけで体感する尋常ならざるボディ剛性。知識として、3点留めのストラットタワーバーやら構造用接着剤でカッチリ強固なボディ剛性を仕立てている! ってのはわかってはいたが。この鉄の塊に包まれているかの様な感覚、 “LANCER Evolution Ⅹ” 並と表現してしまうとさすがに言い過ぎではあるが。そのベース車両であるGALANT FORTIS(セダン)と同等か……それ以上のボディ剛性があるんじゃないか!? なんて感じてしまう程だ。SUVのモノコック構造と、同じモノコック構造のであってもボディの構造上、圧倒的にセダンタイプからは不利であるにも拘わらず。“ルナチタニウム合金” でも採用したのかと思わずにはいられない。そんな後部座席で、ナノ洗浄の食器用洗剤商品名を心の中で叫んでいる当方などつゆ知らず、軽快に新型車を走らせるとある知人。ここですかさず、セールスポイントと「どうです、車内も静かでしょ」っと、販売促進マニュアルに書きつられてあるであろう台詞をぶっ込んでくる営業の方。運転席に座るとある知人は「そうですねぇ~」なんて適当に返答をしているも……ゴーゴーと聞こえる走行音に「それは違うよ!」っと、銀河に吠えたくなる……のをグッと堪える当方。音源の元を探るべく、暫し走行音に耳を傾けているとドアウィンドウガラスの遮音性の高いようで、明らかにドアウィンドウガラスより上と下では、走行音のボリュームが違う。これはロードノイズが入り込んできているんだろうと、タイヤボックスへ耳を向けるも……どうにも、聞こえる音源はドア付近からのような気がする。とはいえ、音の大きさ的にRVR(DBA-GA3W/GA4W)と比べれば抑えられてはいるし。OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)と比べると……15年式辺りのロードノイズ音なので、この価格帯で気にしすぎと言われてしまえば、まさにその通りなんですけどね。然し、ロードノイズ以上に気になったというか、体感的に厳しいのが乗り心地だ。開発・調整をした人としては「リアが跳ねる感じする~」っと、指摘されることのないよう路面からの入力があった際の衝撃を和らげ下からの突き上げを感じさせないように調整をしているようで。整備されている路面を走行している分には、後部座席自体の背中に感じる圧迫感が~……は、さておき。乗り心地としては申し分はなかったが、ひとたび路面に凹凸のある荒れた路面に差し差し掛かるや否や、左右に強く弾かれるかのような、揺すられる現象が起きる。この謎の挙動を分析すべく、後部座席にどっかりと体を預け、路面からの入力があった際の車両の動きに身を任せてみたところ、例えば右後輪だけに凹凸路面を通過すると、後部座席の当方に対し↖、↗、↖のワンサイクルバウンドが発生。更に後部座席(正確には背もたれ)の固さとサイドの高反発なシート素材も相まって、体が跳ねる様に揺すられるのなんの……。そんな状態で、荒れた路面なんて走行しようものなら “shake it off” ですよ。恐らく、この新型車。ダブルレーンチェンジやら、急旋回をしても、操縦安定性水準をかなり高めに設定するあまり、リアの足回り(↖、↗軸)を強くしすぎているんじゃ……。ここで、個人的には後部座席の左右独立 200 mm のシートスライド機構とか、車両総重量を⤴するだけで、殆ど動かすこともないだろうし……省いちゃっても良かったのじゃないの? なんて浅はかな疑問を抱いていたのですが。この左右独立 200 mm のシートスライド機構を採用した事により、リア荷重が増加。本来ならば、もっと↖、↗軸に跳ねる所を、この程度の跳ねで抑えられているのではないかと……勝手な憶測をする当方はさておき。運転したとある知人曰く、ステアリングが軽く、クイックに操舵できるので “小回り” がいいそうで。エンジンも1.5 L とは思えない程に力強く、どんどん加速しちゃうもんだから、気を付けないと直ぐに速度オーバーしてしまう。然し、ヘッドアップディスプレイ[HUD]にて、車速表示が表示されるから、運転していて車速の確認に大変便利とのこと。とある知人的には、概ね好印象だったようなので、満足のいく試乗が出来たことだし。お暇しますか……と戦略的撤退をしようとするも。営業方より「続けて行きましょう」なる試乗を催促される上。とある知人も「自分も後部座席の乗り心地を知りたい」なんて言い始めるではないか。ここでダメ。ゼッタイ。と、「時間とか大丈夫なん?」遠回しに後部座席に座ることを阻止しようと試みるも、流れ的に試乗をせざるを得ない状況に陥り致し方なく……運転席に座ることに。
この新型車に関して、試乗する気なんぞ更々なかった当方。前知識は公式サイトのアーカイブ動画と、オカザえもんのお膝元でごにょごにょ……くらいの情報しかしらず。これっぽっちもよくわからないのですが、とりあえずドライビングポジションを調整すべく。フットレストに左足を置き、スライドで運転席を前へスライドさせ。ブレーキペダルを深く踏み込んでも余裕のある位置にスライド調整したついでにエンジンスイッチを押しエンジンを始動。ステアリングの左根元にあるレバーを下げ、ステアリングを上下・前後と以前試乗したOUTLANDER PHEV感覚で調整すると、やけにステアリングが近!! 大柄な人やら、足が長い人とか、かなりの体格の違いをカバーできるように設計したんかな? 続いて、高さ調整レバーを何度も引き。運転席の高さを最大限にまでするや、高さ調整の上げ幅が大きいのか? 視線のほぼ真横にルームミラーが!? いやいや、これじゃ~運転中視界の邪魔じゃと、今度は高さ調整レバーを数度押しルームミラーが視界の邪魔にならない位置まで運転席を下げる。どうやら、設計した人の意図としては、SUV……とはいっても、“SPORTS” を意識しての設計なので、ドライビングポジションもSPORTS車の様な低い位置で運転するですよね? 的な設計がなされている様で、あまり運転席を上げまくると、フロントガラス上部との距離が……。次にサイドミラー調整と視線をやると、Aピラーの根元付近の死角エリアを小さくすべく、サイドミラーをAピラー付け根よりやや後ろに設置ポイントを移動したことにより、自分のドライビング(運転席を高めに調整)では、サイドミラーも近!! やっぱり、運転席は低め~中間辺りが適切な高さなようだ。まぁ、運転中の視野範囲にボンネットを入れたい当方としては、高めの着座位置を変えるる気は無いんですけどね。それにしても、サイドミラー自体が大きく、視野範囲が広くて非常に良いんですが……この新型車。 車両寸法的には、全幅 1,805 mm とOUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)と然程(全幅 1,800 ~1,810 mm)変わらない全幅ではあるが。ミラー to ミラーと、所謂サイドミラーを含む全幅寸法では約 2,165 mm なんだそうで。三自のフラッグシップ車であるPAJERO(DBA-V93W / LDA-V98W)の車両寸法の全幅1,875 mm と車両はこの新型車よりも大きいのだが。サイドミラーを含む全幅では、1,985 mmとこの新型車の方がサイドミラーを含む全幅でか大きいので、中央線のない細い道路なりの車同士のすれ違いで、車両寸法的にいけそうだからと油断して行ってしまうと、サイドミラーが……なんて事になるんではないかと。運転する際には、サイドミラー幅も考慮した方が良さそうだ。因みに、この新型車より小さなRVR(DBA-GA3W/GA4W)も、車両寸法的的には1,770 mm 何ですが。実はサイドミラーを含む全幅では 2,135 mm(ウインカー付きドアミラー装着車)と以外と大きくなるので、運転する車両は車両寸法の全幅も然る事ながら、ミラー to ミラーも知っておいた方がいいかと。次にシートベルトを締めた動作のついでにブレーキオートホールドスイッチを押してみたところ、なななんと! ブレーキオートホールド機能がONになるではないか!! 以前試乗したOUTLANDER(DBA-GF8W /DLA-GG2W)では、一旦車両を少しでも動かさない限り、ブレーキオートホールド機能をONにすることが出来なかったが。この新型車からか? ①エンジンの電源がON ②運転席のシートベルト着用 ③運転席のドアが閉まっているの条件が整えばブレーキオートホールド機能をONが可能になったようだ。※但し、上記のいずれかがの条件が満たされなくなった場合、即時ブレーキオートホールド機能はOFFになるので、駐車時・運転席より離れる場合は手動で電動パーキングブレーキレバーを引く必要あり。なんだか、細々とした所が便利に改善されてるなぁ~なんて感動していたところ。センターコンソール中央に設置されるハザードランプ左側にある助手席 & 後部座席シートベルト警告ランプ。これにより、助手席の営業の方は勿論のこと。運転席後方に座るとある知人がシートベルトを着用したか否かが一目で識別出来るのはナイスですね! 特に運転席後方の乗員がシートベルトの着用有無は目視で確認しづらいですからねぇ~。最後に、三自としては初となる。この新型車の目玉? 機能であるヘッドアップディスプレイ[HUD]の表示位置調整をすべく、ステアリング右にあるスイッチで上下調整をするも……ここでも着座位置を高くする奴は想定していない? 将又、表示できる角度的な問題があるのか、当方の目線で、ヘッドアップディスプレイ[HUD]の中央に表示位置を調整すること適わず。う~ん、表示位置が上過ぎるのも気になるが、それ以上に表示フォント小っさ!? 表示できる情報量も然程ある訳でもないのなら、表示の拡大・縮小設定もあっても……まぁ、収納式ヘッドアップディスプレイ[HUD]が付いたんですよ! っと、玩具的な捉え方が適切なのだろう。サクッと運転準備が整ったところで、ブレーキペダルを踏み込みシフトレバーを『D』にする当方に隣の営業の方より「電動パーキングブレーキレバーを押して解除を~」なる一言を入れられるも。かまへんかまへんと、アクセルペダルを軽く踏み込む当方。車体後方が僅かに沈み込み、サイドブレーキかかりっぱなしですよ~的な車両の挙動を一瞬するも、直ちに電動パーキングブレーキが解除され走り出す。いやはや、以前試乗したOUTLANDER(DBA-GF8W /DLA-GG2W)の時に電動パーキングブレーキ操作を覚えていて良かったZ!! クリープ現象でのそのそと販売店敷地内駐車場を移動した後、国道へと合流すべく一旦停車。前を横切っていく走行車の流れが途切れるのを待ちつつ、マルチインフォメーションディスプレイスイッチで表示画面を “平均燃費表示・ECO ドライブアシスト” に切り替え、スイッチ長押しで平均燃費値表示をリセット。これで準備が整ったと、顔を上げ車線に目をやったところ、うまい具合に後続車が途切れていたのでアクセルペダルを軽く踏み込み出発する。走り出すと、エンジン音が微かに耳に届く? なんて程の1,900回転と低回転領域でみるみる 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h と車速は上がり。加速感を然程感じることなく、エンジン回転が1,200回転~1,400回転数辺りで落ち着く頃には、気が付けば法定速度と軽やかな0スタートをするのだが……あれ? この感覚。どっかで酷似した体感をした様な……頭を傾げる当方。そんな微妙なリアクションをされたのは初めて? とばかりに、隣に座る営業の方より「GALANTに乗っているお客さん(恐らくGALANT FORTIS 2.0 L モデル?)が自分の車よりスタートダッシュが速いと絶賛をしていたんですが、気に入りません?」なる問いかけをされてしまう。GALANT FORTIS……1.8 L モデル関しては、運転したことがないのでニャンとも言えないのですが。国内で販売していたモデルに関して、搭載されているCVTが、GALANT FORTISが発売された当時のCVTということもあり。どうしても0スタート時の加速時、エンジン回転に伴わない加速でもたつきがあり。ある程度の車速に乗れば問題ないんだけど……と、エンジン総排気量云々以前にCVTなる “トランスミッション” が足を引っ張っていたので、如何ともしがたい出だしのもたつきや、巡行中からのキックダウンでの急加速など。これだからCVTはねぇ~なんて思わせる仕様であったが。15年式RVRより、Jatcoが新開発した次世代のCVTが採用され。従来のCVTではできなかった発進時からの即ロックアップでエンジンからの動力ロスを減少させ。変速比幅の拡大で、より低速域から高速域まで効率の良い変速比での走行が可能となった事で、エンジン総排気量は1.8 L と変わらず、トランスミッションだが変わっただけでしょ~と、運転してみたところ別次元の走りじゃん!? ってな具合に進化したCVTに驚き。そんな世代の上がったCVTを採用した車両を運転したことのあるものならば、国内で販売されていたGALANT FORTIS(海外で継続販売されているモデルには、MCで新型CVTが採用しれている)の前世代CVTと現在のCVTと加速感を比べられてもねぇ……。話にならないLvで、この新型車両の方が速いわ!! とか思わずツッコミを入れたくなる気持ちをグッと抑え。「いや~加速感に不満があるとかじゃなく。なんかこう……ピンとこないんですよねぇ~。ガソリン車なのに、静かすぎるからかな?」ニャンとも言えないモヤモヤ感を抱きながら、この感覚、なんだっけかなぁ~っと頭を悩ませ走行すること暫し。スーッと軽快に車速が伸び、気が付けばって、EV走行をしているOUTLANDER PHEVやんっと、ここでようやくモヤモヤの正体に気が付く。この大してアクセルペダルを踏み込み事なく、みるみる加速していく感じはEVっぽいなぁ~っと、なんだかガソリン車を運転している感覚に乏しく。静かで軽快に加速ってポイントを好意的に捉えるか? いやいや、内燃機関とエンジンが主体の車両なんだから、そのエンジン音を聴かせてくれYOっと、否定的に捉えるかで大分この車両に対する評価は変わってくるんじゃないかと。ただ、ガソリン車でありながらも、さもEVの様な走り出しが出来るってのは、感心せざるを得ない。それにしても、この新型車。走り出しからのスムーズな加速も然る事ながら、巡航速度域でもある 50 ㎞/h ~ 60 ㎞/h 付近まで車速が上がったところから、殆どアクセルペダルの踏み込み量を変えていないにもかかわらず、更にそこから伸びるように加速をしていき。ドライバーとしては、法定速度域くらいの車速で走行しているつもりが、気が付けば車速が 70 ㎞/h ~ 80 ㎞/h を軽くオーバーしてしまう。なるほど、これがとある知人が「速度オーバー」してしまうと証言していた原因か。こりゃ~、この新型車の速度感覚になれるまでは、ヘッドアップディスプレイ[HUD]を常に展開しておき。現在の車速を意識していないと、青い制服を着た方々の
車両寸法的には、全幅 1,805 mm とOUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)と然程(全幅 1,800 ~1,810 mm)変わらない全幅ではあるが。ミラー to ミラーと、所謂サイドミラーを含む全幅寸法では約 2,165 mm なんだそうで。三自のフラッグシップ車であるPAJERO(DBA-V93W / LDA-V98W)の車両寸法の全幅1,875 mm と車両はこの新型車よりも大きいのだが。サイドミラーを含む全幅では、1,985 mmとこの新型車の方がサイドミラーを含む全幅でか大きいので、中央線のない細い道路なりの車同士のすれ違いで、車両寸法的にいけそうだからと油断して行ってしまうと、サイドミラーが……なんて事になるんではないかと。運転する際には、サイドミラー幅も考慮した方が良さそうだ。因みに、この新型車より小さなRVR(DBA-GA3W/GA4W)も、車両寸法的的には1,770 mm 何ですが。実はサイドミラーを含む全幅では 2,135 mm(ウインカー付きドアミラー装着車)と以外と大きくなるので、運転する車両は車両寸法の全幅も然る事ながら、ミラー to ミラーも知っておいた方がいいかと。次にシートベルトを締めた動作のついでにブレーキオートホールドスイッチを押してみたところ、なななんと! ブレーキオートホールド機能がONになるではないか!! 以前試乗したOUTLANDER(DBA-GF8W /DLA-GG2W)では、一旦車両を少しでも動かさない限り、ブレーキオートホールド機能をONにすることが出来なかったが。この新型車からか? ①エンジンの電源がON ②運転席のシートベルト着用 ③運転席のドアが閉まっているの条件が整えばブレーキオートホールド機能をONが可能になったようだ。※但し、上記のいずれかがの条件が満たされなくなった場合、即時ブレーキオートホールド機能はOFFになるので、駐車時・運転席より離れる場合は手動で電動パーキングブレーキレバーを引く必要あり。なんだか、細々とした所が便利に改善されてるなぁ~なんて感動していたところ。センターコンソール中央に設置されるハザードランプ左側にある助手席 & 後部座席シートベルト警告ランプ。これにより、助手席の営業の方は勿論のこと。運転席後方に座るとある知人がシートベルトを着用したか否かが一目で識別出来るのはナイスですね! 特に運転席後方の乗員がシートベルトの着用有無は目視で確認しづらいですからねぇ~。最後に、三自としては初となる。この新型車の目玉? 機能であるヘッドアップディスプレイ[HUD]の表示位置調整をすべく、ステアリング右にあるスイッチで上下調整をするも……ここでも着座位置を高くする奴は想定していない? 将又、表示できる角度的な問題があるのか、当方の目線で、ヘッドアップディスプレイ[HUD]の中央に表示位置を調整すること適わず。う~ん、表示位置が上過ぎるのも気になるが、それ以上に表示フォント小っさ!? 表示できる情報量も然程ある訳でもないのなら、表示の拡大・縮小設定もあっても……まぁ、収納式ヘッドアップディスプレイ[HUD]が付いたんですよ! っと、玩具的な捉え方が適切なのだろう。サクッと運転準備が整ったところで、ブレーキペダルを踏み込みシフトレバーを『D』にする当方に隣の営業の方より「電動パーキングブレーキレバーを押して解除を~」なる一言を入れられるも。かまへんかまへんと、アクセルペダルを軽く踏み込む当方。車体後方が僅かに沈み込み、サイドブレーキかかりっぱなしですよ~的な車両の挙動を一瞬するも、直ちに電動パーキングブレーキが解除され走り出す。いやはや、以前試乗したOUTLANDER(DBA-GF8W /DLA-GG2W)の時に電動パーキングブレーキ操作を覚えていて良かったZ!! クリープ現象でのそのそと販売店敷地内駐車場を移動した後、国道へと合流すべく一旦停車。前を横切っていく走行車の流れが途切れるのを待ちつつ、マルチインフォメーションディスプレイスイッチで表示画面を “平均燃費表示・ECO ドライブアシスト” に切り替え、スイッチ長押しで平均燃費値表示をリセット。これで準備が整ったと、顔を上げ車線に目をやったところ、うまい具合に後続車が途切れていたのでアクセルペダルを軽く踏み込み出発する。走り出すと、エンジン音が微かに耳に届く? なんて程の1,900回転と低回転領域でみるみる 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h と車速は上がり。加速感を然程感じることなく、エンジン回転が1,200回転~1,400回転数辺りで落ち着く頃には、気が付けば法定速度と軽やかな0スタートをするのだが……あれ? この感覚。どっかで酷似した体感をした様な……頭を傾げる当方。そんな微妙なリアクションをされたのは初めて? とばかりに、隣に座る営業の方より「GALANTに乗っているお客さん(恐らくGALANT FORTIS 2.0 L モデル?)が自分の車よりスタートダッシュが速いと絶賛をしていたんですが、気に入りません?」なる問いかけをされてしまう。GALANT FORTIS……1.8 L モデル関しては、運転したことがないのでニャンとも言えないのですが。国内で販売していたモデルに関して、搭載されているCVTが、GALANT FORTISが発売された当時のCVTということもあり。どうしても0スタート時の加速時、エンジン回転に伴わない加速でもたつきがあり。ある程度の車速に乗れば問題ないんだけど……と、エンジン総排気量云々以前にCVTなる “トランスミッション” が足を引っ張っていたので、如何ともしがたい出だしのもたつきや、巡行中からのキックダウンでの急加速など。これだからCVTはねぇ~なんて思わせる仕様であったが。15年式RVRより、Jatcoが新開発した次世代のCVTが採用され。従来のCVTではできなかった発進時からの即ロックアップでエンジンからの動力ロスを減少させ。変速比幅の拡大で、より低速域から高速域まで効率の良い変速比での走行が可能となった事で、エンジン総排気量は1.8 L と変わらず、トランスミッションだが変わっただけでしょ~と、運転してみたところ別次元の走りじゃん!? ってな具合に進化したCVTに驚き。そんな世代の上がったCVTを採用した車両を運転したことのあるものならば、国内で販売されていたGALANT FORTIS(海外で継続販売されているモデルには、MCで新型CVTが採用しれている)の前世代CVTと現在のCVTと加速感を比べられてもねぇ……。話にならないLvで、この新型車両の方が速いわ!! とか思わずツッコミを入れたくなる気持ちをグッと抑え。「いや~加速感に不満があるとかじゃなく。なんかこう……ピンとこないんですよねぇ~。ガソリン車なのに、静かすぎるからかな?」ニャンとも言えないモヤモヤ感を抱きながら、この感覚、なんだっけかなぁ~っと頭を悩ませ走行すること暫し。スーッと軽快に車速が伸び、気が付けばって、EV走行をしているOUTLANDER PHEVやんっと、ここでようやくモヤモヤの正体に気が付く。この大してアクセルペダルを踏み込み事なく、みるみる加速していく感じはEVっぽいなぁ~っと、なんだかガソリン車を運転している感覚に乏しく。静かで軽快に加速ってポイントを好意的に捉えるか? いやいや、内燃機関とエンジンが主体の車両なんだから、そのエンジン音を聴かせてくれYOっと、否定的に捉えるかで大分この車両に対する評価は変わってくるんじゃないかと。ただ、ガソリン車でありながらも、さもEVの様な走り出しが出来るってのは、感心せざるを得ない。それにしても、この新型車。走り出しからのスムーズな加速も然る事ながら、巡航速度域でもある 50 ㎞/h ~ 60 ㎞/h 付近まで車速が上がったところから、殆どアクセルペダルの踏み込み量を変えていないにもかかわらず、更にそこから伸びるように加速をしていき。ドライバーとしては、法定速度域くらいの車速で走行しているつもりが、気が付けば車速が 70 ㎞/h ~ 80 ㎞/h を軽くオーバーしてしまう。なるほど、これがとある知人が「速度オーバー」してしまうと証言していた原因か。こりゃ~、この新型車の速度感覚になれるまでは、ヘッドアップディスプレイ[HUD]を常に展開しておき。現在の車速を意識していないと、青い制服を着た方々のノルマ……もとい、街の交通標識やガードレール等、地域に貢献できる特別な権利が獲得出来ちゃいますね。しかし、下級市民である当方には、そんな地域に貢献だなんて……恐れ多い。先行車・単独で走行する場面では、身分相応の速度域を意識した方が良さそうだ。それにしても、CVTも然る事ながら、この新開発された直列4気筒1.5 L直噴ターボエンジンこと、“4B40”。車両重量が約1.5㌧(正確には1,460 ㎏ ~ 1,550 ㎏)もある車両で、これだけ低回転領域でこの走りが出来るのなら。車両重量が1㌧(正確には900 ㎏)に満たないMIRAGE(DBA-A03A)に搭載したら、相当面白そうですねぇ~なんて話を振ってみるも「無理無理、MIRAGEのボディ剛性じゃ~とても耐えられない」と、速攻で否定されてしまう。そうは言っても、 MIRAGEをベース車両にラリーへ参戦していたりするので、それこそ構造用接着剤でボディ剛性を強化し。この新型車で採用されている
MIRAGEをベース車両にラリーへ参戦していたりするので、それこそ構造用接着剤でボディ剛性を強化し。この新型車で採用されている “スーパーオールホイールコンチョロォォル” こと、電子制御4WDの後輪への駆動力をカットし、簡素化した電子制御FF車(仮)なんて旋回性に特化した駆動制御するMIRAGE Version R(仮)でも造れば、コンパクトカーで遊びたいんよね~ってな客層に売れると思うんだけどなぁ。この新型車以外にも、搭載車種ラインナップが増えることを期待する虚けな当方であったが。営業の方としては「 “直噴” エンジンってのが……ちょっと……」と、新型エンジンに対し不安を抱いているようだ。まぁ、その気持ちを何となく察するところではあるが、開発側もその点にはついて、細心の注意を払っているようで。世界各国、何台ものテスト車両を走り回らせ、計うん十万㎞と問題が発生しないか? テストにテストを重ねているそうで。本来であれば、もっとこの新型エンジンの性能上限値があるにも拘わらず、耐久性やら燃費的な事情もあるのだろうが、なにより安全性に重点を置き。敢えてエンジン性能を抑えている(そもそもCVTが新型エンジンの最大性能に耐えられない物が採用されている)んだそうな。そんな安全マージン的な保険をかけまくっている制御・設計の上、この新型エンジン。
“スーパーオールホイールコンチョロォォル” こと、電子制御4WDの後輪への駆動力をカットし、簡素化した電子制御FF車(仮)なんて旋回性に特化した駆動制御するMIRAGE Version R(仮)でも造れば、コンパクトカーで遊びたいんよね~ってな客層に売れると思うんだけどなぁ。この新型車以外にも、搭載車種ラインナップが増えることを期待する虚けな当方であったが。営業の方としては「 “直噴” エンジンってのが……ちょっと……」と、新型エンジンに対し不安を抱いているようだ。まぁ、その気持ちを何となく察するところではあるが、開発側もその点にはついて、細心の注意を払っているようで。世界各国、何台ものテスト車両を走り回らせ、計うん十万㎞と問題が発生しないか? テストにテストを重ねているそうで。本来であれば、もっとこの新型エンジンの性能上限値があるにも拘わらず、耐久性やら燃費的な事情もあるのだろうが、なにより安全性に重点を置き。敢えてエンジン性能を抑えている(そもそもCVTが新型エンジンの最大性能に耐えられない物が採用されている)んだそうな。そんな安全マージン的な保険をかけまくっている制御・設計の上、この新型エンジン。 通常の回転域での燃焼では、従来のガソリンエンジン同様の “ポート噴射” のみで。エンジンを高回転域まで回した際に “ポート噴射” & “直噴” の “デュアルインジェクションシステム” なる、ダブルで燃料噴射を~っと、なんだかよくわからないが、従来のターボエンジンより高負荷のかかるブースト域での違いがあるんだそうな。専門的な事はお詳しい方に丸投げするとして、とりあえず “高回転域” までエンジンをぶん回す事さえしなければ “直噴” 機能が働くことはなく。仮に “直噴” を使う領域までエンジンをぶん回しまくったとして、“直噴” 特有の問題点である燃えカツが~なんてのも、エンジンをぶん回している時点で、指して気にするような事になるのか……。まぁ、コールドスタートとエンジン始動直後(エンジンが温まっていない状態)にアクセルペダル全開っと、エンジンぶん回して “直噴” をするような無茶な事をしたら、さすがに何かしらの問題が発生するとは思うも……そんな事したら “直噴” 云々以前にどんなエンジンだろうと問題があるか。 なんにしても、新型エンジン故に、一般ユーザーが四の五の考えず、メーカー側が想定もし得ない環境・操作・条件等の様々な適当な使い方をし始め2~3年は経たないと、どんな問題が発生する or しないにしても、わからない事もある訳で……こればっかりはねぇ。無用なトラブルにあいたくない~とか、製品に完璧主義的なものを求めるのなら、新型と名付くエンジンは市場投入されてから最低でも5年以上は見送るべきかと……。何にしても、なんらかの問題が仮にあったと仮定しても「誠に勝手ながら、4B4倶楽部に加入させて頂きました」って具合に運転席側のドアトリガーの下にステッカーを貼れば何の問題もないでしょ。そんな楽観的な返答をする虚けな当方に、渋い反応をする営業の方……どうやら、返答にまずったようだ。う~ん、なんらかの問題が仮に発生した際、ドアトリガーの下にステッカーを貼る以外の方法があるとしたら、例えば……
通常の回転域での燃焼では、従来のガソリンエンジン同様の “ポート噴射” のみで。エンジンを高回転域まで回した際に “ポート噴射” & “直噴” の “デュアルインジェクションシステム” なる、ダブルで燃料噴射を~っと、なんだかよくわからないが、従来のターボエンジンより高負荷のかかるブースト域での違いがあるんだそうな。専門的な事はお詳しい方に丸投げするとして、とりあえず “高回転域” までエンジンをぶん回す事さえしなければ “直噴” 機能が働くことはなく。仮に “直噴” を使う領域までエンジンをぶん回しまくったとして、“直噴” 特有の問題点である燃えカツが~なんてのも、エンジンをぶん回している時点で、指して気にするような事になるのか……。まぁ、コールドスタートとエンジン始動直後(エンジンが温まっていない状態)にアクセルペダル全開っと、エンジンぶん回して “直噴” をするような無茶な事をしたら、さすがに何かしらの問題が発生するとは思うも……そんな事したら “直噴” 云々以前にどんなエンジンだろうと問題があるか。 なんにしても、新型エンジン故に、一般ユーザーが四の五の考えず、メーカー側が想定もし得ない環境・操作・条件等の様々な適当な使い方をし始め2~3年は経たないと、どんな問題が発生する or しないにしても、わからない事もある訳で……こればっかりはねぇ。無用なトラブルにあいたくない~とか、製品に完璧主義的なものを求めるのなら、新型と名付くエンジンは市場投入されてから最低でも5年以上は見送るべきかと……。何にしても、なんらかの問題が仮にあったと仮定しても「誠に勝手ながら、4B4倶楽部に加入させて頂きました」って具合に運転席側のドアトリガーの下にステッカーを貼れば何の問題もないでしょ。そんな楽観的な返答をする虚けな当方に、渋い反応をする営業の方……どうやら、返答にまずったようだ。う~ん、なんらかの問題が仮に発生した際、ドアトリガーの下にステッカーを貼る以外の方法があるとしたら、例えば…… ECUの改良や、所々のパーツを交換しただけでは根本的な解決が出来へん。せや、しれっとエンジンのバージョンアップ版が出来たんですYO! と、総排気量を⤴させたり。より性能が向上したので、以前のエンジンに関しては、忘れて下さい。つきましては、購入したオーナーには車検を迎える機会を機に、素晴らしいバージョンアップしたエンジンを採用した新車へ
ECUの改良や、所々のパーツを交換しただけでは根本的な解決が出来へん。せや、しれっとエンジンのバージョンアップ版が出来たんですYO! と、総排気量を⤴させたり。より性能が向上したので、以前のエンジンに関しては、忘れて下さい。つきましては、購入したオーナーには車検を迎える機会を機に、素晴らしいバージョンアップしたエンジンを採用した新車へ早急に……乗り換えをご提案。下取りも価格も頑張っちゃいますよ♪ っと、自然な流れで乗り換えを促せば、もうバッチ……リ? しまった!? このエンジンへの不安に関する話題の返答。とどのつまり、どの様なアプローチの仕方で返答しても、結果的に失敗する欠陥返答しか思い浮かばない!? アイヤ~っと遊んでいる間に毎度お馴染みのやや傾斜のある坂道ポイントへ差し掛かる。周囲の安全確認と、グルッと周囲を見回したところ前方に車両が1台目視出来るも、数百㍍も先である。車速を一旦最徐行速度まで落とした後、アクセルペダルを躊躇なく底まで踏み込む。アクセルペダルを踏み込んでから、一拍程あるかないかの僅か反応が遅れてからエンジン回転がグンと上がり始め。エンジン回転が2,100回転に差し掛かるや、パワフルなターボトルクで急加速し始め。先程まで存在感をあまり感じさせることのない静かなエンジン音が、なかなかのボリューム(とは言っても、エンジン音はかなり抑えられている)へとなり。エンジン回転数が4,200回転付近まで到達するや、僅かに加速感の途切れる一拍おいて、更にもう一段トルクの山で加速する。体感的に、シートに体が押さえ付けられる感覚はDELICA D:5(LDA-CV1W)2.2 L DI-D ベタ踏み加速をやや凌ぐ勢いで、ドッカンターボとまでは行かずとも、ターボが効き始め(2,000回転を超え)てからの加速の仕方がどえりゃ~ことになっとります。ただ、何故か5,000回転付近から加速の伸びが失速……。ベタ踏み加速をしてみた感覚として “ポート噴射” のみから “直噴” も加わるデュアルなんちゃって状態に入る高回転領域が4,000回転以上と推測。燃料噴射制御の切り替わる瞬間に若干のターボラグ的な、間が発生するのと。レッドゾーンより手前のエンジン回転に差し掛かると速度リミッターの燃料カットの様な制御を入れてるのか? それ以上エンジンを回そうというより、CVTの変速比を変える制御を積極的にしていこうという走りをした。まぁ、百㍍程度のベタ踏み加速なので、それ以上の加速はどうなるかはわからないなせよ。最徐行速度域から80 ㎞/h を優に超える車速へ軽々加速でき。つい今し方まで数百㍍も先行車していた車両に、ものの数秒で真後ろまで追いつくとかね。 COLT RALLIART Version-R(CBA-Z27AG)に匹敵する……とまでいってしまうと、さすがに誇張しすぎになってしまうが。エンジン性能を抑えた制御 & 車両重量+乗員で約1.8㌧近くの状態でこの加速は凄すぎ!!
COLT RALLIART Version-R(CBA-Z27AG)に匹敵する……とまでいってしまうと、さすがに誇張しすぎになってしまうが。エンジン性能を抑えた制御 & 車両重量+乗員で約1.8㌧近くの状態でこの加速は凄すぎ!!
国道Lvを走行するには、ちょいとパワフル過ぎる印象を受けなくもない動力性能はさておき。後部座席に乗車した際に感じた↖、↗軸に跳ねる挙動。運転席では、腰辺りの左右をホールドする部分や、エンジンなどフロント荷重がリアに比べ重いこともあるのだろう。荒れた路面を通過する際、後部座席に乗車している時に比べれば……↖、↗軸に跳ねる強さは軽減されるので、ちょっと足回りを固めたSPORTS車両に乗っている? 感覚の乗り心地ではある為、運転している限りでは、それ程気にするLvではない。ただ、下からの突き上げる様な跳ね……とは異なるので、この↖、↗軸の跳ねる乗り心地について、許容範囲であるか否かは要確認です。そんな乗り心地の確認の為と、道路上に点在するマンホールの蓋を敢えて通過するような走行をし「やっぱり揺すられるなぁ~(ぼそ)」なんて漏らしたところ。後部座席に座るとある知人より「こっちも」なるコメントが!! しまった、購入検討している人を後部座席に乗せているんじゃった。こりゃ~まずったと、オドメーターもそれ程進んでいないから、まだ足回りの固さがあるのだろうし。もう1,000 ㎞ ~ 2,000 ㎞ と走行させたり。タイヤのインチダウン……もしくは、ロードノイズ対策も兼ねて、コンフォートタイヤを履かせちゃうって選択肢もありだねぇ~っと、苦し紛れなフォローを入れる虚けな当方。いやはや、後部座席は左右独立 200 mm のシートスライド機構で足元ノビノビ~とか、さも後部座席の乗り心地も重視されてセッティングされているかと漠然と思ってしまうが。表現的に2+3とか、エマージェンシート的な捉え方が適切なのかも知れない。運転して感じるのは、ステアリング操舵の舵角に対し、タイヤの切れ角がやや大きめに切れ、ステアリング操舵している感覚以上にスイスイと曲がれるので、とある知人が「小回りがいい」と感じたのは、この事だろう。ただ、あくまで交差点等の右左折ではグイグイ曲がれまっせ♪ とはなっているが。この新型車、最小半径は 5.4 m (RVR・OUTLANDER系は 5.3 m )なので、車庫入れ等の切り返しが必要となる場面や、Uターンと片側一車線のような道路幅が然程大きくない道路で、最小半径 5.0 m を下回るコンパクトカーの様に小回りがいい……とはまた違うので、あくまで “クイックステアリング” と理解した方が良さそうだ。また、ステアリングがやけに軽く、電動ステアリング特有の手応えのない感覚で軽々操舵出来てしまうので。 “クイックステアリング” & 軽い操舵が相まって、まぁ~笑っちゃうくらいにステアリングが回る回る……コーヒーカップか!! そんな遊具的な手応えに、ステアリングがek CUSTOM(DBA-B11W)と同じ本革巻ステアリングホイール(メッキ & ピアノブラックアクセント)ということもあり。なんだか、買い物CAR or Go-cart的な車両を運転しているような感覚で……どうにもしっくりこない。もうちっと、油圧式を彷彿とさせるような、重め……とまでは言わなくとも、手応えのあるステアリングが個人的には好みではある。次に気になったのが、エンジンブレーキにシフトダウンとパドルシフトを使おうとしたところ、指が……空を切る!? ありゃ? パドルシフトって、この大きさだっけか??? 三自の他の車両に採用されているパドルシフトと実際に比べた訳ではないので、ただの勘違いかも知れないが。気持ち小さくなって……いる? 様な気がしたことと、パドルシフトの左側(-DOWN)を引き、『D』からSPORTSモードへ移行。変速ショックをやや感じながら、エンジンブレーキを効かせ速度調整仕様とすると、感覚的にエンジンブレーキの効きが薄い。おやっと、ヘッドアップディスプレイ[HUD]上に表記されるギア数にちらっと目をやったところ、当方が思っていた以上にギア数が高い。其処でようやく、この新型車は “8速SPORTSモードCVT” なんだったと思い出す。そんな訳で、エンジンブレーキ目的でパドルシフトを使う際は、気持ちパドルシフトの左側(-DOWN)を引く回数を+1回~2回多めに引くことを心がけた方が良いようだ。オートストップ & ゴー[AS & G]について、車速が0 ㎞ / h になり、完全停車してから一拍おいてからの作動制御となっているのだが。RVRだったかな? ブレーキペダルを踏み切らないと作動しないっという設定の所為で、オートストップ & ゴー[AS & G]を作動させるのに、意識的にブレーキペダルを強く踏み込む必要があったと記憶にあるのだが。この新型車に関して、車両が停止した状態で、やや深めにブレーキペダルを踏み込む(ブレーキの踏み込み域として8~9割くらい?)と作動するので、楽にオートストップ & ゴー[AS & G]が使えることが一点。更に嬉しいことに、ブレーキオートホールド機能をONにしていると、自動でブレーキを踏んだ状態を維持してくれるので、オートストップ & ゴー[AS & G]が作動したと同時にブレーキペダルから足を外しても、エンジンが再始動することもなく。しかも、自動でブレーキを踏んだ状態を維持してくれるということは……ブレーキランプも点灯したまま(運転席に座っている為、直接車両後方に回り確認した訳ではないが。後続車のメッキパーツに赤い光が反射が確認できたので、恐らく点灯していると思われ)と、信号待ち・渋滞で車列が詰まっている時等々、常にブレーキペダルを踏み続けることなく、足を休めることが出来るとか……グットですよ! 発進する際には、走り出した時と同様にアクセルペダルを踏むだ、け、で!! エンジン再始動 & ブレーキオートホールドが解除され、半テンポ程で走り出すことが可能とくる。いやはや、こんな贅沢極まるけしからん環境に馴れてしまったら、ブレーキオートホールドの無いオートストップ & ゴー[AS & G]とか……ないわ~。そんな便利機能にも弱点? を発見と、上り坂での信号待ちになりオートストップ & ゴー[AS & G]が作動。サイドブレーキ感覚で、電動パーキングブレーキレバーを引いたところ、突然エンジン再始動!? 原因を考えるに、電動パーキングブレーキレバーを引く = ブレーキオートホールド解除と同時に電動パーキングブレーキがかかる制御を行うので、オートストップ & ゴー[AS & G]の作動条件である “ブレーキが効いている状態” が満たされない状態になったことにより、エンジンが再始動してしまったようだ。電動パーキングブレーキをかけた状態で、オートストップ & ゴー[AS & G]を動作させつづめるにはブレーキペダルを踏み続ける必要があるようだ。それにしても、電動パーキングブレーキレバーを引いてから、動作するまでに体感2秒くらい? の間が開くので、初見だと本当に電動パーキングブレーキのレバー操作入力ができたのかわかりづらい。また、坂道に駐車する際などにもう1段強いパーキングブレーキをかける為にと、もう1回電動パーキングブレーキレバーを引く操作入力も、電動パーキングブレーキレバーを “カチカチ” っと連続で引くの? それとも、1回パーキングブレーキマークが点灯してから、もう1度電動パーキングブレーキレバーを引く??? 電動パーキングブレーキレバー操作が今一わからない。う~んっと、電動パーキングブレーキレバー操作をしている当方に、隣に座る営業の方より「ブレーキオートホールドとパーキングブレーキが動作している違いってわかるので?」なる質問をしてくるではないか……いやいや、そこは商品売るのに知っておかなアカンやらと思いつつ。速度メーターの右下辺りに緑のマークが点灯でブレーキオートホールド。速度メータの針根元の下に赤い『エクスクラメーションマーク』が表示でパーキングブレーキ。もう1回、電動パーキングブレーキレバーレバーを引くと、赤く点灯している『エクスクラメーションマーク』表示が消灯し、再度点灯直しもう1段強いパーキングブレーキ状態になったと表示されるんですよ~っと、ザックリした説明をする。パーキングブレーキの電子化の波に今一着いてこれない……のか? 「へぇ~」っと、速度メータを助手席より覗き込む営業の方。質問ついでにと「“左右独立温度コントロール式フルオートエアコン” のAUTOスイッチの横に “SYNC” なる謎のスイッチが加わっているんですけど、なんですこれ?」なる問いを投げかけられる当方。 “SYNC” って……そりゃ~、貴様と俺とは~♪ と、肩組んで唄おうZ! と、胸熱なんて具合に “スタートアップヒーター(この新型車には非搭載)” 的な強暖房モードスイッチ? なんて瞬時に察するも……先程のエンジン回答でのしくじりもあるしなぁ。うかつな発言は控えるべきかと、ここは素直に回答の “息切れ” であると白旗を揚げる。これはもう “徹底抗戦の決意” である……なんて受け取られかねない対応をしてしまう虚けな当方に気にすることなく、クローズボックスから取扱説明書を取り出し調べ始める営業の方。暫しの後「左右の独立温度設定を同じ温度に固定するスイッチみたいですよ。前からある “左右独立温度コントロール式フルオートエアコン” でAUTOスイッチの押し直しで左右の温度設定が同じになるのに、いるんですかね? このスイッチ」と、身も蓋もないバッサリと切り捨てるコメントをする営業の方。まぁ……ぶっちゃけ、 “左右独立温度コントロール式フルオートエアコン” のスイッチ類で一番押す頻度が多いであろうAUTOスイッチの幅を小さくしてまで、わざわざ “SYNC” なるスイッチを配置する必要性は感じられないわな。ただ、取扱説明書も読まないようなユーザー層から、「1度左右で違う温度設定したら戻らない……なんとかしろ!!」ってな大変貴重なご意見も寄せられた結果が、この “SYNC” なるスイッチが採用されたんたのだろう。それにしても、ドライビングポジションを調整する際。かなり高めの着座位置に設定ていしたので、ルームミラーとの距離感が~なんて思っていたのですが。実際に運転してみると、 着座位置が高いことによりボンネットが見える上。丁度ボンネットの右側のラインがうまい具合に目安となり。ドライバー視点で、車両の右端に座っている感覚で、車両感覚が掴みやすい。運転している感覚(視点的な意味で)としては、着座位置こそ低いが、PAJEROを運転している感覚に近く、非常に運転をしていて楽ではある……のだが。如何せん、この新型車両。フロントバンパーのボリューム感やら、ボンネットの膨らみがある関係で車両の左斜め前辺り……正確には、左前輪のエリア辺りの感覚が今一わかりづらい(大抵のSUVでそうだけど)のと、上記にも記載しての通り “クイックステアリング” と舵角に対し、タイヤの切り角が大きく切りてしまうので。路肩に寄せるとか、ガードレール等の障害物の合間を左折で通ろうとする時「あれ……ステアリングの舵角的に曲がれる切れ角とは思うけど、最小半径が 5.4 m だから、もうちょっとステアリングを切った方が良い? いやいや、ステアリングを切りすぎで左後輪前のサイドフェンダーを擦っちゃう???」と、ステアリングの舵角感覚 & 車両左側面の感覚を掴むまでは、ステアリングのカメラスイッチでマルチアラウンドモニター(バードアイビュー機能付)をカーナビゲーションシステムなりに表示させ、安全確認をした方が良さそうだ。1度ばかし、ベタ踏みをしたいがいは、基本的に1,900回転以上エンジンを回すこともなく走行した結果、
着座位置が高いことによりボンネットが見える上。丁度ボンネットの右側のラインがうまい具合に目安となり。ドライバー視点で、車両の右端に座っている感覚で、車両感覚が掴みやすい。運転している感覚(視点的な意味で)としては、着座位置こそ低いが、PAJEROを運転している感覚に近く、非常に運転をしていて楽ではある……のだが。如何せん、この新型車両。フロントバンパーのボリューム感やら、ボンネットの膨らみがある関係で車両の左斜め前辺り……正確には、左前輪のエリア辺りの感覚が今一わかりづらい(大抵のSUVでそうだけど)のと、上記にも記載しての通り “クイックステアリング” と舵角に対し、タイヤの切り角が大きく切りてしまうので。路肩に寄せるとか、ガードレール等の障害物の合間を左折で通ろうとする時「あれ……ステアリングの舵角的に曲がれる切れ角とは思うけど、最小半径が 5.4 m だから、もうちょっとステアリングを切った方が良い? いやいや、ステアリングを切りすぎで左後輪前のサイドフェンダーを擦っちゃう???」と、ステアリングの舵角感覚 & 車両左側面の感覚を掴むまでは、ステアリングのカメラスイッチでマルチアラウンドモニター(バードアイビュー機能付)をカーナビゲーションシステムなりに表示させ、安全確認をした方が良さそうだ。1度ばかし、ベタ踏みをしたいがいは、基本的に1,900回転以上エンジンを回すこともなく走行した結果、 マルチインフォメーションディスプレイ上ではこんな感じの数値が表示される。ベタ踏みせず、走行距離も伸ばせば、簡単にもうちょっと数値は上げられそうだ。
マルチインフォメーションディスプレイ上ではこんな感じの数値が表示される。ベタ踏みせず、走行距離も伸ばせば、簡単にもうちょっと数値は上げられそうだ。
とある知人的には、大変好評(但し、後部座席の乗り心地は除く)であったこの新型車。運転した個人的な感想としては……しっくりこない。と、言いうのも、ボディ剛性・足回りのセッティングに加え。軽くアクセルペダルを踏んでいるだけで、法定速度オーバー気味に走行しちゃうところから、クローズドコース・時速 140 ㎞/h ~ 150 ㎞/h 速度域での高速巡航をするような基準で調整をしていると思われ。その想定されている様な走行でもすれば「グイグイいけるSUVですなぁ~」なんて楽しめるのだろうが。あくまで、今回の国道Lvでの運転だけでは、高性能なのは十二分にわかるんだけど……国道Lvでは手に余す感しかない。もうちょっと、ステアリングに手応えがあったり、街乗りLvでも楽しめるセッティングにするとか、セッティングを煮詰めても良いんじゃないかなぁ~なんて思ってしまうも。よくよく考えてみるに、この新型車。本来であれば、DELICA D:5(LDA-CV1W) に搭載している2.2 L DI-D を改良(?)したクリーンディーゼルのエンジンラインナップで国内市場へ投入する予定……だったのだが。色々とやらかした関係で、自動車を製造・販売する上で必要な自動車型式認定の審査がより厳しくされている為、通常より審査時間がかかる事に加え。ハイブリッド車? 笑止。これからの時代は、クリーンディーゼルですよ! クリーンディーゼル!! 最高の環境性能を誇るクリーンディーゼルを造れる技術力は、日の丸メーカーにはあるますまいってな具合に、多くの自動車評論家を始め、ある製造メーカーのクリーンディーゼルがもてはやされていた……そんな時代もあったんですけどね。米国で販売されていたある製造メーカーのクリーンディーゼルの排ガス……台上試験では、基準値を問題なくクリアをしていることはしているんだけど……な~んか釈然としない。でもなぁ~、排ガスを測定器がでかく、台上試験しか測定できない。何処かに、車載することの出来る、そんな都合の良いコンパクトな測定器があったらいいなぁ~……なんてぼやいていたかは定かではないが。その需要にお応えしますと、京都市に本社にある “とある測定器メーカー” が車両に搭載できるサイズの排ガス測定器に開発成功してしまい。実際に路上で走行した際の測定をしたところ……その測定器より「たいそう綺麗な排ガスですねぇ」なんて高評価判定が出たそうな。そんな魔法の言葉でハチャメチャ大混乱! っと、ある製造メーカーのクリーンディーゼルが如何に環境性能に優れている事が明るみになった……とか、ならなかったとか。そんな気に留める程でもない、些細な出来事もあったからかな? クリーンディーゼルに関しては、路上での走行測定をみっちり測定しましょう♪ ってな具合に自動車型式認定の審査がいつ認可されるか目処が立たず……このままだと年度内に発売が危うい!? 然し、もう既に先行して新型車を発売するってアナウンス流し散った……テヘペロ。どないしよっと、トラブルもアクション!? ピンチも勇気のクエストっと、対応策を講じた結果「やせ、ガソリンエンジンなら時短が可能や!(本当は1年遅れで市場投入する予定だった)」ってな大まか事があったのが昨年(17年)の夏頃の話。そういった経緯から察するに、この新型車……製品として販売するには、十分な安全マージンを確保しているので問題はないが。各種のセッティング的な細かな調整に関しては、開発している人達的には、満足いく水準に達する時間が足りなかったのでは? なんて思ってしまう。……そうなると、この新型車。本命は、2.2 L DI-D搭載したモデルであり。ガソリンモデルを購入するにしても、1回~2回のMCを待ってからの方がいいのかもしれない。ただ、昨今のディーゼルエンジンへの逆風を鏡みるに、一部地域の海外市場では市場導入するだろうが。問題の国内市場に関しては……。一応、営業の方に2.2 L DI-D搭載モデルは発売する可能性はありますかねぇ? なる質問を振ってみるも。「どうなんですかね。ディーゼルのイメージが悪くなっていますし、無理じゃないですかね(3月時点)」なんて回答で販売の現場としては、2.2 L DI-D搭載モデルの発売に懐疑的なようだ。それにしても、あれだけある製造メーカーやら、多くの自動車評論家がクリーンディーゼルを絶賛していたのに、手のひらを返したようにディーゼルエンジン = 悪である! 故に、販売しなければいいじゃない的な流れで済ませようとしているのか意味がわからない。ディーゼルエンジンの “善し悪し” の問題でなく。単純に、その販売する地域(国)で定めた “排ガス基準値” に適合してたのディーゼルエンジンを造ればいいだけじゃないの? なんて思ってしまうのは虚けな当方だけか? まぁ、 “排ガス基準” なり “測定の仕方” に問題があるとか、そもそも “排ガス基準” に適合した ディーゼルエンジンを製造した場合、商売にならないっとか、そういった理由があるなら、まだ理解できなくもないにしろ……これからの時代は “EV” ですよ! “EV” !! 今時内燃機関とか……失笑っと、なんだかデジャブな展開から察するに、次もちゃんと落ちなり、手のひらを返しがあるのかな? 乞う御期待!? 兎も角、車検の関係・早急に車が必要になった等の理由が無い限りは、様子見で良いのではないかと思う所存で御座います。
日は巡り、新年度を迎えるにあたりホームセンターへと買い出しへ訪れた日のこと。思いの外、大きな(物理的)買い物をしてしまい、愛車に積載することが出来なひ……。致し方なく、無料貸し出しの軽トラックを借りる流れとなり。ホームセンターより貸し出された軽トラックが、御フランスブランドの日本支部エンブレム車両じゃ~あ~りませんか。このエンブレムって事は、正直で誠実な、まるで生き仏を体現したかのような神々しく後光が……あれ? なんか一部光が切れてない?? ぇ、ただの接続不良だから大丈夫なの??? じゃ~なんの問題はない!! で、お馴染みの国内メーカーさんの軽トラックか。無料で貸し出してくれる車両だし、とっとと輸送しますかと乗員2名 & 荷台に数十㎏の荷物を乗せ。ロープワーク・タイヤの溝に、車両の下をチラッと確認する簡易的な始業点検を済ませた後、走り出して驚愕。やけにエンジンの吹き上がりがよく、加速も申し分ない。なにより、乗り心地がいい!! 正直で誠実な、まるで生き仏……以下略の国内メーカーさんの軽トラックって、こんなに進化していたのかと驚く当方。然し、助手席に座る方は軽トラックに乗車することが初めてだそうで「は? これで乗り心地がいいの?」なんてご褒美……もとい、理解できないと酷評をするが、何もわかっちゃいない!! 軽トラックでこの路面からの入力に対し、衝撃を和らげる乗り心地(座り心地はお察しですよ)が如何に凄いことかを力説するも、助手席に座る方にはかるくスルーされてしまう……グスン。それにしても、明らかに当方が運転したことのある正直で誠実な、まるで生き仏……以下略の国内メーカーさんの軽トラック(といっても、一昔前以上の年式ですけど)とは一線を画してLvが違う。荷下ろしを無事終え、後は1人で返却しに戻るだけとなったところで。興味本位にクローズボックスより、車検証を取り出し確認をしたところ。初度登録は平成24年……ん? って事は、皇紀2672年の西暦で表すところの12年か。あれ、その時期だと確かOEM供給メーカーが変更される前じゃないかと更に読み進めるや、型式がGBD-U71Tと車両型式までは把握していなかったのでわからなかったが。原動機の型式が “3G83” !? 紛うことなき三自がOEM供給していた ミニキャブトラックじゃないか!! 三自純正車であることを認識し、改めて車内を見回してみると……愛車とステアリング・ハザードスイッチが一緒じゃないか! いやはや、気付かないもんだねぇ~。折角だし、返却する前にちょいと走らせてからにするかと、グレード『DX』の2WD(後輪駆動)モデル。3ATのオドメーターは約25,000 ㎞ の車両を運転してみる事に。ドライビングポジションについて、シート調整で前後スライド機能があるのだが、ヘッドレストがリアガラス部分と固定され、
ミニキャブトラックじゃないか!! 三自純正車であることを認識し、改めて車内を見回してみると……愛車とステアリング・ハザードスイッチが一緒じゃないか! いやはや、気付かないもんだねぇ~。折角だし、返却する前にちょいと走らせてからにするかと、グレード『DX』の2WD(後輪駆動)モデル。3ATのオドメーターは約25,000 ㎞ の車両を運転してみる事に。ドライビングポジションについて、シート調整で前後スライド機能があるのだが、ヘッドレストがリアガラス部分と固定され、 シート自体もくたびれた座布団状態がデフォルトなので。まぁ、座り心地にしろ、ドライビングポジション的にも長時間の運転には不向きである。ブレーキペダルを踏み、シフトレバーを『D』にしてからサイドブレーキを下ろしアクセルペダルを軽く踏み込み走り出すや、なんとまぁ~威勢の良いエンジン音を響かせながらのスタートダッシュを決めるんでしょ。時速 30 ㎞/h くらいまであっという間に(軽自動車としては)加速し。そこからやや加速ペースは落ちるものの、時速 50 ㎞/h ~ 60 ㎞/h までもたつきも感じさせることなく、力強い快適な加速をみせる。軽トラック故に、ギア比が低めに設定されている & エンジンも低トルクに振っていることもあり、0スタートからの走り出しが気持ちいいことこの上ない。なにより、この気持ちよさを後押しするのが、吹き上がりの良いエンジン音だ!! 時速にして、40 ㎞/h ~ 50 ㎞/h 程度の速度域というのに、車内に入り込んでくるエンジン音と加速感が相まって、「これぞ内燃機関車を運転している感覚じゃ~」っと、ついついアクセルペダルを深めに踏み込んでしまいたくなる……も、法定速度域を上回らないという素晴らしさ。それにしても、アクセルペダル……あまり踏み込んでいるつもりもないが、思いの外スロットル開度が大きい気がする。前方に車両がいない信号待ちからの0スタートを利用し、ベタ踏み加速とアクセルペダルを底まで踏み込んでみたところ。一般的な軽自動車などと比較して、アクセルペダルの踏み込み幅が約2/3程しかなく。ブレーキペダルも同様に踏み込み幅が短いので、愛車感覚でペダル操作をするとやや強めにアクセル・ブレーキが効いてしまう。最初の数分こそ、踏み込み量のズレに違和感を覚えるも、馴れてしまうと大した踏み込み量もなく。つま先感覚の踏み込み量でアクセル・ブレーキの加減調整が可能となるので、これはこれで法定速度域であれば楽である。助手席に座っていた方的には、酷評をされた乗り心地ですが。荷積みを下ろし、車両総重量が軽くなったことにより、路面からの入力に対してやや跳ねる傾向が見受けられるも足回りで衝撃の大半を受け止め、乗員に伝わる証言をかなり和らげる処理した後、車両を大きめにバウンドさせ直ぐに収まるので、「軽トラックでこんなに快適でいいのだろうか?」なんて思う程だ。ただ、シートがくたびれた座布団Lvな上、車両のボディ剛性も……そんな訳で、いくら足回りが良い仕事をしているとはいえ、限界がある訳でして。軽トラックに乗ったことの無い人からすれば、体感的に直接衝撃が来る感覚は、「なんじゃこれ!?」と酷評されても致し方ない。それでも、当方が運転したことのあるガソリンエンジンの軽トラック(正直で誠実な、まるで生き仏……以下略の一昔前の世代だけど)の乗り心地とは雲泥の差である。ステアリングも適度に手応えで、玩具感覚といったら語弊が生まれるかも知れないが。本当に “気楽に乗り回せるママチャリ感覚” といった具合に一般道から細い抜け道まで、気兼ねなく突っ込んでいけるのはグットですよ。そうこう遊んでいるうちに、天候が変わり俄雨!? 路面が程よく滑りやすくなり。ただでさえ荷台がカラで、後輪のトラクションが低いのに後輪駆動となれば……まぁ~リアタイヤの接地感が心許ないこと心許ないこと。これなら、簡単に
シート自体もくたびれた座布団状態がデフォルトなので。まぁ、座り心地にしろ、ドライビングポジション的にも長時間の運転には不向きである。ブレーキペダルを踏み、シフトレバーを『D』にしてからサイドブレーキを下ろしアクセルペダルを軽く踏み込み走り出すや、なんとまぁ~威勢の良いエンジン音を響かせながらのスタートダッシュを決めるんでしょ。時速 30 ㎞/h くらいまであっという間に(軽自動車としては)加速し。そこからやや加速ペースは落ちるものの、時速 50 ㎞/h ~ 60 ㎞/h までもたつきも感じさせることなく、力強い快適な加速をみせる。軽トラック故に、ギア比が低めに設定されている & エンジンも低トルクに振っていることもあり、0スタートからの走り出しが気持ちいいことこの上ない。なにより、この気持ちよさを後押しするのが、吹き上がりの良いエンジン音だ!! 時速にして、40 ㎞/h ~ 50 ㎞/h 程度の速度域というのに、車内に入り込んでくるエンジン音と加速感が相まって、「これぞ内燃機関車を運転している感覚じゃ~」っと、ついついアクセルペダルを深めに踏み込んでしまいたくなる……も、法定速度域を上回らないという素晴らしさ。それにしても、アクセルペダル……あまり踏み込んでいるつもりもないが、思いの外スロットル開度が大きい気がする。前方に車両がいない信号待ちからの0スタートを利用し、ベタ踏み加速とアクセルペダルを底まで踏み込んでみたところ。一般的な軽自動車などと比較して、アクセルペダルの踏み込み幅が約2/3程しかなく。ブレーキペダルも同様に踏み込み幅が短いので、愛車感覚でペダル操作をするとやや強めにアクセル・ブレーキが効いてしまう。最初の数分こそ、踏み込み量のズレに違和感を覚えるも、馴れてしまうと大した踏み込み量もなく。つま先感覚の踏み込み量でアクセル・ブレーキの加減調整が可能となるので、これはこれで法定速度域であれば楽である。助手席に座っていた方的には、酷評をされた乗り心地ですが。荷積みを下ろし、車両総重量が軽くなったことにより、路面からの入力に対してやや跳ねる傾向が見受けられるも足回りで衝撃の大半を受け止め、乗員に伝わる証言をかなり和らげる処理した後、車両を大きめにバウンドさせ直ぐに収まるので、「軽トラックでこんなに快適でいいのだろうか?」なんて思う程だ。ただ、シートがくたびれた座布団Lvな上、車両のボディ剛性も……そんな訳で、いくら足回りが良い仕事をしているとはいえ、限界がある訳でして。軽トラックに乗ったことの無い人からすれば、体感的に直接衝撃が来る感覚は、「なんじゃこれ!?」と酷評されても致し方ない。それでも、当方が運転したことのあるガソリンエンジンの軽トラック(正直で誠実な、まるで生き仏……以下略の一昔前の世代だけど)の乗り心地とは雲泥の差である。ステアリングも適度に手応えで、玩具感覚といったら語弊が生まれるかも知れないが。本当に “気楽に乗り回せるママチャリ感覚” といった具合に一般道から細い抜け道まで、気兼ねなく突っ込んでいけるのはグットですよ。そうこう遊んでいるうちに、天候が変わり俄雨!? 路面が程よく滑りやすくなり。ただでさえ荷台がカラで、後輪のトラクションが低いのに後輪駆動となれば……まぁ~リアタイヤの接地感が心許ないこと心許ないこと。これなら、簡単にドリフト……もとい、スピンしそうで車両後方の揺れる思いはマシュマロみたいにふわ☆ふわ。慎重に運転することにして。先日試乗した新型車と比べ、比較することすら烏滸がましいまでに車両性能は月と鼈であるが。この運転している楽しさは此方の軽トラックの方が数段上というね。半径数十キロ圏内と、言わば生活圏内の通勤・買い物程度の運転(速度域)では、この軽トラックで十分というか……これでいいんじゃない? なんて思ってしまう程だ。ただ、サイドミラーの幅が小さく、サイドガラスも体の真横でまでのガラス面積がない上に、その後ろはBピラーのボディで完全な死角となる為。車線変更などの左右後方安全確認をしようにも、十分な安全確認が出来ない等の少々軽トラ特有の不便な点もあり。さすがに個人で乗り回すには、荷台がどうしても必要……なんて事がない限りは、“軽バン” をチョイスし、自分好みに室内空間を改造(DIY)するってのが面白そうだ。まぁ、軽トラックを運転する面白さとか、わっかるっかな? わかんねぇだろうなぁ~。そんな事を考えながらうろちょろと走り回っていたら、1h程乗り回していたなんてこともあったりなかったり。
そんな感じで、4月の中旬~5月初旬くらいには書き上げる予定で書き始めているも、クオリティーUpの為という大義名分の元、花粉症というなの持ち前のパッシブスキルで惰眠を貪り早数ヶ月ですよ。その間、空を飛ぶ飛翔体なんて題材の映画が公開されたとかで、これは “応援上映” でもあれば鑑賞しに行こうかと思うも、そういった特別上映回の企画・予定すらないとかね……ガッカリです。だって、作中に描かれる企業・団体の名称はぼかしているものの、誰がどうみても特定の企業・団体であるとわかるように配慮がなされているんですよ? これは劇中に観客が大声で “応援” するしかないじゃないですか! ……ぇ? どんな応援をするって? そりゃ~もう、放送コードがなんぼのもんじゃいって勢いで、怒号・罵詈雑言で特定の企業・団体に向けて応援を浴びせ続けるんですよ。これで劇場にいる観客の一体感と、特定の企業・団体に対する共通の認識を共有できたところで、主演が本業農家のカレーマイスター(?)で、この映画のタイトルとくれば。当然、エンディングロールは「空を飛ぶ~♪ 街が飛ぶ♪ 雲を突き抜け、星になる♪」っと観客全員の大合唱で決まりですよね。劇場を後にする観客は皆一同にスカッとジャパンと晴れ晴れとした表情で帰路につくと。そんな特定の企業・団体故に、許される特別上映回の企画すらしないとか、見識を疑わずにはいられませんよ。それにしても、ネットの掲示板なんかを覗いてみるに「久々の新型車が発売されたタイミングでネガティブキャンペーンとか……」「なんで特定の企業・団体だけ攻められるんだ? 他の企業・団体は?」等々、配給会社の意図がまるで伝わっていないことに誠に残念でなりません。いいですか? 配給会社の筆頭株主に名を連ねる某大手銀行さんが一体何処であるか? その大切なポイントところを理解しないと……。そこから察するに、この特定の企業・団体こそ “戦犯企業” であり、悪しき財閥組織であれは “強制労働問題” があったに違いない!! そう多くの方に思い込んで頂きたいといった意図をちゃんと汲み取ってあげないと……配給会社の筆頭株主に名を連ねる某大手銀行さんが困っちゃいますよ。これから新たなビジネスを世界展開しようと涙ぐましい努力をなさっているんですから。そんな鈍感さが、国内で回転翼軸の角度を変更するティルトローター方式を採用した輸送機を飛行させるなと、キャンドルを掲げて大合唱デモをするも。何故か外国籍の人しか居ない? 内政干渉すんや!! ってなツッコミだけで、ちゃんと自称市民と語る主催者の意図を理解しないことに繋がるんですよ。よ~く考えて下さい。キャンドルと言えば? 勿論、Candle JUNE !! ……そのキャンドルを取っ払い現れる人物名。その人物名を理解した瞬間、つい口遊んでしまいたくなる曲はありませんか? そう、映画撮影で35億円もの借金を背負ったあの方の名曲。其処で初めて、自称市民と語る主催者の背景……もとい、伝えたかった意図がわかるんですよ。正しくメッセージを受け取りましたよっと反応を示す為には、コメントをする際「~なわけで」と語尾に付けないといけないんですよ。これ、特定アジアの常識なわけで。そんな意図を持った自称市民と語る方々が野外ライブと広場に動員した同胞に革命の火を広げるべく、先導し国民感情が一時のテンションに身を任せた結果。国家が転覆した所が……あったような? なかったような……虚けな当方にはよくわからないんですけど。そんな些細なことはさておき、試乗の際に撮影できなかったエクステリア等を撮りに販売店に訪れたところ。丁度納車前の車両が数台程あり。その車両の中に赤系のボディカラーであるレットメタリックがあったので、営業の方に「車体のズームだけ」という条件で撮らせて頂いたのですが。 レッドタイヤモンド(有料色)は “5層構造” の色ベース & クリアコートを重ねているので、パッと見た印象として、車両全体がうっすら青みがかっており。太陽光で直接反射している付近がオレンジ色っぽくも見え、そこから奥へいく都度色合いが段々と変わっていく色彩があるのに対し。レットメタリックは色合いの変化ないのっぺりとした赤色っという印象があるので、直射日光下であればレッドタイヤモンド(有料色)の方が色に深みがありいいなって思うも……。これが日陰や室内照明下では見分けるのが難しく。営業の方ですらどっちがどっちかわからないそうで、接客で「此方が有料色の~」って説明していたら実はレットメタリックだった……なんて失敗談があるとか。この違いがわかる人にしかわからないけど、その違いにこそ価値を見いだすか否かって所なんでしょう。然しながら、やっぱり直射日光下で見るとレッドタイヤモンド(有料色)の方がえぇ~なぁ~なんて眺めて居たところ。営業の方より「実は、4月の生産分からレッドタイヤモンド(有料色)の1層が無くなり。“4層構造” になるんですよ」とこっそり教えて頂く。なぬ!? あれだけ “5層構造” を実現する為に苦難したとか言っていたのに。速攻で製造コストの削減? 或いは、想定していた発注数を上回る需要に対応すべく、1層減らしレッドタイヤモンド(有料色)の月生産枠を増やしたのかな? 何にしても、 “5層構造” が実は “4層構造” になっていただなんて隠蔽だ~っと、服従すべき既存メディアであれは事実確認する必要もなく、大はしゃぎをすればいいだけなのですが。愚民Lvの虚けな当方、公式HPに確認してみようと訪れてみるや。そこには “6月生産分より” との記載を発見。ありゃ? 2ヶ月の誤差があるぞ? 考察してみるに、販売店の試乗車であるレッドタイヤモンド(有料色)が製造ラインを流れた日付が3月の○日。恐らく、先行販売予約分も含め、3月生産分のレッドタイヤモンド(有料色)の生産枠を国内出荷分に確保したので、4月~5月の月生産枠は海外出荷分に全フリ。次の国内出荷分としては “6月生産分” からになりますって事かな? まぁ、何にしても6月以降のレッドタイヤモンド(有料色)については “4層構造” なので、それ以前のレッドタイヤモンド(有料色)と見比べると、違いがわかる……かもしれない。
レッドタイヤモンド(有料色)は “5層構造” の色ベース & クリアコートを重ねているので、パッと見た印象として、車両全体がうっすら青みがかっており。太陽光で直接反射している付近がオレンジ色っぽくも見え、そこから奥へいく都度色合いが段々と変わっていく色彩があるのに対し。レットメタリックは色合いの変化ないのっぺりとした赤色っという印象があるので、直射日光下であればレッドタイヤモンド(有料色)の方が色に深みがありいいなって思うも……。これが日陰や室内照明下では見分けるのが難しく。営業の方ですらどっちがどっちかわからないそうで、接客で「此方が有料色の~」って説明していたら実はレットメタリックだった……なんて失敗談があるとか。この違いがわかる人にしかわからないけど、その違いにこそ価値を見いだすか否かって所なんでしょう。然しながら、やっぱり直射日光下で見るとレッドタイヤモンド(有料色)の方がえぇ~なぁ~なんて眺めて居たところ。営業の方より「実は、4月の生産分からレッドタイヤモンド(有料色)の1層が無くなり。“4層構造” になるんですよ」とこっそり教えて頂く。なぬ!? あれだけ “5層構造” を実現する為に苦難したとか言っていたのに。速攻で製造コストの削減? 或いは、想定していた発注数を上回る需要に対応すべく、1層減らしレッドタイヤモンド(有料色)の月生産枠を増やしたのかな? 何にしても、 “5層構造” が実は “4層構造” になっていただなんて隠蔽だ~っと、服従すべき既存メディアであれは事実確認する必要もなく、大はしゃぎをすればいいだけなのですが。愚民Lvの虚けな当方、公式HPに確認してみようと訪れてみるや。そこには “6月生産分より” との記載を発見。ありゃ? 2ヶ月の誤差があるぞ? 考察してみるに、販売店の試乗車であるレッドタイヤモンド(有料色)が製造ラインを流れた日付が3月の○日。恐らく、先行販売予約分も含め、3月生産分のレッドタイヤモンド(有料色)の生産枠を国内出荷分に確保したので、4月~5月の月生産枠は海外出荷分に全フリ。次の国内出荷分としては “6月生産分” からになりますって事かな? まぁ、何にしても6月以降のレッドタイヤモンド(有料色)については “4層構造” なので、それ以前のレッドタイヤモンド(有料色)と見比べると、違いがわかる……かもしれない。
それから数週間後、ちょいとした所要で販売店の前を通りかかった際。整備工場に駐まる新型車が目界に入る。時期的に先行販売予約で購入したオーナーさんの1ヶ月点検かなぁ~なんて眺めるも、どうにもリアハッチがのっぺりしているではないか!? ありゃ~オカマ掘られたっぽい。納車から1ヶ月も経たずとか……不憫すぎ。それにしてもリアガラスは割れていないし、破損具合から察するに、ミニバン・バン辺りのフロントパンパーがのっぺりとした車両にやられたんだろうなぁ~なんて思いつつ。後日販売店に訪れた際、雑談の中で「整備工場に駐まっていた新型車両が~」なる話を振ったところ。「見ちゃいました? いや~20㌧ダンプに追突されちゃったんですよ」と営業の方がさらりと返答するのだが……ん? ちょっとまて。 20㌧ダンプって、あの砂利やら土を積載する20㌧ダンプ!? 破損具合から、ちょっと乗用車クラスにこつ~んとやられちゃいました♪ Lvかと思ったら、大型車……しかも重量級の
20㌧ダンプって、あの砂利やら土を積載する20㌧ダンプ!? 破損具合から、ちょっと乗用車クラスにこつ~んとやられちゃいました♪ Lvかと思ったら、大型車……しかも重量級の悪質タックル……もとい、車両総重量を遙かに凌ぐ20㌧ダンプに追突されて荷積み空間すら潰れないって、 どんだけ強固なボディなんだよ!! まぁ、それ程追突時の車速は出てはいなかったんだろうが……この安全性は、もっと強く謳った方がいいんのでは。また、営業の方にこっそり教えて貰った情報で、5月下旬頃よりこの新型の衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]の誤作動をするというクレーム(数件)が突然入る様になったとか。なんでも、17年式 OUTLANDER系で採用している安全装置とは違う部品をこの新型車から採用するも、制御ブログラムは基本的に同じなので、もしかするとその部品の仕様による違い? が誤作動となっている可能性が……あるとかないとか。ただ、誤作動報告エリアが極めて限定されている大通りので、その限定されたエリア(付近の地形・強力な電波を発信している)の状況か? 将又、衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]のカメラ & センサーが過敏に反応しすぎた所為なのか? 現在(6月時点)三自・サプライヤーメーカーが原因調査・分析をしているそうな。
どんだけ強固なボディなんだよ!! まぁ、それ程追突時の車速は出てはいなかったんだろうが……この安全性は、もっと強く謳った方がいいんのでは。また、営業の方にこっそり教えて貰った情報で、5月下旬頃よりこの新型の衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]の誤作動をするというクレーム(数件)が突然入る様になったとか。なんでも、17年式 OUTLANDER系で採用している安全装置とは違う部品をこの新型車から採用するも、制御ブログラムは基本的に同じなので、もしかするとその部品の仕様による違い? が誤作動となっている可能性が……あるとかないとか。ただ、誤作動報告エリアが極めて限定されている大通りので、その限定されたエリア(付近の地形・強力な電波を発信している)の状況か? 将又、衝突被害軽減ブレーキシステム[FCM]のカメラ & センサーが過敏に反応しすぎた所為なのか? 現在(6月時点)三自・サプライヤーメーカーが原因調査・分析をしているそうな。
さて、うだうだと時間が経過している間にとある知り合いとは別の知り合いがこの新型車を購入したそうで、運転させて頂ける事に。車両はG PLUS PACKAGE 4WD(メーカーオプション:7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS] (Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステム)・電動パノラマサンルーフ)のタイヤは標準装備(TOYO PROXES R44 225/55R18 98H)でオドメーターは約1,500 ㎞。試乗環境 → 2人乗車。AUTOエアコン → 24.0 ℃ 設定。S-AWCドライブモード → AUTO。試乗コースでは走れない生活道路やら、ワインディングロードを走らせてたく。サクッと試乗車と同じドライビングポジションに調整し、出発してみる。試乗車では、軽やかな走り出し~ってな印象であったが。此方の車両では、加速感が1割減!? あれ? ECOモードに入っているのかとマルチインフォメーションディスプレイを確認するも、ECOの表示はされてはいない。エンジンがまだ温まっていない状態? かと一瞬疑うも、既に水温計は十分に温まっている。後考えられる原因とすれば、試乗車と所詮は他人様の車。試乗した来店客がガンガンにアクセルペダル踏みまくるぜい♪ っと、荒い運転をしたのをCVT学習機能が適応していたから? 将又、メーカーオプション装備有無による車両総重量の差??? なんにしても、このもっさり感はないわぁ~。爽快な走り出しを知っているが故に、どうにも気になってしまう当方。ガソリンメーターが残り2目盛しかなかったので、オーナーである知り合いの方に承諾を得て、ハイオク(ヴィーゴ)をどぶどぶっと注ぎ込む。“レギュラー仕様” の車両にハイオク? 違いがある訳……ホンマヤ!? っと、助手席に座る知り合いの方にも体感できる程、走り出しのもたつきがやや緩和(試乗車程には至らず)した。やはり、この新型車。国内では “レギュラー仕様” と販売してはいるが、海外販売車両も同じ工場ライン生産で製造しているんだから。当然エンジンマッピングも同じであると想定するに、レギュラーガソリンでも問題なく走行することは可能だけれど、海外市場でのレギュラーガソリンオクタン価水準であるハイオクの方がこの新型車には良いのかもしれない。ようやくもたつきを然程気にせず走り出しが可能となったところで。まずは生活道路と普段抜け道に使っているところを走行したところ、アクセルペダルをちょいと踏みだけで元気よく加速しちゃうこの新型車では、意識的に控えめな運転を心がけんと、生活道路ではアカンなぁ~。そんなことを思いながら走行しているや、生活道路というのにぶっ飛ばしてくるミニバンが!! 急ブレーキとステアリングを即座に切り、道の端に車両を寄せつつ “完全停車” をして相手の車両が通過するのを待つ。いやはや、生き急ぐのは勝手だが、人様を巻き込むのは如何なものかと……ぼやきたくなるのをグッと抑え。再び走り出すべく、アクセルペダルを踏み込んだところ、突然車両が意図しない急加速をする。慌ててアクセルペダルを外す当方。なして、いきなり元気よく加速するんだと、今度は周囲の安全確認をしてから先程の同じ感覚でアクセルペダル踏んでみる。すると、車速が時速 20 ㎞/h を超えるまでは低速ギアで引っ張るぜい! っと、CVT制御をするようで。アクセルペダルをそこまで深く踏んでいるつもりはないのに、スタートダッシュを決めるかのように走り出してしまう。これは停車から再発進的な、そんな時だけかと意識しながら運転してみたところ、どうやら信号待ち等の完全停車からある程度の間隔を開けてからの0スタートする際には、そこまで低速ギアで引っ張る制御はしないが。交差点の右左折など、巡航速度からブレーキで徐行速度までの減速し、再度加速する。又は、停車して直ぐに走り出すような場面になると、何故か車速が時速 20 ㎞/h を超えるまでは低速ギアで行くぜ!! と、上記に書いた通りのエンジン回転数を引っ張るCVT制御をするので、一刻も早く車速上げたい! ってな走行シーンなら兎も角。生活道路なんかのそこまで加速力は必要としていない……とか。エンジン回転数を引っ張ることで、突然エンジン音が賑やかしくなるのはちょっと……なんて思うドライバーにとっては、正直厄介なCVT制御である。そんな訳で、時速 20 ㎞/h 以下まで落としてからの再加速をする際は、あまりアクセルペダルを踏まないように意識する必要があるのだが……面倒い。そこで、色々と四苦八苦した結果。シフトレバーの『D』制御にがいけないんだと、パドルシフトでスポーツモードへ事前に移行してしまい。任意で2速 ~ 3速で引っ張り気味に走りたいか? いやいや、4速 ~ 5速とギア数を上げていき、エンジン回転数を上げずに~っと、自分で調整した方がよさげ。次に大通りへ移り『D』で走行してみる。走り出しにエンジン回転数が1,900回転 ~ 2,100回転とエンジンを然程回すことなく時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h 辺りを超えたところで、ギア比を上げていくようで、エンジン回転数が1,200回転 ~1,400回転で落ちる頃には法定速度近くまで車速が達している訳だが。このCVT、何故か一定速度以上のギア比的にある程度上がり始めた段階からトルクコンバータが上乗せされたかのようにトルク量が変化し、エンジン回転数が1,200回転 ~1,400回転とエンジン回転数が変わっていないのに突然トルク量が体感的に1割程度盛られ始めるので、それまでのアクセルペダルと同じ踏み加減で運転していても、気が付くとスーっと車速が伸びるように加速をしてしまう為、巡航速度まで車速をもっていったら気持ちアクセルペダルを緩めるくらいな踏み加減がいるようだ。CVT制御の開発者の意図としては、巡航速度域からの再加速とか、どの速度域からも某髭のカート的表現として “ダッシュキノコ” を使用した様なスタートダッシュが出来るようにってCVT制御にしたかったのかな? 個人的には、車速が上がってからのトルクコンバータが上乗せされたかのようにトルク量が変化するような制御をするのであれば、0スタート時から効かせて貰った方がリニアで扱いやすいのに……なんて思ってしまう。然し、あくまで個人的勝手な推察ですよぉ~っと前置きをしつつ、この新型車は元々 “DI-D” で発売する予定だった。だが、すったもんだでガソリンエンジンモデルを急遽発売することになり、自慢の新型エンジンとはいっても、世間的に1.5 L ……排気量的に大丈夫なん? と懐疑的に思われるであろう。其処で、 自社製の自然吸気2.4 L(4B12・4J12)ガソリンエンジンよりもトルクが豊かであり。何より、
自社製の自然吸気2.4 L(4B12・4J12)ガソリンエンジンよりもトルクが豊かであり。何より、 45度の登坂を登り切る視覚的パフォーマンスをする為、低速域ではトルクコンバータの様な制御を敢えてなくし。CVTに高負荷のかかるような運転をしたとしても、問題のないようにしたのでは……。“DI-D” モデルが仮に発売されたとして、45度の登坂イベントで “DI-D” モデルを使用するようになれば、CVT制御は変わる? 可能性が……まぁ、あくまで個人的憶測ですけどね。それにしても、この新型車は街中を運転していて視界が良いね! ドライビングポジションの関係で、ちょっと視線を斜め上にずらすだけで、ルームミラーで上下2段リアウインドウと後方視界が良いことに加え、フロントドアガラスからリアドアガラスまで、広く確保され。サイドミラーの面積も大きいとくるので、右左折・車線変更時の巻き込み確認・安全確認の際の視野範囲がグッとですよ。軽トラックを運転した後では、なおのこと。また、取扱説明書を一通り目を通してもみるも、記載は見当たらないのですが。左折信号待ちをしている際。ごく稀に、車両の横をすり抜け路肩から接近してくる自転車・自動二輪に後側方車両検知警報システム(レーンチェンジアシスト機能付)[BSW/LCA]のセンサーが反応し、サイドミラー鏡面の警告灯が点灯することがある。“巻き込み防止装置” としての機能もある??? ただ、すり抜け様とする自転車・自動二輪からしてみれば、突然目の前のサイドミラー鏡面の警告灯が点灯するのに驚くのか、警戒してすり抜けるのをやめる行動が見受けられた。これ、路線バスの左リアに “すり抜け危険ステッカー” を貼り注意喚起するよりも。すり抜け様とする自転車・自動二輪が接近した所で警告と “星マーク” でも点灯すれば、かなりの注意喚起になるような……。それはさておき、視界面での良さ以上に驚いたのが乗り心地だ! 試乗した車両では、綺麗に舗装された路面では然程気にはならなかったが。荒れた路面を走行するや、↖、↗軸に跳ねる挙動が~なんて書き連ねていたのだが。此方の車両を運転する限りで、荒れた路面やら、段差を超える所を通過しようとも、↖、↗軸に跳ねる挙動が一切なくなっている……だと!? 路面からの入力に対し、衝撃を足回り・ボディ全体で受け止め、かなり和らげながらも車体のバウンドピッチは早めに1回~2回程度で車体はビシッとバウンドが収まるので、なかなかにスポーティーなセッティングにしているはずなのに……SPORTSタイヤからプレミアムコンフォートタイヤへ履き替えた以上のコンフォートさが此方の車両にはある。なして、こんな飛躍的に乗り心地が良くなっているんだと分析するに、試乗車両には装着されていなかった “メーカーオプション” による差なんじゃないかと推測。もしかすると、この新型車……車両総重量が爽快性(加速感) & 快適性(乗り心地)を大きく左右するんじゃないか? そんな事を考えながら、偶に遊びに行っているワインディングロード(以前Let’s PHEVで借りた15年式で走行した所)を走らせてみる。1.5 L ガソリンエンジンと、自社製2.4 L ガソリンエンジンを凌ぐトルク性能が低回転域からある……とはいっても、さすがに登坂車線での0スタートでは、エンジン回転数を2,300回転域までアクセルペダルを踏み込まないと走り出しは厳しいものの、一旦時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h を超えれば、上記にも記載しての通りトルクコンバータが上乗せされる領域に入るので。エンジン回転数が1,500回転付近まで落ちようとも、登坂車線でグイグイ加速していきアクセルペダルの踏みの踏み加減を殆ど変えることなく、起伏があろうとも法定速度を維持することが出来る。また、DELICA D:5・GALANT FORTIS等で採用されている電子制御4WDでは、どうしてもインへ切り込んでいく限界があるのだが。この新型車では、
45度の登坂を登り切る視覚的パフォーマンスをする為、低速域ではトルクコンバータの様な制御を敢えてなくし。CVTに高負荷のかかるような運転をしたとしても、問題のないようにしたのでは……。“DI-D” モデルが仮に発売されたとして、45度の登坂イベントで “DI-D” モデルを使用するようになれば、CVT制御は変わる? 可能性が……まぁ、あくまで個人的憶測ですけどね。それにしても、この新型車は街中を運転していて視界が良いね! ドライビングポジションの関係で、ちょっと視線を斜め上にずらすだけで、ルームミラーで上下2段リアウインドウと後方視界が良いことに加え、フロントドアガラスからリアドアガラスまで、広く確保され。サイドミラーの面積も大きいとくるので、右左折・車線変更時の巻き込み確認・安全確認の際の視野範囲がグッとですよ。軽トラックを運転した後では、なおのこと。また、取扱説明書を一通り目を通してもみるも、記載は見当たらないのですが。左折信号待ちをしている際。ごく稀に、車両の横をすり抜け路肩から接近してくる自転車・自動二輪に後側方車両検知警報システム(レーンチェンジアシスト機能付)[BSW/LCA]のセンサーが反応し、サイドミラー鏡面の警告灯が点灯することがある。“巻き込み防止装置” としての機能もある??? ただ、すり抜け様とする自転車・自動二輪からしてみれば、突然目の前のサイドミラー鏡面の警告灯が点灯するのに驚くのか、警戒してすり抜けるのをやめる行動が見受けられた。これ、路線バスの左リアに “すり抜け危険ステッカー” を貼り注意喚起するよりも。すり抜け様とする自転車・自動二輪が接近した所で警告と “星マーク” でも点灯すれば、かなりの注意喚起になるような……。それはさておき、視界面での良さ以上に驚いたのが乗り心地だ! 試乗した車両では、綺麗に舗装された路面では然程気にはならなかったが。荒れた路面を走行するや、↖、↗軸に跳ねる挙動が~なんて書き連ねていたのだが。此方の車両を運転する限りで、荒れた路面やら、段差を超える所を通過しようとも、↖、↗軸に跳ねる挙動が一切なくなっている……だと!? 路面からの入力に対し、衝撃を足回り・ボディ全体で受け止め、かなり和らげながらも車体のバウンドピッチは早めに1回~2回程度で車体はビシッとバウンドが収まるので、なかなかにスポーティーなセッティングにしているはずなのに……SPORTSタイヤからプレミアムコンフォートタイヤへ履き替えた以上のコンフォートさが此方の車両にはある。なして、こんな飛躍的に乗り心地が良くなっているんだと分析するに、試乗車両には装着されていなかった “メーカーオプション” による差なんじゃないかと推測。もしかすると、この新型車……車両総重量が爽快性(加速感) & 快適性(乗り心地)を大きく左右するんじゃないか? そんな事を考えながら、偶に遊びに行っているワインディングロード(以前Let’s PHEVで借りた15年式で走行した所)を走らせてみる。1.5 L ガソリンエンジンと、自社製2.4 L ガソリンエンジンを凌ぐトルク性能が低回転域からある……とはいっても、さすがに登坂車線での0スタートでは、エンジン回転数を2,300回転域までアクセルペダルを踏み込まないと走り出しは厳しいものの、一旦時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h を超えれば、上記にも記載しての通りトルクコンバータが上乗せされる領域に入るので。エンジン回転数が1,500回転付近まで落ちようとも、登坂車線でグイグイ加速していきアクセルペダルの踏みの踏み加減を殆ど変えることなく、起伏があろうとも法定速度を維持することが出来る。また、DELICA D:5・GALANT FORTIS等で採用されている電子制御4WDでは、どうしてもインへ切り込んでいく限界があるのだが。この新型車では、菊五郎偉い! ……もとい、S-AWCこと “スーパーオールホイールコンチョロォォル” もう、覚えてくれたかな? 発音が大切なんですYO!! ……は、さておき。その “スーパーオールホイールコンチョロォォル” の御陰で、うねる道に差し掛かるや、ステアリングが軽いことも相まって、恐ろしいまでに曲がるわ、ライントレース性抜群だわで、面白いのなんの。ただ、電動パノラマサンルーフ装着車な為、天井+ 30 ㎏ 増と重心が上がってしまっているので、ややきつめのカーブでステアリングを素早く切るや、車体が僅かにロールをしてしまうので「やっぱりPHEVの様な安定感はないかぁ」っと一瞬ゲンナリしてしまう……も。よくよく考えるに、この車両はSUVで天井が+ 30 ㎏ 増の重心高的にも電池を腹に抱えているPHEVは勿論。セダン・コンパクトカーといった車両タイプからしても、ロールに対してかなり不利なはずなのに、僅かにロールLvって……どんだけスゲぇ~んだよ。ここで初めて、試乗車で感じた↖、↗軸に跳ねる挙動の意味……それは、コーナリング時の対ロールの為なんだと理解する。すると、この新型車の足回りをセッティングした人って、電動パノラマサンルーフ装着(30 ㎏ 増)する前提の足回りで調整したんじゃないか? そんな風に思えてならない。下り坂ポイントになったところで、パドルシフトでエンジンブレーキを駆使しながら下っていく。基本的に4速 ~ 2速を先行車との車間距離を考慮しつつパドルシフトでエンジンブレーキ力を調整するのだが、全体的にもうちょっとエンジンブレーキが強めに効くギア比設定にしてもいいんじゃないかと思ってしまうのだが。 この新型車の2速 ~ 4速の変速比を確認してみると、RVR(DBA-GA4W)・OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W)よりも変速比は高く設定しているので、エンジンブレーキとしてはやや強めになるはずなのだが……憶測ではあるが、減速エネルギーで発電する回生ブレーキとの兼ね合いがしっくりきていないのかな??? そんなことを考えながら走行していると、通り雨が!! 良い具合に滑りやすい路面状況になり、本来であればスリップに備えて~なんてカーブ時の減速タイミングを早めたり等、色々と気を遣う必要がある訳ですが……いやはや、S-AWCこと “スーパーオールホイールコンチョロォォル” で走行(AUTOモード)している御陰で、路面の “摩擦係数μ” が低下し、路面との接地感だとか、カーブ時でもラインが膨らんじゃう~なんてこともなく。寧ろ乾燥路面を走行時以上に四輪で路面をがっしり踏みしめるぜい!! っと、体感できる程に “摩擦係数μ” が低下した下り坂なのに運転している安心感が半端じゃない!!! ちょっと前に、同じような走行環境での軽トラック(空荷)走行と比較すると、もう異次元の世界エルハザードですよ。しかも、ワイパー動作音が静かとくる。雨天走行の文明開化じゃ~って具合にテンション⤴⤴。ちょっと遠乗りしたついでにと、今度は高速道路も走ってみようとなり、折角だからとレーダークルーズコントロールシステム[ACC]を使い走行してみる。設定車速は制限速度より+10 ㎞/h にし、車間設定は3に設定して運送トラックに追従していると、さすがプロのドライバーといいますか、速度抑制装置が装着されているだけあり。きっちり制限速度±5 ㎞/h で走行するので、まぁ快適に先行車追従機能が働き。エンジン回転数が1,500回転 ~ 1,800回転で辺りで巡航。すると、生活道路~ワインディングロードを走行している際のマルチインフォメーションディスプレイ上平均燃費表示が7 ㎞/L ~9 ㎞/L だったのが、みるみる数字が上がり。当方が確認した限りでは最高16 ㎞/L と表記が!! こりゃ~運送トラックを風切り & ペースメーカー車として追従し続ければ、かなりの平均燃費になりそうと思っていたところで、敢え無く運送トラックが高速を降りてしまう。その先の合流ポイントより本線へと入ってきた次なる先行車こと、コンパクトカーが休日ドライバー? なのか。合流段階からなかなか加速せず。巡航速度も時速 70 ㎞/h で永遠と数キロ走っていたかと思えば、突然加速し始め時速 100 ㎞/h まで行くと、慌ててブレーキランプを光らせ減速という……まぁ、事故誘発運転を繰り広げる訳ですが。此方はレーダークルーズコントロールシステム[ACC]で勝手に速度の加減速するからどうでもいいかと、暫く休日ドライバー? のコンパクトカーにお付き合いすることに。すると、先行車追従機能の未熟さが露呈し始める。以前Let’s PHEV(15年式)で試したレーダークルーズコントロールシステム[ACC]と同様にセンサーで先行車との車間距離設定基準でしか速度コントロールが出来ない様で。先行車が突然加速し、車間が開き始めてから約2秒くらいの間隔を置いてから設定車速まで加速をし先行車を追いかけ始めるも。先行車は例の如くブレーキで減速をするもんだから、レーダークルーズコントロールシステム[ACC]としては突然先行車との車間距離・速度差が急激に変化するので、此方の車両も強めのブレーキが掛けるという追従走行を繰り返す。ある程度のドライバーであれば、そんな巡航速度も定まらないトーシロー先行車両であると悟れば、先行車との車間距離感覚だけではなく、先行車が加速しても、此方は徐々に車速を上げ。十分な車間距離が確保されているので、先行車がブレーキ or アクセルオフ等で突然の失速をしても、此方はアクセルオフのエンジンブレーキだけで減速と、そんな車速の調整でブレーキペダルを踏むことなく、のんびり追従~っとしていくものなのだが……まだまだレーダークルーズコントロールシステム[ACC]がフロントバンパーに設置されているセンサーで判定しているが故に、先行車の技量・車列の流れ・道路状況など、総合的な判断材料を元に制御……とはいかないようだ。レーダークルーズコントロールシステム[ACC]も大体理解できたところで、休日ドライバー? さんの御役御免と、先行車との車間距離が開いたタイミングを見計らい、サイドミラーで追越し車線を連なって走行していく車両の最後尾車両と列んだタイミングでアクセルペダルを踏み込み、追越し車線へレーンチェンジ。エンジン回転数を2,500回転辺りまでちょいと上げるだけで、軽く時速 80 ㎞/h台 から100 ㎞/h 台へと車速を乗せることが出来、巡航速度からの加速性能もなかなかに良いようだ。然し、驚いたのがレーンチェンジの際、ステアリングを切り始めた瞬間……それまで軽々とスルスル操舵できていた軽いステアリングは何処へ? 突如としてずっしりとした重いステアリングになっているんですよ。なんじゃ~こりゃっと、一瞬焦ってしまう当方。どうやら、このステアリングは速度感応式パワーステアリングの様で、高速道路を降りた後も意識してステアリング操舵をしたところ。時速 30 ㎞/h ごとに徐々にステアリングの重さを上げていっているようで(感覚的に)、時速 90 ㎞/h 辺りを境にステアリングの重さががらりと重めになる設定にしているようだ。そんな訳で、法定速度域で運転している感覚と高速走行をしている際のステアリング感覚は違うと理解していた方がいいようです。小さくステアリングを左右に数回切り、大体の重さ感覚を理解できれば指して気にする程の重さでもないのだが。問題は
この新型車の2速 ~ 4速の変速比を確認してみると、RVR(DBA-GA4W)・OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W)よりも変速比は高く設定しているので、エンジンブレーキとしてはやや強めになるはずなのだが……憶測ではあるが、減速エネルギーで発電する回生ブレーキとの兼ね合いがしっくりきていないのかな??? そんなことを考えながら走行していると、通り雨が!! 良い具合に滑りやすい路面状況になり、本来であればスリップに備えて~なんてカーブ時の減速タイミングを早めたり等、色々と気を遣う必要がある訳ですが……いやはや、S-AWCこと “スーパーオールホイールコンチョロォォル” で走行(AUTOモード)している御陰で、路面の “摩擦係数μ” が低下し、路面との接地感だとか、カーブ時でもラインが膨らんじゃう~なんてこともなく。寧ろ乾燥路面を走行時以上に四輪で路面をがっしり踏みしめるぜい!! っと、体感できる程に “摩擦係数μ” が低下した下り坂なのに運転している安心感が半端じゃない!!! ちょっと前に、同じような走行環境での軽トラック(空荷)走行と比較すると、もう異次元の世界エルハザードですよ。しかも、ワイパー動作音が静かとくる。雨天走行の文明開化じゃ~って具合にテンション⤴⤴。ちょっと遠乗りしたついでにと、今度は高速道路も走ってみようとなり、折角だからとレーダークルーズコントロールシステム[ACC]を使い走行してみる。設定車速は制限速度より+10 ㎞/h にし、車間設定は3に設定して運送トラックに追従していると、さすがプロのドライバーといいますか、速度抑制装置が装着されているだけあり。きっちり制限速度±5 ㎞/h で走行するので、まぁ快適に先行車追従機能が働き。エンジン回転数が1,500回転 ~ 1,800回転で辺りで巡航。すると、生活道路~ワインディングロードを走行している際のマルチインフォメーションディスプレイ上平均燃費表示が7 ㎞/L ~9 ㎞/L だったのが、みるみる数字が上がり。当方が確認した限りでは最高16 ㎞/L と表記が!! こりゃ~運送トラックを風切り & ペースメーカー車として追従し続ければ、かなりの平均燃費になりそうと思っていたところで、敢え無く運送トラックが高速を降りてしまう。その先の合流ポイントより本線へと入ってきた次なる先行車こと、コンパクトカーが休日ドライバー? なのか。合流段階からなかなか加速せず。巡航速度も時速 70 ㎞/h で永遠と数キロ走っていたかと思えば、突然加速し始め時速 100 ㎞/h まで行くと、慌ててブレーキランプを光らせ減速という……まぁ、事故誘発運転を繰り広げる訳ですが。此方はレーダークルーズコントロールシステム[ACC]で勝手に速度の加減速するからどうでもいいかと、暫く休日ドライバー? のコンパクトカーにお付き合いすることに。すると、先行車追従機能の未熟さが露呈し始める。以前Let’s PHEV(15年式)で試したレーダークルーズコントロールシステム[ACC]と同様にセンサーで先行車との車間距離設定基準でしか速度コントロールが出来ない様で。先行車が突然加速し、車間が開き始めてから約2秒くらいの間隔を置いてから設定車速まで加速をし先行車を追いかけ始めるも。先行車は例の如くブレーキで減速をするもんだから、レーダークルーズコントロールシステム[ACC]としては突然先行車との車間距離・速度差が急激に変化するので、此方の車両も強めのブレーキが掛けるという追従走行を繰り返す。ある程度のドライバーであれば、そんな巡航速度も定まらないトーシロー先行車両であると悟れば、先行車との車間距離感覚だけではなく、先行車が加速しても、此方は徐々に車速を上げ。十分な車間距離が確保されているので、先行車がブレーキ or アクセルオフ等で突然の失速をしても、此方はアクセルオフのエンジンブレーキだけで減速と、そんな車速の調整でブレーキペダルを踏むことなく、のんびり追従~っとしていくものなのだが……まだまだレーダークルーズコントロールシステム[ACC]がフロントバンパーに設置されているセンサーで判定しているが故に、先行車の技量・車列の流れ・道路状況など、総合的な判断材料を元に制御……とはいかないようだ。レーダークルーズコントロールシステム[ACC]も大体理解できたところで、休日ドライバー? さんの御役御免と、先行車との車間距離が開いたタイミングを見計らい、サイドミラーで追越し車線を連なって走行していく車両の最後尾車両と列んだタイミングでアクセルペダルを踏み込み、追越し車線へレーンチェンジ。エンジン回転数を2,500回転辺りまでちょいと上げるだけで、軽く時速 80 ㎞/h台 から100 ㎞/h 台へと車速を乗せることが出来、巡航速度からの加速性能もなかなかに良いようだ。然し、驚いたのがレーンチェンジの際、ステアリングを切り始めた瞬間……それまで軽々とスルスル操舵できていた軽いステアリングは何処へ? 突如としてずっしりとした重いステアリングになっているんですよ。なんじゃ~こりゃっと、一瞬焦ってしまう当方。どうやら、このステアリングは速度感応式パワーステアリングの様で、高速道路を降りた後も意識してステアリング操舵をしたところ。時速 30 ㎞/h ごとに徐々にステアリングの重さを上げていっているようで(感覚的に)、時速 90 ㎞/h 辺りを境にステアリングの重さががらりと重めになる設定にしているようだ。そんな訳で、法定速度域で運転している感覚と高速走行をしている際のステアリング感覚は違うと理解していた方がいいようです。小さくステアリングを左右に数回切り、大体の重さ感覚を理解できれば指して気にする程の重さでもないのだが。問題は90歳を行ったり来たり……もとい、時速 80 ㎞/h ~ 90 ㎞/h 付近を行ったり来たりするような走行状態に遭遇するや、ステアリングの操舵感覚がおかしな事に……。丁度ステアリングの重さセッティングの変わり目となる速度域なので、時速 80 ㎞/h ~ 90 ㎞/h で行ったり来たりされると、まぁ車線維持程度のステアリング補正操舵ですらイライラしてきますよ。もうちょっと、ここら辺のステアリングの重さの変化を緩やかにするか。もしくは “車線逸脱防止支援システム” で高速走行をサポートしまっせ♪ なんて機能でもあれば、この速度域での不満も大分緩和されると思うんですけどね。とりあえず、この追越し車線の車列の波に乗っかっていくかと、エンジン回転数が2,300回転辺りで巡航しているとマルチインフォメーションディスプレイ上平均燃費表示が12 ㎞/L と一気に下がったので、燃費的な事を考えるとターボのかからないエンジン回転数(2,000回転以下)での巡航キープが鍵となるようだ。とはいえ、車速を上げていき時速 120 ㎞/h付近に差し掛かるも、運転している感覚として時速 80 ㎞/h で走行している感覚(ステアリングの重さは違うけど)と殆ど変わらないず。寧ろ、丁度いい具合に走ってんな~くらいの感覚で、個人的には、さらの車速を上げて~っと、アクセルペダルを踏み込みたい気持ちは無きにしも非ずなんですが……さすがに隣に座る知り合いのお車ですからね……断念することにして。やはり、僅かではあるが試乗車を運転した際に感じた、“クローズドコース・時速 140 ㎞/h ~ 150 ㎞/h 速度域” をする時にバッチリ合うようなセッティングにしてあるようで、法定速度域だけでは「ん~悪くはないんだけどね。こう……しっこりこないんだよね」なんて印象が一変する。この新型車……試乗コースでちょっと一回りなんてLvじゃなく、レンタカーなりでガッツリうん百キロ走り込む! くらいの勢いで運転しないと、本当の意味での良さを理解することは出来んな。これで一通り生活道路~高速道路も走れたし、後は流して行こうと高速道路の料金所を通過したタイミングで “ECOモード” に入れたところ、驚きの変化が!! なんと、ステアリング・アンセルペダル・ブレーキペダルが “気持ち” 重たくなる……だと!? この僅かに生まれる重みと申しますか、手応えみたいなものが、まぁ~運転している印象を変え。なかなかに良いんですよ……これが! 勿論、“ECOモード” なので加速感・エンジン回転数も抑えられるので、NORMALモードの様な軽快さは薄れてしまうも、車速が抑え気味になる御陰? で、気が付けば速度オーバーなんて車速になることなく。一般道路を走行するにはこの “ECOモード” が適切じゃないか!! いやはや、最初からそういってくれればいいじゃないかと思っていた矢先。信号に引っかかり0スタートと走り出したところ、 “ECOモード” ではエンジンを2,000回転以上まで上げないように抑制制御が働き、走り出しが鈍く。ゆっくりと走り出すべく、軽くアクセルペダルを踏む程度ではなんの問題はないのたが。此方の車両が先行車と、やや深めにアクセルペダルを踏み込んでみるや、エンジン回転数を2,000回転でキープしたままの急加速を始め、下手すると、NORMALモードのスタートダッシュ(同じ踏み込み量)より早いんじゃないの? Lvで飛び出すので、“ECOモード” で走り出す際は、必要以上にアクセルペダルを踏み込まない方がいいようだ。それにしても、納車されてから日も浅いからかな? 7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS] (Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステム)の音がなんともぼやっとしていて曇って聞こえる。サラウンド設定で“Premi DIA” のリスニングポジションを “ALL” にして、辛うじて聞けなくもない音になる。こりゃ~しばらく鳴らしっぱなしにしてエージングさせないとアカン奴かな? 音質的なところはさておき。試乗車と比べ、明らかにロードノイズが小さくなっている。察するに、Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステムを装着したことにより、フロントドア・リアドアにデットニングも施されるので、それが遮音性向上に繋がっていると思われる。また、外気温26℃~28℃くらいの環境をAUTOエアコン → 24.0 ℃ 設定で稼動させていたのですが、NORMALモードとエアコンがECOモードでもなくても冷房の効きが良くないような……。そんな風に思うも、そういや愛車には “エアコン添加剤(AC フラーレンC60)” なる物をぶっ込んでいるので、冷房の効きが弱く感じるだけかも? これは “エアコン添加剤” がいいんじゃないかと弱冷房習慣(脳内エコー音追加で)だ!! オーナーである知り合いにそういった商品がある紹介。今なら何と、お試し価格……にはならないが、しじみ……もとい、 “エアコン添加剤” チャンス!! と体感には個人差があるとネタを振ったところで、このまま飲み会の買い出しにでも行くかとなり。某スーパーの駐車場へ入庫しようと駐車券発行機へ車を寄せるべく、パワーウインドウにサイドミラーも畳むかとスイッチ操作をしようとしたところ、パワーウインドウ操作スイッチはドアトリムで、サイドミラー操作スイッチはドアグリップと、いい具合に手の軌道上にドアグリップが……パワーウインドウとサイドミラーを連続しての使い勝手が些か宜しくない事に気が付く。次に車庫入れと、新車がぶつけられないように他の車があまり駐車もしていない駐車スペースへバックで駐車を試みるべく、駐車姿勢に一旦ステアリングを切った後、シストレバーを『R』に入れバックしていたところ。突然、警告音と共にマルチインフォメーションディスプレイ上にデカデカと「ブレーキ!」なる警告表示が!! どうやら、後退時車両検知警告システム[RCTA]が反応した様子。な、なんや!? っと咄嗟にブレーキペダルを踏み込み周囲を見渡すも、危険と判断される対象物が見当たらない。どういうこっちゃとルームミラーに目をやったところ、後方を横切るミニバン……といっても、駐車しようとしていた駐車スペース枠後方の車両通行帯を跨いだ先の駐車スペース……更に奥の車両通行帯を走行するミニバンにだ。ぇ゛……そんな後方・広範囲まで検知するの!? センサーの感度といいますか、性能はかなり凄い事になっているようだ。センサーの感度といえば、一般道路を時速 60 ㎞/hくらいで走行していると、交差点の横断歩道を障害物と検知するのか? 偶に警告音と共にマルチインフォメーションディスプレイ上に「ブレーキ!」なる警告表示がされることがある。おそらく、横断歩道の白線の幅 & 光の反射具合が関係しているんだろうが、カメラ & センサーで映像・空間からこれは○○であるって認識する段階にまでは達していない様なので、レーダークルーズコントロールシステム[ACC]同様、まだまだ進化・発展途上といったところなんでしょうね。買い出しを終え、荷積みをしようとリアシートが一番後ろにスライド & リクライニングで後ろに倒した状態でマイカゴ×1・段ボール×2・ロング缶パック×2の量を入れようとすると積載できない。ここで初めて、左右独立 200 mm のシートスライド機構のありがたみを理解ですよ。この新型車、リアシートが一番後ろにスライドした状態では、RVR(DBA-GA3W/GA4W)の荷室よりやや狭く、リアシートを一番前にスライドさせれば、OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)よりは狭いが、左右独立で動かせるので、リアシートの乗員空間を残しつつ、必要に応じ荷積み空間を調節することが可能なのかと。車両左側の後部座席だけをリクライニングで起し、少しだけスライドで前にずらすだけで、あら不思議。奥さん、刮目して下さいよ! 見て、見て、見て見て見てっと、先程まで積載できなかった荷物が収納出来るんです!! ただ、シートアレンジをする為には、リアドアを開けての~っと回り込む必要があることと、この車両にはディーラーオプションの “トノカバー” が装着されていたのですが、これが使い勝手が悪く。巻き取り式の引っ張る部分が大きく、荷物を入れるのに1度と収納しないと荷積みに邪魔で。荷積みが終わり、 “トノカバー” を引っ張ろうとすると、今度は引っ張る部分が荷物に引っかかり広げられないとくる。純正品とは思えぬ使い勝手の悪さ……これ、必要なのか? こんなんだったら、OUTLANDER(DBA-GF7W / GF8W /DLA-GG2W)等のディーラーオプションである “UV & IRカットフィルム” のスモークで、車内を外から見えづらくした方がいいんじゃないの? なんて思ってしまうも、この新型車にはそのようなディーラーオプションはラインナップされておらず。 “トノカバー” の引っ張る部分をリアゲートに固定できるとか、引っ張る部分がもう少しコンパクトになれば、かなり使い勝手が向上するんじゃないかと。あと、個人的に気になった点として、全グレード標準装備 “本革巻ステアリングホイール” なのだが。手汗などで滑らないように表面に凹凸加工がされているのだが、握り心地がek Wagon ベースグレードに採用されている “ウレタン” ステアリングホイールに近く、なんだか安っぽい握り心地に思えてしまうのだが……これは当方だけかな? そんな新型車を運転させて頂いてから約1ヶ月後。同車両に乗る機会があり、助手席に乗せて頂いて所、ぼやっと曇っていた印象のRockford Fosgate プレミアムサウンドシステムの音がクリアになっており。随分とパワフル(主に重低音)な音を奏でる様になっていた。個人的には、音質調整 “トーンコントロール” の “BASS” 設定を -1 ~ -2 と少し低音を抑える調整にした方が好みではあるが……。更に、AUTOエアコン → 24.0 ℃ 設定なのに、体感的に冷房の効きがいいと感じたので、知り合いに確認をしてみると “エアコン添加剤(AC フラーレンC60)” を入れてみたそうで、冷房設定をやや高めにしてもひんやりするようになったようだ。だが、それ以上の副産物として、なぜか走り出しがじゃっかん良くなったそうで、軽快な走りになったそうな。ここら辺の違いは、実際にオーナーになりBefore・Afterで走り比べないとなんともわからない所ではあるが、愛車でも “エアコン添加剤(AC フラーレンC60)” をぶっ込んだ時、エアコンのON・OFFに関係なく走り出しが改善したので、冷房の利き目以外の目的で “エアコン添加剤” なる商品を試してに入れてみるのもいいのかも知れない(※別の商品・他の車両での効果はわかりませんよ!)。
試乗車含め、色々と運転した感想としては “3G83” のエンジン音(吹き上がり)がえがった~なんて思いなのだが……其はそれとして。この新型車……車名が『ECLIPSE CROSS』と、車名が言いづらい上に、“ECLIPSE” ? 2ドアクーペだろ!! はよ Concept RAの市販車を造れや!!! っと、頑固として新型車を “ECLIPSE” と認めない原理主義的な思いは無きにしも非ずだが。メーカーとし、 “ECLIPSE” の “CROSSOVER” だからと、まぁ~ぶっちゃけ “ECLIPSE” が売れていた “米国” 市場で売りたいSUVだから、ある程度認知されている “ECLIPSE” ネーミングを使ったんだろうなぁ~なんて推測しつつ。なして国内でも同じ車名にしたのだろうか? 疑問を抱いてしまう。この新型車、車両サイズがRVR・OUTLANDERの中間で~とか。クーペスタイルのSUVだとか、色々と説明をされるも。結局この新型車ってどんな立ち位置かよくわからないし、車両サイズ的にも中途半端なんじゃない? なんて思ってしまう方も少なくないだろう。しかし、実際に運転してみて、この新型車を的確に言い表すのであれば “OUTLANDER SPORT” である。この表現であれば、この新型車が一体どんな車両であるか瞬時に理解できるんじゃないでしょうか。ただ、海外市場では既にRVRを “OUTLANDER SPORT” なる車名で販売している所もあるので、国内市場も『ECLIPSE CROSS』で統一することにしたのだろう。それにしても、すったもんだの色々とあった末。やっとの新型車が、なしてライバル車種犇めくコンパクトSUVなんでしょうね。幾らSUVが活気立っている市場……とはいっても、低迷しきっている三自の国内市場で一発逆転を画策するのであれば、『ECLIPSE CROSS』より先にコンパクトSUVミニバンこと
Concept RAの市販車を造れや!!! っと、頑固として新型車を “ECLIPSE” と認めない原理主義的な思いは無きにしも非ずだが。メーカーとし、 “ECLIPSE” の “CROSSOVER” だからと、まぁ~ぶっちゃけ “ECLIPSE” が売れていた “米国” 市場で売りたいSUVだから、ある程度認知されている “ECLIPSE” ネーミングを使ったんだろうなぁ~なんて推測しつつ。なして国内でも同じ車名にしたのだろうか? 疑問を抱いてしまう。この新型車、車両サイズがRVR・OUTLANDERの中間で~とか。クーペスタイルのSUVだとか、色々と説明をされるも。結局この新型車ってどんな立ち位置かよくわからないし、車両サイズ的にも中途半端なんじゃない? なんて思ってしまう方も少なくないだろう。しかし、実際に運転してみて、この新型車を的確に言い表すのであれば “OUTLANDER SPORT” である。この表現であれば、この新型車が一体どんな車両であるか瞬時に理解できるんじゃないでしょうか。ただ、海外市場では既にRVRを “OUTLANDER SPORT” なる車名で販売している所もあるので、国内市場も『ECLIPSE CROSS』で統一することにしたのだろう。それにしても、すったもんだの色々とあった末。やっとの新型車が、なしてライバル車種犇めくコンパクトSUVなんでしょうね。幾らSUVが活気立っている市場……とはいっても、低迷しきっている三自の国内市場で一発逆転を画策するのであれば、『ECLIPSE CROSS』より先にコンパクトSUVミニバンこと “Xpander” を投入(国内市場向けにトランスミッション・エアコン・リアスライドなどの仕様変更が必須だけど)させた方が販売台数的にも良いんじゃないかと個人的には思うも、海外工場(インドネシア・ジャカルタ東部のブカシ工場)で生産車両 & 現地で思わぬ大ヒットと、需要に供給が追っつかない状況等々。国内市場向けに輸入する余裕がないこともあるのだが、わざわざ『ECLIPSE CROSS』を国内で発売したからには、きっと何かしらの車名に意味が込められているのではないか? そんな推察をした当方、考察をしてみることに。まず、真っ先に “CROSS” なるWordに関連し、これは主力販売地域にちなんで “米国” カリフォルニア大学ロサンゼルス校に客員研究員で~なる経歴を持つ “堀 潤” 氏に引っかけているんじゃないか? かと推測するも、わざわざ国内市場向けにアピールする理由付けとしてはあまりにも弱い。なんで『ECLIPSE CROSS』なんだろうと考えること数週間。ある出先で垂れ流されていたTVにて、親の資産を食い潰すで有名な額の汗を札束 or 金地金で拭うある下町のプリンスが登場するや、なななんと! 両腕を “クロス” するポーズをするんですよ!! その画面を見た瞬間、わかっちゃったんですよ。なぜ『ECLIPSE CROSS』を色々とあった後、国内市場第1段として発売する意味が。皆様も、もうお気づきになられたんじゃないですか? 親の資産を食い潰すで有名な額の汗を札束 or 金地金で拭うある下町のプリンスが同じ劇団員で結成したコンビ名が何であったかと。この『ECLIPSE CROSS』に込められた意味を正しく理解できましたよっと、三自関係者に伝えるべく、
“Xpander” を投入(国内市場向けにトランスミッション・エアコン・リアスライドなどの仕様変更が必須だけど)させた方が販売台数的にも良いんじゃないかと個人的には思うも、海外工場(インドネシア・ジャカルタ東部のブカシ工場)で生産車両 & 現地で思わぬ大ヒットと、需要に供給が追っつかない状況等々。国内市場向けに輸入する余裕がないこともあるのだが、わざわざ『ECLIPSE CROSS』を国内で発売したからには、きっと何かしらの車名に意味が込められているのではないか? そんな推察をした当方、考察をしてみることに。まず、真っ先に “CROSS” なるWordに関連し、これは主力販売地域にちなんで “米国” カリフォルニア大学ロサンゼルス校に客員研究員で~なる経歴を持つ “堀 潤” 氏に引っかけているんじゃないか? かと推測するも、わざわざ国内市場向けにアピールする理由付けとしてはあまりにも弱い。なんで『ECLIPSE CROSS』なんだろうと考えること数週間。ある出先で垂れ流されていたTVにて、親の資産を食い潰すで有名な額の汗を札束 or 金地金で拭うある下町のプリンスが登場するや、なななんと! 両腕を “クロス” するポーズをするんですよ!! その画面を見た瞬間、わかっちゃったんですよ。なぜ『ECLIPSE CROSS』を色々とあった後、国内市場第1段として発売する意味が。皆様も、もうお気づきになられたんじゃないですか? 親の資産を食い潰すで有名な額の汗を札束 or 金地金で拭うある下町のプリンスが同じ劇団員で結成したコンビ名が何であったかと。この『ECLIPSE CROSS』に込められた意味を正しく理解できましたよっと、三自関係者に伝えるべく、 『ECLIPSE CROSS』のレビュー・試乗動画などの情報を発信する際には、額の汗を札束 or 金地金で拭うという下りを入れないとね……あ、この人なんもわかっちゃいねぇ~なっと、鼻で笑われちゃいますよ。ようやく分析に成功(?)出来たところで、この新型車こと『ECLIPSE CROSS』。掲示板などで、2WDか4WDこと “スーパーオールホイールコンチョロォォル” の何方が買いか? なる論争を見かけることもあるが、ちょっと待てと。この新型車は駆動方式も然る事ながら、メーカーオプション装着有無による違いも考慮していなければならない。当方が運転した4WDモデルでも、電動パノラマサンルーフ・Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステムの装着有無の違いで加速感・乗り心地・ロードノイズが異なる事からわかるように。如何にこの新型車は車両総重量の違いが大きく軽快な走り・乗り心地の影響するので、2WD or 4WDの何方がいい? ではなく。オーナーになろうとしている自分はどんな走りを欲しているのか? を理解した上で駆動方式・グレード・メーカーオプションの組み合わせを検討すべきかと思う。個人的には、後部座席に人を乗せることを考慮し。4WD G以上のグレードに電動パノラマサンルーフと
『ECLIPSE CROSS』のレビュー・試乗動画などの情報を発信する際には、額の汗を札束 or 金地金で拭うという下りを入れないとね……あ、この人なんもわかっちゃいねぇ~なっと、鼻で笑われちゃいますよ。ようやく分析に成功(?)出来たところで、この新型車こと『ECLIPSE CROSS』。掲示板などで、2WDか4WDこと “スーパーオールホイールコンチョロォォル” の何方が買いか? なる論争を見かけることもあるが、ちょっと待てと。この新型車は駆動方式も然る事ながら、メーカーオプション装着有無による違いも考慮していなければならない。当方が運転した4WDモデルでも、電動パノラマサンルーフ・Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステムの装着有無の違いで加速感・乗り心地・ロードノイズが異なる事からわかるように。如何にこの新型車は車両総重量の違いが大きく軽快な走り・乗り心地の影響するので、2WD or 4WDの何方がいい? ではなく。オーナーになろうとしている自分はどんな走りを欲しているのか? を理解した上で駆動方式・グレード・メーカーオプションの組み合わせを検討すべきかと思う。個人的には、後部座席に人を乗せることを考慮し。4WD G以上のグレードに電動パノラマサンルーフと 本革シート+運転席パワーシート+運転席・助手席シートヒーターで座席全体の座り心地向上(通常のシートと座り比べてないので確かではないが)を図り、納車後にカーオーディオ専門店などでデットニングを施して貰うなんてのがいいんじゃないかと。ただ、それ以前にこの新型車が買いか? となると、CVT制御(特に低速域)なり、色々と改良が必要と思われる点も多く見受けられるので早急に車が必要・買換が~なんて逼迫している事情がないのであれば、1~2回のMCで様子を見つつ。国内市場にも導入? されると思われる本命の 2.2 L DI-Dモデルなり。Concept CAR 時点でPHEVモデルにしていたということは、本来 “PHEV” こそがこの新型車の完成形なのでは? なんて、勝手な憶測を元に、懐を暖めておくというのも……一つの選択肢かと。また、1.5 L ガソリンエンジンモデルでも、CVTをより高負荷に耐えうる物へランク⤴させるなり、海外販売モデルでラインナップされている “MT” と組み合わせて、1.5 L ガソリンエンジンをフルに生かせる特別限定仕様車を、期間限定で~なんて売り出し方をするのもえぇんじゃないかと。何はともあれ、この新型車が秘めている基本性能が尋常ではないことがわかったので、これからどうMCでLv⤴していくのか見物である。
本革シート+運転席パワーシート+運転席・助手席シートヒーターで座席全体の座り心地向上(通常のシートと座り比べてないので確かではないが)を図り、納車後にカーオーディオ専門店などでデットニングを施して貰うなんてのがいいんじゃないかと。ただ、それ以前にこの新型車が買いか? となると、CVT制御(特に低速域)なり、色々と改良が必要と思われる点も多く見受けられるので早急に車が必要・買換が~なんて逼迫している事情がないのであれば、1~2回のMCで様子を見つつ。国内市場にも導入? されると思われる本命の 2.2 L DI-Dモデルなり。Concept CAR 時点でPHEVモデルにしていたということは、本来 “PHEV” こそがこの新型車の完成形なのでは? なんて、勝手な憶測を元に、懐を暖めておくというのも……一つの選択肢かと。また、1.5 L ガソリンエンジンモデルでも、CVTをより高負荷に耐えうる物へランク⤴させるなり、海外販売モデルでラインナップされている “MT” と組み合わせて、1.5 L ガソリンエンジンをフルに生かせる特別限定仕様車を、期間限定で~なんて売り出し方をするのもえぇんじゃないかと。何はともあれ、この新型車が秘めている基本性能が尋常ではないことがわかったので、これからどうMCでLv⤴していくのか見物である。
追記 9月13日、この新型車含む4車種に “リコール” が発表され。1つ目(リコール届出番号:4321)は “ブレーキハイドロリックユニット” なる制動装置に不具合があるんだとかで、ハイドロリックユニットのポンプモーター制御の切り替え時に電気的なノイズが発生し、それが原因で制動装置の制御が一時的に中断される場合があるんだとか。2つ目(改善対策届出番号:552)は衝突被害軽減ブレーキシステムで、前方に衝突の可能性がある歩行者を検知した際。衝突被害軽減ブレーキシステムが作動する時間設定を長めにしてある為、運転者(ドライバー)が不要な急制動(急ブレーキ)を誘発する恐れがあるんだそうだ。最後の3つ目(サービスキャンペーン)に関しては、この新型車のみで。なんでも“エンジンECU” の制御プログラムに不適切な所があり。クルーズコントロールで走行中、パドルシフト操作をすると制御プログラムが故障と誤判定する場合があるんだとかで、警告灯が点灯!? フェールセーフでエンジン出力が制限されるんだとか。いずれも部品(ハードウェア)の問題ではなく、制御プログラム(ソフトウェア)の不具合で、対策制御プログラムに書き換え(修正パッチを適応)すればOKなんだそうだ。然し “リコール” と一括りに発表しているが、届出項目が “改善対策” とか “サービスキャンペーン” と……表現が異なっているのは何でじゃ? 何かしらの定義・規定があるんかな??? 虚けな当方にはさっぱり。そんな残念な知識しか無いので、本当に今更ながら…… “リコール” について調べた所。
“リコール” について調べた所。 何でもかんでも不具合を “リコール” と括ってしまうと色々と管理する側(国土交通省)としても問題になるので、不具合内容によって “リコール” “改善対策” “サービスキャンペーン” と表現をわけているそうな。因みに、製造・販売しているメーカーより “リコール” の発表がされているにも関わらず。ユーザー(ドライバー)が販売店などで速やかにリコール改修をしないと、道路運送車両法 の第47条 を怠ったとして、ユーザー(ドライバー)の責任が問われるんで、リコール情報は定期的に確認をした方がいいんだとか。具体的に責任が問われるって? なんなんよって事なんですが、例えば街頭検査・検問などで『整備命令』が言い渡される!? ……なんてことはないが。仮にリコール届出番号:4274の制動装置(ブレーキマスターシリンダー)に問題があり。ブレーキペダルをゆっくり踏むとブレーキ液が漏れ、制動距離が長くなるおそれが~ってものや、リコール届出番号:4275のエンジンルームの遮音材とエキゾーストマニホールドとの隙間が少なく。遮音材に固定していない部分がある為、エキゾーストマニホールドの熱で火災に至っちゃう可能性も~なんてリコール発表 or リコール通知が来ても「何言ってんの? 今までなんの問題なく走行できたんだから、時間のかかるリコールなんて受けてられねぇ」っと、運転していたら追突事故なり車両火災が!? 製造・販売しているメーカーの責任が~っと、騒いだとしても。速やかにリコール改修をしなかったユーザー(ドライバー)にも責任があるとなるので、リコール通知が来たら素直にリコール改修をした方がいいそうですよ。また、リコール改修をしていないと
何でもかんでも不具合を “リコール” と括ってしまうと色々と管理する側(国土交通省)としても問題になるので、不具合内容によって “リコール” “改善対策” “サービスキャンペーン” と表現をわけているそうな。因みに、製造・販売しているメーカーより “リコール” の発表がされているにも関わらず。ユーザー(ドライバー)が販売店などで速やかにリコール改修をしないと、道路運送車両法 の第47条 を怠ったとして、ユーザー(ドライバー)の責任が問われるんで、リコール情報は定期的に確認をした方がいいんだとか。具体的に責任が問われるって? なんなんよって事なんですが、例えば街頭検査・検問などで『整備命令』が言い渡される!? ……なんてことはないが。仮にリコール届出番号:4274の制動装置(ブレーキマスターシリンダー)に問題があり。ブレーキペダルをゆっくり踏むとブレーキ液が漏れ、制動距離が長くなるおそれが~ってものや、リコール届出番号:4275のエンジンルームの遮音材とエキゾーストマニホールドとの隙間が少なく。遮音材に固定していない部分がある為、エキゾーストマニホールドの熱で火災に至っちゃう可能性も~なんてリコール発表 or リコール通知が来ても「何言ってんの? 今までなんの問題なく走行できたんだから、時間のかかるリコールなんて受けてられねぇ」っと、運転していたら追突事故なり車両火災が!? 製造・販売しているメーカーの責任が~っと、騒いだとしても。速やかにリコール改修をしなかったユーザー(ドライバー)にも責任があるとなるので、リコール通知が来たら素直にリコール改修をした方がいいそうですよ。また、リコール改修をしていないと “車検” が通らなくなる場合があるので。何方にしろ、ユーザー(ドライバー)の責任として販売店へ連絡・入庫しろってこと事みたいです。そんな “リコール” 発表されたこの新型車。3つ目の “サービスキャンペーン” なる改善内容が “エンジンECU” の制御プログラムの書き換えとあり。いつもの三自のこと……これは修正パッチと、いいながら制御プログラムをアップグレードしているんじゃないか? なんて思っていたところ、知り合いの新型車(G PLUS PACKAGE 4WD(メーカーオプション:7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS] (Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステム)・電動パノラマサンルーフ)のタイヤは標準装備(TOYO PROXES R44 225/55R18 98H)でオドメーターは約5,000 ㎞。試乗環境 → 2人乗車。AUTOエアコン → 25.0 ℃ 設定。S-AWCドライブモード → AUTO。走行場所 → 生活道路 ~ 国道)に再度運転させて頂く機会が出来。NORMALモードである事を確認した後、アクセルペダルを軽く踏み込んだ瞬間! 脳内でSEと共に“Lv ⤴ ですぜ! この新型車も、成長したもんだ” なる謎のテロップが!? まず驚いたのが、アクセルペダルに僅かな重さを入れたようで、踏みごたえがあり。ステアリング操舵も僅かに手応えのある重さに変わっていて “ECOモード” になっているんじゃないかとマルチインフォメーションディスプレイを確認してしまう程、以前のNORMALモードとは運転の手応えが違うではないか!! 読み通り? ただ不適切な箇所の対策制御プログラムに書き換えた……だけでなく。大幅に制御プログラム全体に手を入れているようだ。これは期待しちゃって良いのかなっと、走り出したところ。サービスキャンペーン以前の制御プログラムでは、エンジン回転数を1,900回転 ~ 2,100回転辺りで時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h まで加速したら、そこからエンジン回転数を落とし、1,100回転 ~ 1,300回転と低回転で法定速度に達し巡航するといった制御プログラムだったのに対し。サービスキャンペーン以降では、出だし時速 20 ㎞/h くらいまではエンジン回転数を1,900回転 ~ 2,100回転辺りまでエンジン回転を一時的に上げるも、そこから先はエンジン回転数を1,400回転 ~1,800回転辺りの領域を使い加速をし、法定速度 or 巡航速度になる頃にはエンジン回転数が1,100回転 ~ 1,300回転という3段階に分ける制御にしたようだ。体感的に加速区間である時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h 辺りのエンジン回転数が1,800回転前後で加速していた以前の制御プログラムに比べてしまうと、エンジン出力を抑えられている感覚にさいなまれ。軽快な加速感が薄れてしまった印象を受ける。恐らく、購入したオーナーさん方から「思ったより燃費が伸びない」等の御意見を頂いたからかな? 実質燃費を伸ばす為、ややエンジン回転を抑制する制御プログラムに変更したようだ。個人的に気になっていた、巡航速度で走行していると、アクセルペダルの踏み加減を変えていないのにトルクコンバータが上乗せされたかのようにトルク感が増し。気が付けば速度オーバーに!? なんてのは改善され、法定速度を維持したままでの巡航(速度調整)が楽に可能となった。また、減速してからの再加速時に意図しない急加速制御が!? ってな部分も試したところ。これも時速 20 ㎞/h までは低速ギアで引っ張り急加速!! なんて事もなくなり。減速から徐行発進といった場面でのサービスキャンペーン以前のアクセルペダルの踏み加減みたく、気を利かせなくとも穏やかに徐行発進・再加速が可能となっていた。ついでに “ECOモード” も試してみるかと、走行モードを切り替えた所。NORMALモード同様に此方も制御プログラムを変更したようで。 “ECOモード” もサービスキャンペーン以前の “ECOモード” よりステアリング・アクセルペダルの重さがじゃっかん増していた。0スタート時の走り出しに関しても、此方も3段階に分ける制御になっており。時速 20 ㎞/h くらいまではエンジン回転数を1,900回転辺りで車速を上げたところで、そこからエンジン回転数を1,500回転まで下げ、そのまま1,500回転キープし続け加速するのだが。これ以上はエンジン回転数を上げさせへんで!! っと、エンジン出力を抑制し続け加速をするもんだから、これが某ローグライグGAMEで言うところの “鈍足状態” に陥ったかのような感覚で加速区間が続く。やっとこさ、法定速度 or 巡航速度になる頃には1,100回転 ~ 1,300回転で走行しているんですけどね……燃費的に、それなりに向上はするんだろうけど。NORMALモードの軽快さを体感しちゃっているとね……。なんだかなぁ~っと苦笑をせざるを得ない加速感な訳ですが。暫く運転して気付く……生活道路とか交通量が多く、車列の流れにダラダラっとついて行く程度の大して加速も必要とされない走行シーンおいて、このゲンナリしてしまうエンジン出力が抑制されたくらいが丁度良い事に。街乗りくらいなら “ECOモード” で十分かなっと思っていたところ、一時停止で一旦完全停車をした後、アクセルペダルを軽く踏み込んでみた際。突然急加速!? っと、サービスキャンペーン以前の2,000回転キープでスタートダッシュ制御が顔を出す。あれ? NORMALモードでは、こんな挙動しなかったのに…… “ECOモード” の制御プログラムに関しては、もうちょい調整が必要なんじゃないかと思いつつ。一時停止が多く設置されている生活道路では、NORMALモードの方が運転しやすい(試した限り)と思われる。とりあえず、サービスキャンペーンと、不適切な所を改善しました~っと、公式的には謳っているが。その実、年式変更のMC並の制御プログラムに手が加えられており。サービスキャンペーン以前では、車両の性能が凄いって事は分かるんだけど……街乗りにおいては手を余すというか、しっくりこないんだよねぇ~なんて制御プログラムが全体的に街乗り仕様に調整がなされ。今回、生活道路 ~ 国道を走った限りではありますが、なかなかに運転のしやすい調整に仕上がっていた。ただ、その反動として街乗り仕様にしてしまったが故に、あの車両重量を感じさせない軽快さのある加速感が薄れてしまい。ワインディングロード・クローズドサーキット等を走行した際の感じはどうなんだろ? とか、思ってしまう。車の性能だとか、軽快さではなく。衝突軽減ブレーキ等の安全装置が一通り付いている車両だから~なんて、街乗り中心に使用しているオーナーが乗り換えで購入した分には、この調整でいいんだけど。この新型車のコンセプトというか、キャラクターとして良い物なのかと考えながら運転していると、走行距離も伸び、足回りも大分馴染んできたからか、足回りがよく動き。乗り心地が軽やなんですよね。そんな車の方向性を考えるに、この新型車の性能・面白さを生かす為の街乗りとか、燃費なんざ関係ない!! ガンガンにエンジンぶん回して、軽快に行きましょう♪ 的な、SPORTSモード(仮)を設けてもいいし。なんなら、足回りをBILSTEINにしたS Edition(仮) なり Version-R(仮)のグレードを期間限定・台数限定でも企画するもいいんじゃないかと。
“車検” が通らなくなる場合があるので。何方にしろ、ユーザー(ドライバー)の責任として販売店へ連絡・入庫しろってこと事みたいです。そんな “リコール” 発表されたこの新型車。3つ目の “サービスキャンペーン” なる改善内容が “エンジンECU” の制御プログラムの書き換えとあり。いつもの三自のこと……これは修正パッチと、いいながら制御プログラムをアップグレードしているんじゃないか? なんて思っていたところ、知り合いの新型車(G PLUS PACKAGE 4WD(メーカーオプション:7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS] (Rockford Fosgate プレミアムサウンドシステム)・電動パノラマサンルーフ)のタイヤは標準装備(TOYO PROXES R44 225/55R18 98H)でオドメーターは約5,000 ㎞。試乗環境 → 2人乗車。AUTOエアコン → 25.0 ℃ 設定。S-AWCドライブモード → AUTO。走行場所 → 生活道路 ~ 国道)に再度運転させて頂く機会が出来。NORMALモードである事を確認した後、アクセルペダルを軽く踏み込んだ瞬間! 脳内でSEと共に“Lv ⤴ ですぜ! この新型車も、成長したもんだ” なる謎のテロップが!? まず驚いたのが、アクセルペダルに僅かな重さを入れたようで、踏みごたえがあり。ステアリング操舵も僅かに手応えのある重さに変わっていて “ECOモード” になっているんじゃないかとマルチインフォメーションディスプレイを確認してしまう程、以前のNORMALモードとは運転の手応えが違うではないか!! 読み通り? ただ不適切な箇所の対策制御プログラムに書き換えた……だけでなく。大幅に制御プログラム全体に手を入れているようだ。これは期待しちゃって良いのかなっと、走り出したところ。サービスキャンペーン以前の制御プログラムでは、エンジン回転数を1,900回転 ~ 2,100回転辺りで時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h まで加速したら、そこからエンジン回転数を落とし、1,100回転 ~ 1,300回転と低回転で法定速度に達し巡航するといった制御プログラムだったのに対し。サービスキャンペーン以降では、出だし時速 20 ㎞/h くらいまではエンジン回転数を1,900回転 ~ 2,100回転辺りまでエンジン回転を一時的に上げるも、そこから先はエンジン回転数を1,400回転 ~1,800回転辺りの領域を使い加速をし、法定速度 or 巡航速度になる頃にはエンジン回転数が1,100回転 ~ 1,300回転という3段階に分ける制御にしたようだ。体感的に加速区間である時速 30 ㎞/h ~ 40 ㎞/h 辺りのエンジン回転数が1,800回転前後で加速していた以前の制御プログラムに比べてしまうと、エンジン出力を抑えられている感覚にさいなまれ。軽快な加速感が薄れてしまった印象を受ける。恐らく、購入したオーナーさん方から「思ったより燃費が伸びない」等の御意見を頂いたからかな? 実質燃費を伸ばす為、ややエンジン回転を抑制する制御プログラムに変更したようだ。個人的に気になっていた、巡航速度で走行していると、アクセルペダルの踏み加減を変えていないのにトルクコンバータが上乗せされたかのようにトルク感が増し。気が付けば速度オーバーに!? なんてのは改善され、法定速度を維持したままでの巡航(速度調整)が楽に可能となった。また、減速してからの再加速時に意図しない急加速制御が!? ってな部分も試したところ。これも時速 20 ㎞/h までは低速ギアで引っ張り急加速!! なんて事もなくなり。減速から徐行発進といった場面でのサービスキャンペーン以前のアクセルペダルの踏み加減みたく、気を利かせなくとも穏やかに徐行発進・再加速が可能となっていた。ついでに “ECOモード” も試してみるかと、走行モードを切り替えた所。NORMALモード同様に此方も制御プログラムを変更したようで。 “ECOモード” もサービスキャンペーン以前の “ECOモード” よりステアリング・アクセルペダルの重さがじゃっかん増していた。0スタート時の走り出しに関しても、此方も3段階に分ける制御になっており。時速 20 ㎞/h くらいまではエンジン回転数を1,900回転辺りで車速を上げたところで、そこからエンジン回転数を1,500回転まで下げ、そのまま1,500回転キープし続け加速するのだが。これ以上はエンジン回転数を上げさせへんで!! っと、エンジン出力を抑制し続け加速をするもんだから、これが某ローグライグGAMEで言うところの “鈍足状態” に陥ったかのような感覚で加速区間が続く。やっとこさ、法定速度 or 巡航速度になる頃には1,100回転 ~ 1,300回転で走行しているんですけどね……燃費的に、それなりに向上はするんだろうけど。NORMALモードの軽快さを体感しちゃっているとね……。なんだかなぁ~っと苦笑をせざるを得ない加速感な訳ですが。暫く運転して気付く……生活道路とか交通量が多く、車列の流れにダラダラっとついて行く程度の大して加速も必要とされない走行シーンおいて、このゲンナリしてしまうエンジン出力が抑制されたくらいが丁度良い事に。街乗りくらいなら “ECOモード” で十分かなっと思っていたところ、一時停止で一旦完全停車をした後、アクセルペダルを軽く踏み込んでみた際。突然急加速!? っと、サービスキャンペーン以前の2,000回転キープでスタートダッシュ制御が顔を出す。あれ? NORMALモードでは、こんな挙動しなかったのに…… “ECOモード” の制御プログラムに関しては、もうちょい調整が必要なんじゃないかと思いつつ。一時停止が多く設置されている生活道路では、NORMALモードの方が運転しやすい(試した限り)と思われる。とりあえず、サービスキャンペーンと、不適切な所を改善しました~っと、公式的には謳っているが。その実、年式変更のMC並の制御プログラムに手が加えられており。サービスキャンペーン以前では、車両の性能が凄いって事は分かるんだけど……街乗りにおいては手を余すというか、しっくりこないんだよねぇ~なんて制御プログラムが全体的に街乗り仕様に調整がなされ。今回、生活道路 ~ 国道を走った限りではありますが、なかなかに運転のしやすい調整に仕上がっていた。ただ、その反動として街乗り仕様にしてしまったが故に、あの車両重量を感じさせない軽快さのある加速感が薄れてしまい。ワインディングロード・クローズドサーキット等を走行した際の感じはどうなんだろ? とか、思ってしまう。車の性能だとか、軽快さではなく。衝突軽減ブレーキ等の安全装置が一通り付いている車両だから~なんて、街乗り中心に使用しているオーナーが乗り換えで購入した分には、この調整でいいんだけど。この新型車のコンセプトというか、キャラクターとして良い物なのかと考えながら運転していると、走行距離も伸び、足回りも大分馴染んできたからか、足回りがよく動き。乗り心地が軽やなんですよね。そんな車の方向性を考えるに、この新型車の性能・面白さを生かす為の街乗りとか、燃費なんざ関係ない!! ガンガンにエンジンぶん回して、軽快に行きましょう♪ 的な、SPORTSモード(仮)を設けてもいいし。なんなら、足回りをBILSTEINにしたS Edition(仮) なり Version-R(仮)のグレードを期間限定・台数限定でも企画するもいいんじゃないかと。